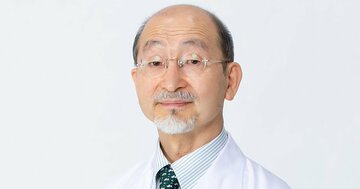AIに行動を委ねるほど弱まっていく
「主体的に生きている」という実感
人の幸福は非常に主観的で、人それぞれの多様な文脈に依存しています。
誰かにとっては、散歩の途中で偶然見つけた喫茶店が一日のハイライトになります。誰かにとっては、仕事での小さな成功が自己肯定感を育てます。また別の誰かにとっては、ペットとの静かな時間こそが心を整えてくれます。
AIが扱うデータとは、このような「人それぞれの幸福の瞬間」ではありません。あくまでも平均化されたパターンであり、そこには「あなた自身の物語」も「その日の気分の揺らぎ」も存在しません。なぜならAIは、人間がウェルビーイングを感じる上で不可欠な「偶然」「非合理」「主観性」といった要素を本質的には理解できないからです。
さらに言えば、AIに行動を委ねるほど、人間の主体性が徐々に弱まる懸念もあります。人のウェルビーイングにとって、自分が主体的に生きているという実感が非常に重要であることはさまざまな研究によって明らかになっています。
AIが「これが効率的です」と提案し続けると、私たちは「自分はどうしたいのか」「何が心地よいのか」という内的な問いを立てる機会を失います。主体性が薄れれば、幸福の感受性もまた鈍っていきます。結果として、AIに導かれた「効率的な人生」は、表面上は便利でも、深層において、「自分が生きている実感」を損ないかねません。
ウェルビーイングとは、本来「自分で選び取る」プロセスに価値を置く概念です。選択した内容そのものが幸福をもたらすのではなく、「選択した」という事実が人間の尊厳や主体性を支えます。
ところが、AIが高度になるほど、この選択のプロセスは削ぎ落とされていきます。SNSでのレコメンド、健康アプリの最適化指示、職場の業務効率化ツール。どれも意思決定の負担を軽くしますが、その裏で「決める」という人間の根源的な力が薄れていく側面もあります。
AIの普及が人間のウェルビーイングの低下につながるという可能性は、まさにこの点に原因があります。私たちは便利さの代償として、「自分の物語を生きる力」をそっと手放し始めているのかもしれません。