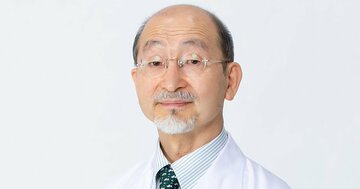AIがどれほど賢くなっても
人間を超えられないものとは?
AIが返す完全な正解よりも、少し不器用で、少し遠回りで、しかし心が触れ合うような手触り感のあるやり取りの中にこそ、ウェルビーイングの土壌は存在していたはずです。
AIは「正しさ」の提供において圧倒的に強い存在です。健康、仕事、習慣、金融、恋愛、教育など、多くの意思決定をAIが最適化できる未来は目前です。しかし意思決定の一部をAIに委ねるたび、人間は「自分が選んだ」という感覚を少しずつ失います。
さらに深刻なのは、社会全体が「幸福=効率」と誤認しはじめることです。
・最適な運動
・最適な睡眠
・最適な食事
・最適な働き方
・最適な人間関係
これらすべてが「最適化」で語られ、「最適化されていない状態」が正常ではないかのように扱われます。その結果、幸福の定義そのものがAIに飲み込まれ、人間が本来持っていた「非効率で豊かな幸福」への許容性が弱まっていきます。
幸福は最適化と均質化だけでは育ちません。幸福は予測不能な非効率の余白で育ちます。AIが社会の前提となったとき、これらの本質的な幸福の構造は見えにくくなる可能性があるのです。
だからといってAIに抗う必要はありません。むしろAIと共存しながら、「人間だけが担える領域」を強く意識し直すことが重要です。
AIは選択肢を提示できますが、人の人生を編集することはできません。編集とは「意味づけ」であり、意味づけとは主体性そのものです。AIがどれほど賢くなっても、私たちが自分の過去や未来の意味を語る力までは奪えません。
AIが便利なコミュニケーションを提供するほど、人と人の間に生じる「偶然の温度」が希少になります。私たちはこの温度の意味を意識的に守る必要があります。AIは平均化を進めますが、人間は多様性から豊かさを生み出します。異なる価値観を理解し、橋渡しをする力は人間だけが持つ創造性です。
AI時代のウェルビーイングデザインとは何か。端的に言えば、それは「AIの助けを借りて、人間が物語を描く社会」をつくることです。
AIは計算し、解析し、提案します。しかしその提案に意味を吹き込むのは人間です。AIが道具になり、人間が主体となる構造を保つことで、ウェルビーイングは損なわれるどころか、むしろAIを使いながら自分らしさをより高めることができるのです。
最適化の世界に埋没せず、偶然や非効率の価値を再発見すること。そこにこそ、AI時代におけるウェルビーイングを支える核心があると私は考えています。
(インテグレート代表取締役CEO 藤田康人)