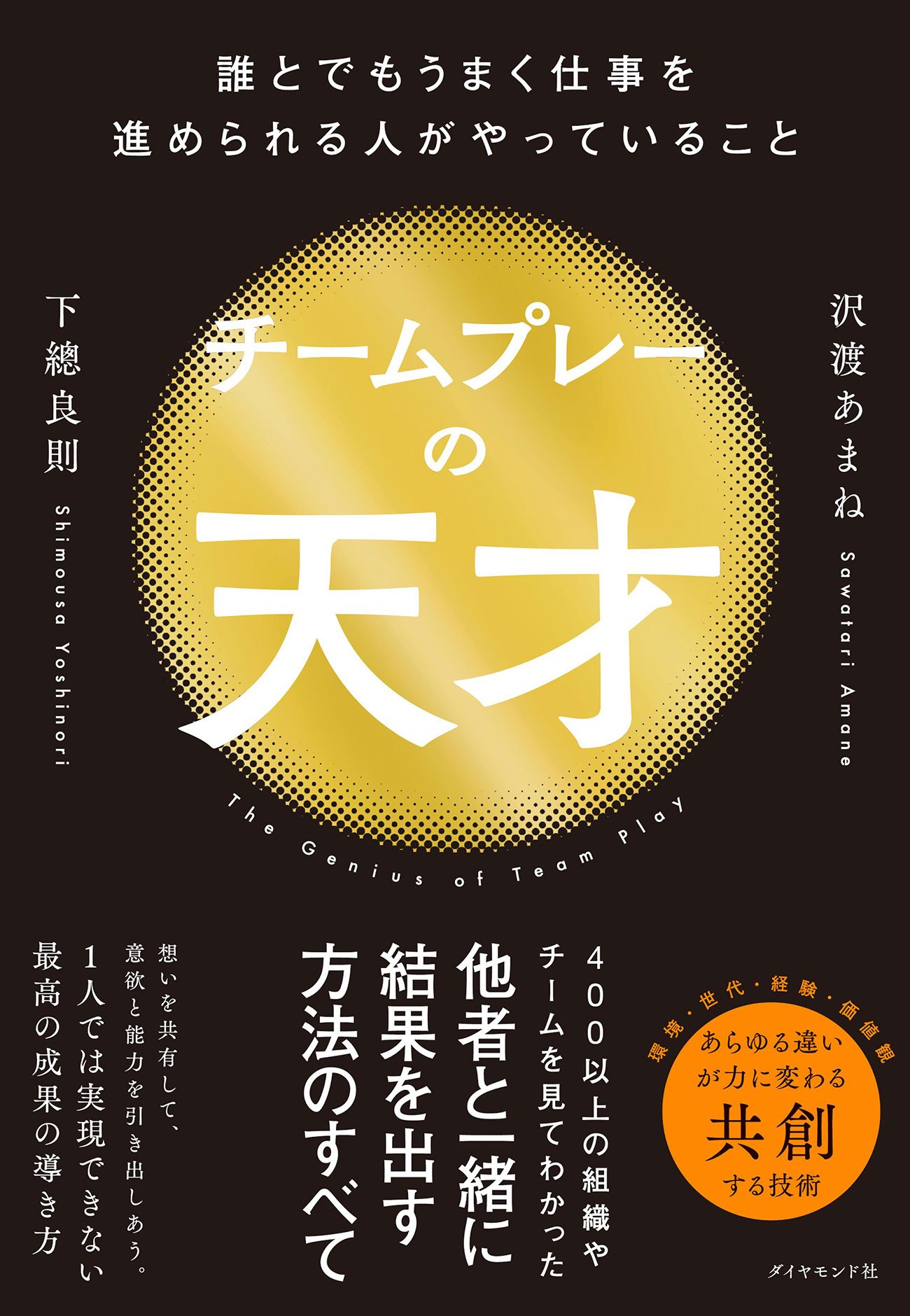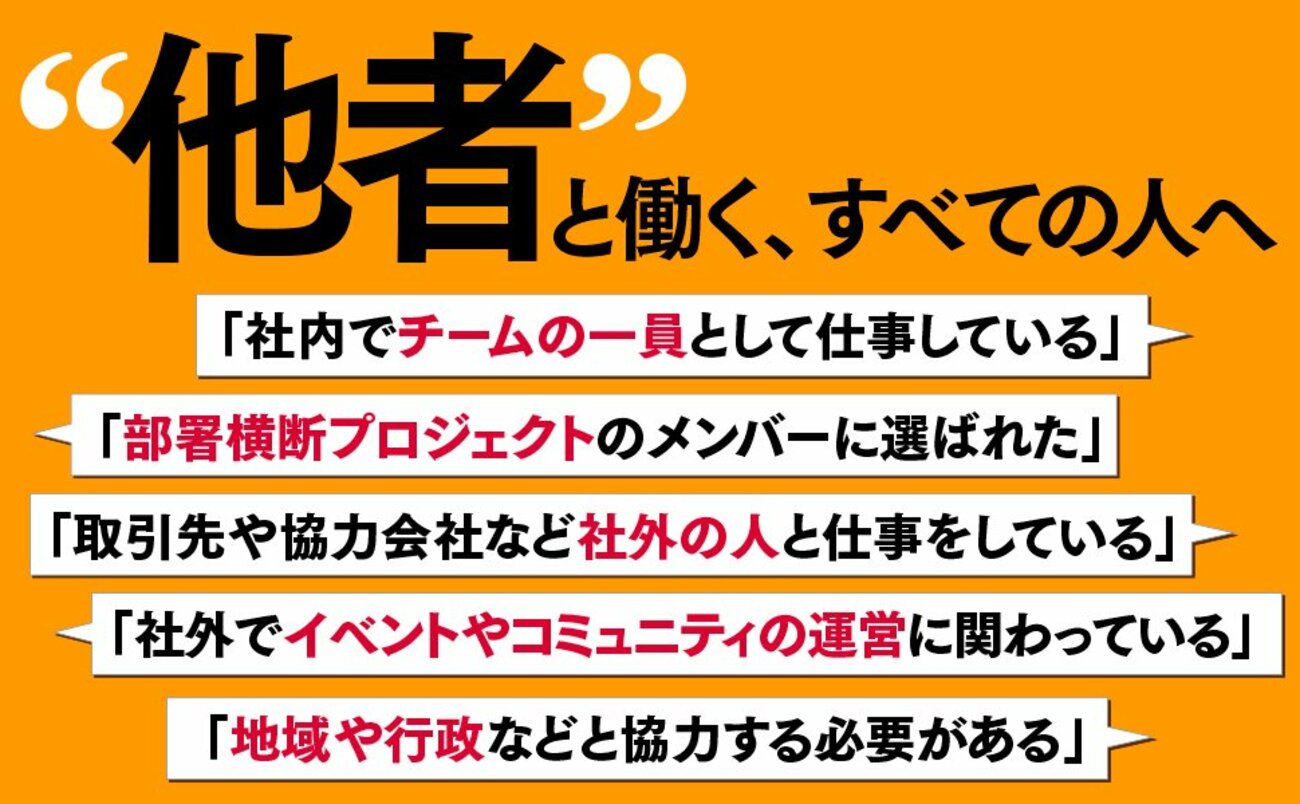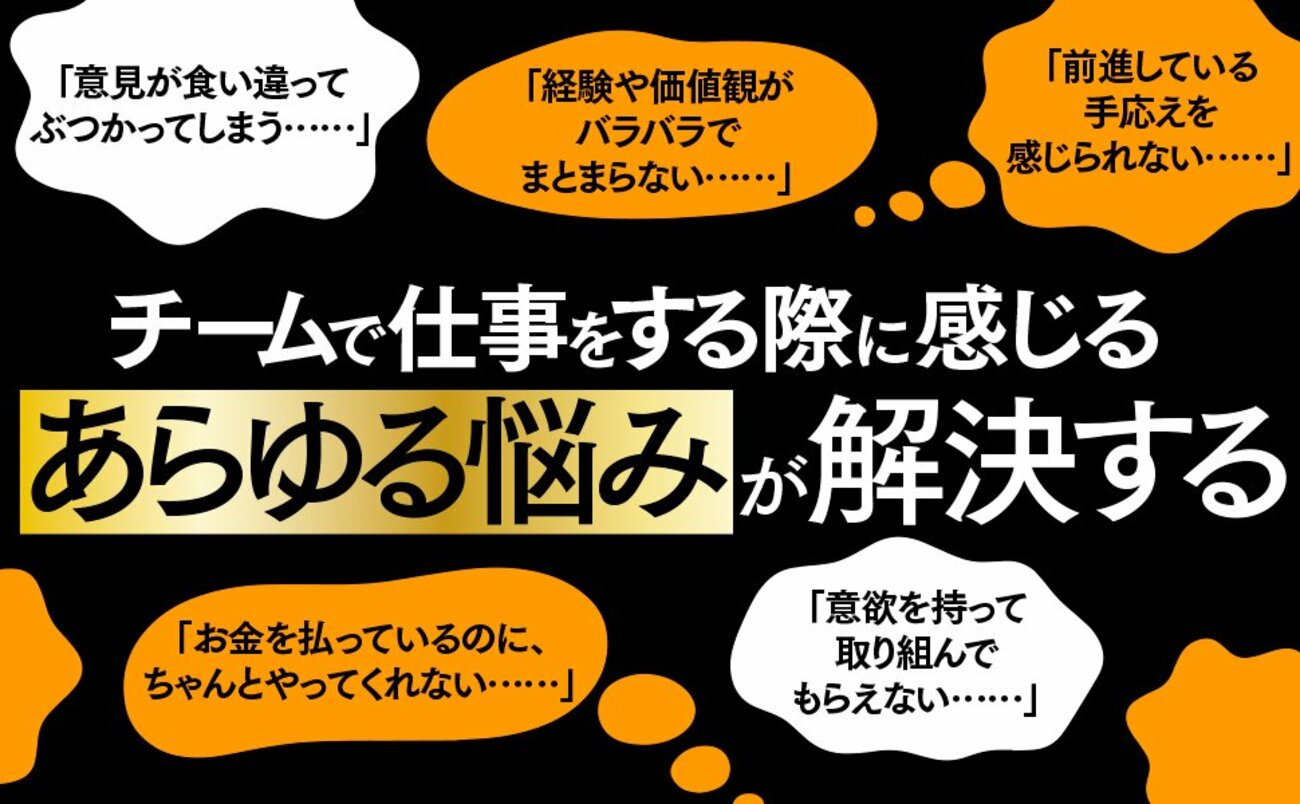「計画どおりに進まないとイライラする」「想定外の展開が苦手」――。そんな“こだわり”が強いほど、周囲の人に見えないストレスを与えてしまう。なぜなら、仕事には必ず“偶然”や“想定外”が起きるものだから。では、そんな事態とどう向き合えばいいのだろう。その答えを教えてくれるのが、400以上のチームを見てわかった「仲間と協力するのがうまい人の共通点」をまとめた書籍『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』(沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊)だ。「あらゆる仕事仲間との関係性が良くなる」と話題の一冊から、その内容を紹介しよう。(構成/ダイヤモンド社・石井一穂)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「計画通りに進まない」というストレス
チームで仕事を進める際、メンバーや周囲の協力者に必要な情報を伝えて「納得」によって参画してもらうことが大切です。
そのためには「ものがたり」、すなわちストーリーがカギとなります。
ただ、活動の初期でいきなりストーリーを描こうとしてもうまくいかないかもしれません。
先々のことがわからなかったり、ガチガチにストーリーを描いてしまったあまりに計画通りに進まないストレスをメンバーが感じたりすることもあります。
ストーリー創りを焦らない。一緒に走りながら、活動を共にしながらストーリーを描いていく。そのスタンスも大切にして、とにかく前に進みましょう。
「想定内」だけが、ストーリーではない
想定外の気づきや出会いによって計画を変えることもあります。
計画されたストーリーだけでなく、「後づけのストーリー」も存在するのです。
それぞれ必然のストーリーと偶然のストーリーと言い換えることもできるでしょう。
計画されたストーリー(または必然のストーリー)とは、文字どおり事前の計画どおりに「想定内」でものごとが進み、結実したさまを示します。
ある企業が40代男性向けの新しい健康食品を開発し販売したとしましょう。目論見どおりその食品は40代男性の支持を得て、売上も順調に伸び始めた。これは計画されたストーリーです。
「偶然のストーリー」に目を向けて、受け入れる
これに対して後づけのストーリー(または偶然のストーリー)はいわば「想定外」。
その食品は、ふたを開けてみたら、または開発の途中で40代の男性にはウケそうにないことがわかった。それどころか、人間ではなく牛や豚などの家畜に好まれ、かつ健康で栄養価の高い肉質にすることが判明した。
たまたま試食会に参加していた大学畜産学部の教授の一言がきっかけで、開発チームはその可能性に気づいた。
そこで当初の計画を変更し、食用の牛と豚向けの飼料として売り出すことにした。
これが後づけのストーリーです。
当初の思いや計画どおりにものごとを進めるよう努力するのも大事ですが、そのマインドがリーダーやチームに強すぎると、意外な可能性やチャンスを見失ってしまうこともあります。
偶然の産物、および後づけのストーリーも大切にしましょう。
(本稿は、書籍『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です)