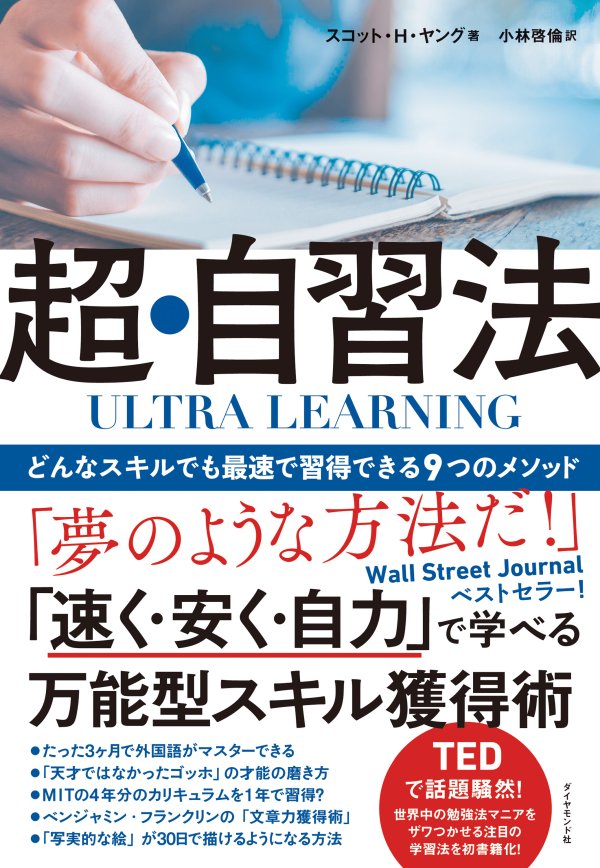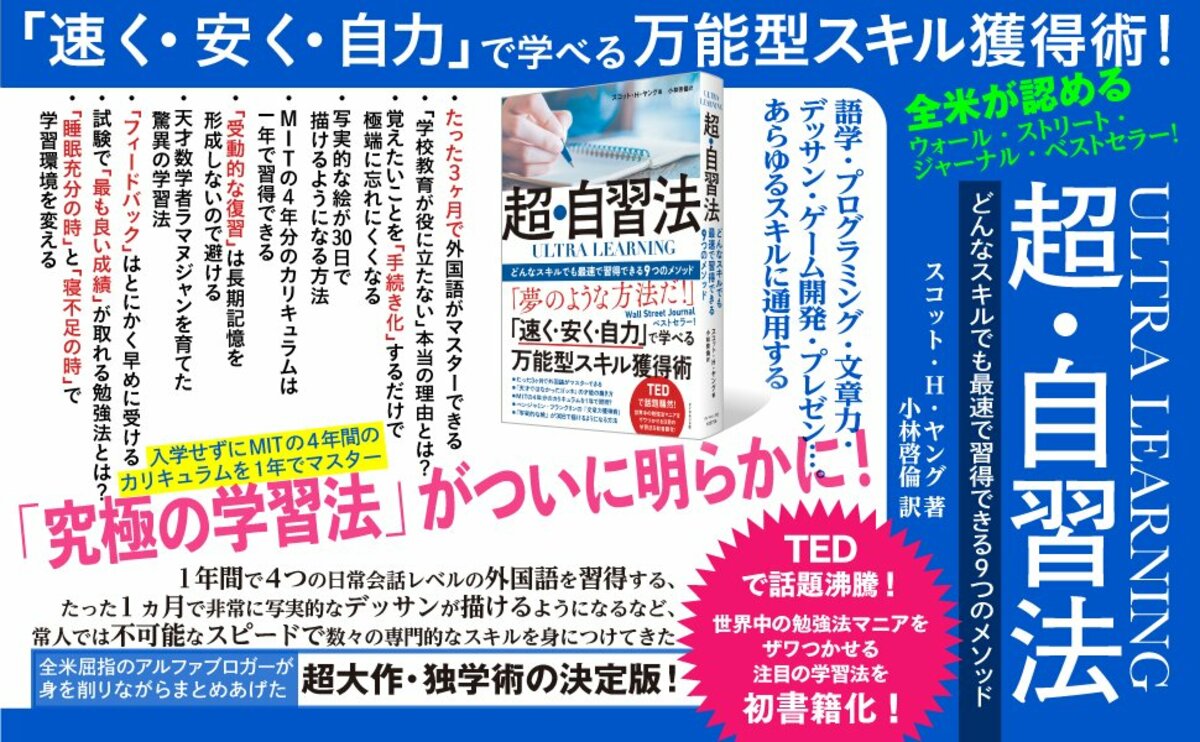勉強を始めるとすぐ気が散ってしまう…。そんな悩みを抱える人に、『ULTRA LEARNING 超・自習法』で紹介されているメソッドを紹介したい。「続けられない理由」を根本から理解し、改善する手がかりが得られるだろう。本連載では、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった本書の「学習メソッド」を紹介していく。(構成:ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
作業そのものが集中を奪う理由
机に座っても集中できない背景として、「作業自体」が原因である場合がある。
本書では、活動の種類によって集中のしやすさが異なると述べられており、ツールを選べるなら「どれが簡単に感じられるか」を判断材料にせよと促している。
場合によっては、自分の行動を微修正するだけでも、集中力を高めることができる。私は教材を読むのを難しく感じると、自分にとって難しい概念を改めて解説するメモを書くようにしている。(『ULTRA LEARNING 超・自習法』より)
著者と同じように、読むことが苦手な人は、「問題を解く・要点を説明する」など能動的な動きに切り替えることが集中維持に有効かもしれない。
自分の心がつくる集中の大敵
集中を妨げるもう1つの要因は「自分の心」である。
不安、怒り、落ち着かなさなどの感情は、学習の天敵だ。本書は、精神状態が整わなければ集中が成立しないと強調する。
悩みが頭を占めていると、勉強することが困難になるため、まずその問題に一定の処理を施す必要がある。
そして、感情が荒れているときほど、“ある行動”が重要になる。
そのようなときは、しばらくすれば感情の激しさは落ち着くものだということを覚えておこう。落ち着くまでに、作業をすべて放り出してしまうといった、強い反応を回避していれば良い。(『ULTRA LEARNING 超・自習法』より)
本書を読み進めると、感情が乱れても“完全に作業をやめないライン”を保つことが学習の継続力につながると理解できる。
気分に左右されず、作業とのつながりを少しでも残すことが重要だろう。
集中を取り戻すための実践ポイント
集中が切れたときに最も大切なのは、自分がどの要因でつまずいているのかを特定することだ。本書では、気が散る原因を「作業」「心」、それに加えて「環境」に分類し、順番に確認するよう推奨している。
本書の内容から考察すると、気が散っても「集中できる状態に戻る力」こそが現代に必要な集中力だと言えるかもしれない。
短い休憩を挟んでも、再び机に戻る習慣があれば、集中力は徐々に鍛えられていくだろう。
著者は集中力を「意志の強さ」ではなく「トレーニング可能なスキル」として扱うべきだと示唆している。
SNS通知や情報刺激が強い現代社会では、集中が途切れること自体は自然な現象である。
だからこそ著者のメソッドを活用し、集中力が“切れる前提・戻す前提”の学習設計を取り入れることが重要になるだろう。