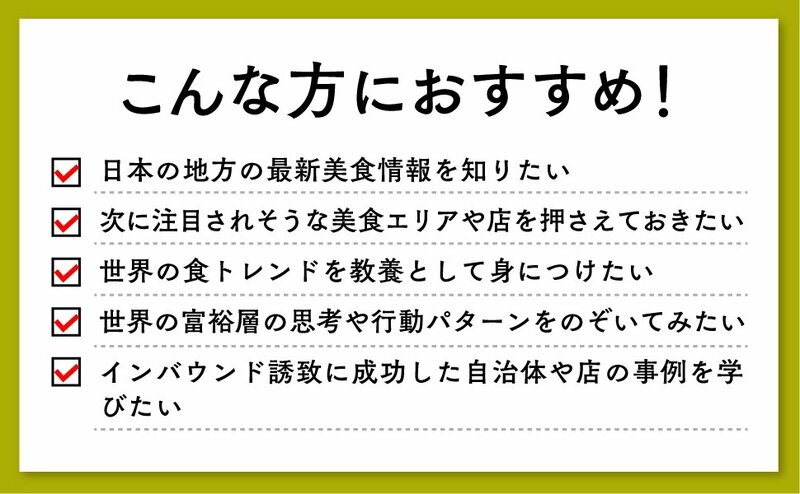世界の富裕層たちが日本を訪れる最大の目的になっている「美食」。彼らが次に向かうのは、大都市ではなく「地方」だ。いま、土地の文化と食材が融合した“ローカルガストロノミー”が、世界から熱視線を集めている。話題の書『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著)から、抜粋・再編集し、日本におけるガストロノミーツーリズム最前線を解説。いま注目されているお店やエリアを紹介していきます。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
全国から名店を集結させる「魚屋」の哲学とは?
「美味しい!」と評価され、表舞台で輝いているシェフの陰には、それを支える存在があります。これは、TBS『情熱大陸』やNHK『ガッテン!』でも取り上げられた、とある魚屋の話です。
静岡県焼津市に「サスエ前田魚店」という魚屋があります。駅から車で10分ほどのロードサイドにあり、大きな看板が掲げられた一見ふつうの魚屋です。ところが近年、この魚屋に、探究心のあるシェフたちが引き寄せられているのです。
たとえば、本書のP65でも触れたように、広島でフランス料理屋を営んでいた西健一さんは「サスエ前田魚店」の魚に出会い、わずか1日か2日の物流の差なのにこんなに旨さが違うことにショックを受けたことで地縁のまったくない焼津に移住してきました。そして、ここの魚を使うレストラン「馳走 西健一」を開いています。
なぜこの魚屋は、これほどの決断をシェフにさせるのでしょうか?
その理由は、「魚が極上である」ことに尽きます。
通常、魚屋というのは、魚を店先に並べて、それを買い手である私たちやシェフなどに「この魚はどうのこうので」というような話をするのが仕事です。
ところが「サスエ前田魚店」の五代目・前田尚毅さんは違います。駿河湾の魚の魅力や漁師さんたちの仕事を伝えるために、「魚のバトンリレー」を大切にしているのです。
スタートは漁師、ゴールは食卓
魚のバトンリレーというのは、漁師→魚屋→料理人→食べ手という、魚が人の手を経て届けられる流れをリレーとして捉えたもので、それぞれ卓越したプロフェッショナルがつながることによって、魚の味わいと思いに魂を込める取り組みのことです。
前田さんがこの発想のヒントを得たのは、2016年のリオ五輪男子400メートルリレーからでした。素晴らしいバトンパスによって日本が銀メダルを獲得した様子から、「バトンを魚に置き換え、チーム戦と考えたら、静岡の食はもっと強くなれる。でも、今はスターターがいない」と感じたそう。
そこで、さっそく彼はスターターを生むべく、漁師さんたちに掛け合いました。しかし、「魚を獲ったその場で仕立ててほしい」という前田さんの要望は、漁師さんたちの手間を増やすことに他なりません。そのため、最初はまったく聞く耳を持ってもらえなかったそうです。しかし、諦めずに直談判を続け、協力してくれる漁師さんの魚を2~3割高く買うようにしたところ、徐々に輪は広がっていきました。
最初こそ、「高く買ってくれるなら協力する」という姿勢だった漁師さんたちも、自分たちが手間暇加えることで魚のクオリティが上がっていくのを目の当たりにするにつれて、「食べる人をとにかく喜ばせたい」という心境に変わっていったそうです。
こうして、漁師さんたちの意識が変わり、両者の信頼が積み上がる中で、前田さんはさらなる試みを実行します。
「泳がせ」です。漁師さんたちに、獲った魚を水揚げせず、泳がせた状態で運んでもらうようにしたのです。
具体的には、漁船に搭載された「活魚水槽」などで、魚を泳がせながら持ち帰ってもらうのです。なぜなら、魚は死んでから時間がたつと、旨味成分が崩れたり、身が固くなったりするため、調理されるギリギリまで生きていることが望ましいからです(ただし、特別な水槽や手間がかかるため、すべての魚に用いられているわけではありません)。
泳がせで港にやってきた魚の多くは、前田さん自身が手当てをします。
魚の種類や状態に応じて最適な締め方をするのはもちろん、特に、県外に出す魚の場合は、脱水に気を配ります。移動している間に魚の水分量が変わってくるため、できるかぎり地元で食べるのと同じ状態になるように仕立てていくのです。
さらに、「あの店、あのシェフは…」というように、今では80軒ほどの国内外の取引先の好みに応じて、さばき方や仕立てを変えています。
そして、シャーベット状から魚の形をしたものまで12種類あるという氷を使い分け、浸透圧も考慮しながら詰め、料理人の元へバトンをつないでいくのです。
※本記事は、『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著・ダイヤモンド社刊)より、抜粋・編集したものです。