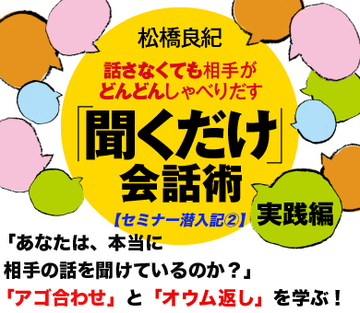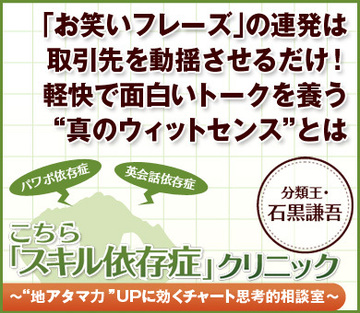ダジャレが粋か否かは
「かかり」が深いかどうか
連載残るはこれとあと一回。おなごのお尻…いや、お名残惜しいです。というところで今回は、文字をどうやって捉えると、認識すると、ダジャレ生成にとっていいのか、を探っていきます。
そしてそこの理解をよりクリアにするために、前提として説明しておきたいのが、連載開始当初からさらさらと何度か触れてきた「かかりの深さ」。まずここからおさらいしていきます。「かかり」については、連載21回<石黒式ダジャレ構造分類14種の解説前編> など参照に。
素材語と加工語。その2単語の文字を、ローマ字として考えて同じ部分を僕は「かかり」と呼んでいます。ローマ字でという意味はつまり<音として捉える>ということです。そして同じ部分が少なければ「かかりが浅い」、多ければ「かかりが深い」と表現します。そしてかかりは、深ければ深いほど、ダジャレとして粋ということ。ここでいつものように実例を。
<池脇シズル感>これはまあまあ、かかりが深くて好きです。<池脇千鶴>と<シズル感>がかかっている部分をローマ字で見てみると<hizuru>。この場合、前後にほどよく両単語のかかっていない部分があって、わかりやすさや面白みという点で、ここちよい作品です。
しかし、2単語の文字数が全然違っていたら、どちらかの語に完全に含まれてしまうケースも多々ある。円を使った集合図で、1つの円の中に、もう一方の大部分が内包されている状態と思っていただければ。
<予感シュトラウス>これは、<K>と<H>がかかってないだけであとは含まれていますね。かかりの深さ的には相当なもの。
さらにいきつくと<完全一致>という究極のかかりものがあります。
<印籠>これは、野球の内角低め<インロー>と発音はまったく同じ。 ここまで美しい形になると粋の極みではあるのですが、気付いてもらえないことも多いので用法を工夫しないと一般的な会話では使いにくい。
たとえばフリを入れる。野球の話の中にこれをかますなら、水戸黄門が印籠を差し出す真似にするとか、水戸黄門の話の中なら、バットを構えて足下のボールを見送る真似をするとか。ただ発しても気付かれませんから。