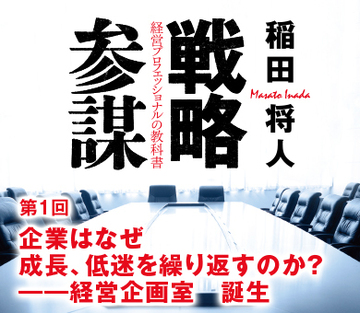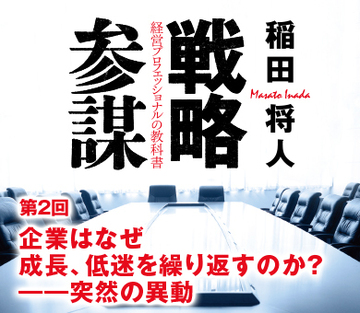**安部野の叱責
「ところで……、だ」
安部野は、珈琲カップを口元に運びながら、急に強い口調で言った。
「君は、ここまでの話をメモも取らずに聞いていたが、さぞかし超人的な記憶力の持ち主なんだろうな?」
「……」
声にならない声を発し、口をあけたまま高山の頭の中は、まっ白になった。
珈琲カップを持ったまま、高山の動きも表情も凍りついた。
「自分の知らないことを人に聞いている時は、メモを取るなんてことは、基本中の基本じゃないのか」
視線を薄暗い部屋の隅にそらし、安部野は体ごと横を向いて珈琲を飲んだ。
「す、すみません」
高山はあわてて珈琲カップを置いたため、ソーサーに珈琲が飛びちった。鞄の中を覗き込み、とっさに中にあった書類を出し、裏返してメモ代わりに使おうとした。
「ばかもの!」
安部野の声が応接スペースに響き、高山の体は、わずかにはね上がった。
「君はこれから、まがりなりにも頭を使う仕事をするんだろう。言ってみれば、情報を扱う役目なのに、その辺の書類の裏紙に、自分が得た情報を記録するような仕事の仕方をしていいと思っているのか」
高山の頭は、この場をなんとか取り繕いたいという思いと、どうしようもない緊張状態の下でパニックになっていた。
「君がこれからやる仕事は、『こんな感じがいいと思います』という程度の表現で進められるものではない。言葉にして、時には分析もし、何がポイントなのかを抽出して人に上手に伝え、全社視点での動きをつくっていかなければいけない仕事なのだ。知らないことを学びに来て、そこで得られた情報は、自分でその意味合いを咀嚼し、自分のものにしなければならない。そのためには、すくなくとも書いたメモはあとから整理ができるようにノートを使うのが、まず基本中の基本だろう」
「あの……。今日はノートを持ってきていません。すみませんでした」
高山は、つばを飲みこみながらなんとか答えたが、まるで格闘家に首を絞められたような声だった。
安部野は立ち上がり、壁際の棚からA4のノートを1冊取り出し、高山に手渡した。
「今日は、そのノートを使えばいい。この先の話は、君にとって重要なはずだ」
「ありがとうございます」と言って、高山がノートを開くと5ミリ方眼のノートだった。
安部野は高山に問いかけた。
「さて、ここまで話をしたが、様々な企画業務まで分業を進めた『成功した創業者』には、どんな業務が残されているのかな?」
高山は手にペンを持ち、A4のノートを開いたまま、静止してしまった。