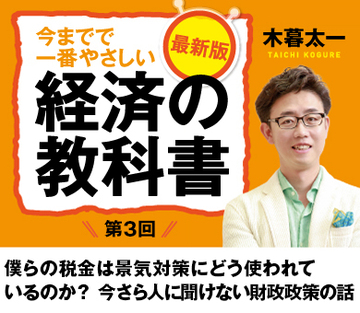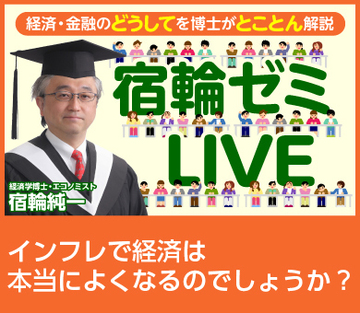「期待に訴える政策」って、どういうこと?
アベノミクスのもう1つの特徴が「期待に訴える政策」だということです。
「自民党に期待してください!」ってこと?
そうではありません。経済学でいう「期待」は、一般用語の「予想」の意味です。「期待に訴える」というのは、国民が「これから、こうなるだろうな」と予想するように仕向け、そう予想して動くようにし、結果的にそれを実現させようと考えている、ということです。
もともと、いろんな政策で「期待に訴える」ということがされています。たとえば、総理大臣が「来年、景気対策のために、減税をするかもしれない」とインタビューで口にしたとします。
そうすると、それを聞いた国民は「まじ!? じゃあ、来年は少し楽になりそうだから、貯金を切り崩していいかも♪」といって、買い物を始めます。まだ減税されていないのに、減税されたことを見越して動いてしまうわけです。
景気対策を実行する前に、景気が良くなっちゃうかもしれません。そしてもしかしたら、言うだけで減税はしないかもしれません。みんなの「期待(予想)」をうまく利用すると、現実を変えやすいんです。
今回のアベノミクスでは「物価の上昇率を2%にするのが目標!(インフレ2%)」としています。じつは2%物価を上げることは簡単ではなく、かなり本気にならなければ達成できない目標なんです。「2%」という数字には、政府が「本気」で取り組むことが表れているんですね。
そして、国民も「政府が本気で取り組むんだったら、本当にそうなりそうだ」と思うようになります。それが狙いでした。
アベノミクスの大まかな内容は、これまで行ってきた政策と同じです。ただ、「インフレ目標2%」と、明確な数字を出し、覚悟を見せたこと、そしてそれを基に国民の期待を変えたことが違いました。
金融緩和政策の波及効果は?
じゃあ、アベノミクスで金融緩和をしたときは、うまくいったの?
率直に言うと、「多少はうまくいった。でも想定通りにはならなかった」というのが、ぼくの印象です。つまり、期待していたくらいの効果はなかったということです。なぜ「想定通り」にはならなかったのでしょうか? それを説明していきましょう。
金融政策は「世の中の企業や個人が、お金を借りやすくする政策(お金を借りやすくしてお金を使いやすくする政策)」です。そしてもともと、「お金を借りたい人はたくさんいるだろう」という前提で行われています。
だから金利が下がれば、企業はたくさんお金を借りる!と考えられていました。でも、そうではなかった。
なんで?
たしかに、お金を借りたい人にとっては、金利は低い方がいいです。金利が高いと「資金を借りて商品を仕入れたりしたいけど、諦めるか……」となります。そんなときに、「金利が下がりました!」と言われたら、「じゃあうちも借りたい!」と手を挙げる人が増えます。
うん、そうだよね。今回は違ったの?
今回は違いました。問題は、そもそもお金を借りたいと思っている人が、それほどいなかったということです。お金を借りたいと思っていなければ、金利が低くなっても借りません。「歴史的な超低金利ですよ!」と言われたとしても、「いやいや、いりません」と断るだけです。
みなさんがご自身のケースで考えても同じように感じると思います。また、普通の買い物も一緒です。いらないものは、いくら安くても、いりません。ということは、金利を下げても、企業が融資を受けたい!と思っていなければ、借りないということなんです。
「金融緩和をすると、景気が良くなる」という理屈には、「金利が下がれば、もっと企業・個人がお金を借りる」という前提が組み込まれています。この前提が崩れたら、結果が変わってしまいます。「金融緩和をしても、景気は良くなるとは限らない」となるのです。お金を借りたいと思う人が少なければ、金融緩和政策の波及効果が小さくなってしまうんですね。