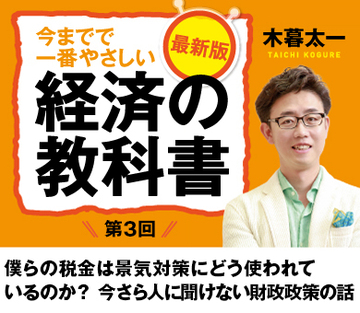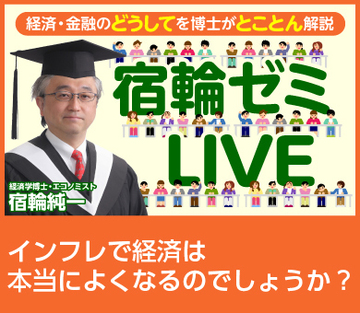「インフレ2%」は何が狙い?
アベノミクスの特徴の一つに「インフレ2%を目標」というものがあります。これは正しく言うと、インフレーション率2%を目標ということで、要するに「毎年物価を2%ずつ上げること」を目標に掲げているんです。
物価を上げることが目標なの!? 商品の値段が高くなっちゃうじゃん! なんでそんなことするの??
それは、インフレが起きると、みんながお金を使うからです。 どういうことか、説明しましょう。インフレとは、継続的に物価が上がることです。
たとえば「インフレ率1%」だったら、「世の中の商品が全体的に毎年、1%値上がりしている状態」です。このインフレが起きると、同じ商品でも去年より今年、今年よりも来年の値段が高いということですよね。
うん、そうだね。で?
今年よりも来年の方が高くなっちゃうんだったら、今年買った方が「得」ですよね。だとしたらみんな「だったら、今年買おう!」と言って、お金を使うようになります。その結果、商品が売れて、景気が良くなるんです。
また、インフレになれば、借金の返済が楽になります。物価が上がれば、商品を1個売ったときにもらえるお金が(物価が上がった分)増えるわけですね。
自社の商品がこれまで1個100円だったのに、インフレが起きた結果110円に上がったとします(10%値上がり)。世の中全体的に値上がりしているので、ライバル商品と比べて割高になったわけではありません。消費者からすると「結局、前と同じ」という状態なので、前と同じ数が売れます。となると、売上も10%増え、収入は10%増えます。
うん、だから何?
ポイントは借金の金額です。収入は10%増えても、借金の金額は増えません。となれば、借金が返しやすくなりますね。極端な話、物価が2倍になり、収入が2倍になったら、実質的に借金が半分になるのと同じなんです。要は、インフレの分だけお金を稼ぎやすくなるということ、そして、それだけ借金を返済しやすくなるわけですね。
それで?
ということは、企業も借金しやすくなる、つまり(借金をして)ビジネスをすることが簡単になるということになります。
ビジネスをすることが簡単になれば、経済が活気づいて、景気が良くなりますね。だから大ざっぱに考えると「インフレは景気にプラス」なんです。
なるほどね、じゃあデフレは反対にマイナスなの?
その通り。反対に、デフレ(物価が下がり続ける状態)だと、消費者もなかなかお金を使おうとしません。物価が下がる→給料も下がる→これから収入が少なくなる→「今使うのをやめよう」となるからですね。
企業にとっても、物価が下がる→自社の商品の値段が下がる→お金を稼ぎづらくなる→「借金をしたら返済が大変!」→「銀行からお金を借りるのをやめよう」、となります。その結果、ビジネスが盛り上がらなくなるわけですね。だから、アベノミクスでは「2%のインフレ」を目標に掲げていたのです。
でも、なんで2%なの? たまたま?
鋭いですね。それが次の「期待に訴えた」という部分に関係してきます。