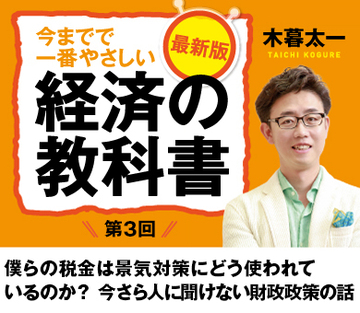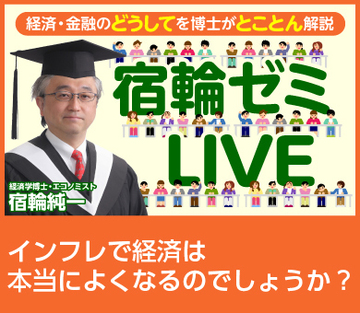景気は良くなるという「消費者の気持ち」が大切
それじゃあ、アベノミクスの“2本目の矢”財政出動の効果は出たの?
結論から言うと、こちらも「期待していたよりは効果が小さかった」と思います。繰り返しになりますが、財政出動は、政府がお金を使うことなので、必ず何らかの効果は出ます。でも、それだけではダメなんです。
「1兆円の財政出動をして、1兆円分の効果があった」では合格点をあげられません。最初の「1兆円」は、単なる呼び水なので、その後に広がっていかなければいけません。ただし、その後広がるかどうかは、政府がコントロールできません。
え、そうなの?
財政出動をするということは、国がお金を使うということです。そして国がお金を使うと、
(1)そのお金は、誰かの給料になっている。そしてその結果、
↓
(2)国民がもっと多く買い物をする。そしてその結果、
↓
(3)世の中のお店がもっと儲かる。そしてその結果、
↓
(4)国民の給料がもっと増える
という流れで政策の成果が出てきます。このように、効果が波及していくことを、「乗数効果」といいます(詳しくは第3回参照)。
ただ、国民の給料が増えても、(2)で「買い物をたくさんする」とは限りません。各自の判断です。みなさんも給料が増えたからといって、すぐに「もっと買い物しよう!」となるとは限りませんよね。
うーん、たしかに。将来が不安だから貯金するかも。
そうです。個人個人で考えたら貯金も大切です。でも、せっかく給料が増えても、みんなが貯金してしまったら、波及しなくなっちゃうわけです。この財政出動がどれくらいの効果をもたらすかは、じつは、ぼくら国民がどれだけお金を使いやすくなっているかによるんです。
じゃあ、財政出動がうまくいくかどうかって、消費者の気分次第ってことなの?
最終的には「消費者の気持ち(消費マインド)」がとても重要な要素になります。社会の雰囲気が暗くなり、個人がお金を使わないときはいくらバラマキ政策をやっても効果が限られます。そういう意味で「気分」はとても重要で、みんなに「これから景気は良くなりそう」と思わせること自体がすごく大切です。