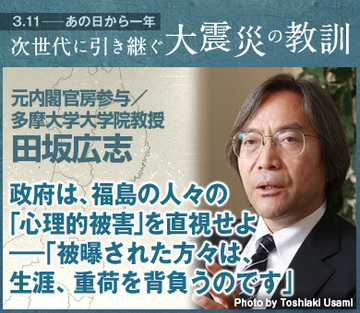【前回までのあらすじ】
首都移転チームが正式に発足。各省庁から20数人の優秀な若手官僚らが選抜された。初顔合わせの日、チームリーダーの村津は1年でスキームをまとめるとメンバーに発表する。
森嶋が帰宅すると携帯電話が鳴った。東京経済新聞記者の理沙からだった。近くのコーヒーショップに呼び出された森嶋は、理沙から首都移転プロジェクトの事実関係について質問されるが答えない。
理沙と別れたあと、ふたたび森嶋の携帯が鳴った。理沙はアメリカのヘッジファンドが日本で動き出したと告げる。
チーム発足2日目の夜、森嶋は村津に連れられ、渋谷の居酒屋に入った。村津は首都移転を提案した森嶋の真意を問いただす。村津は、これまでの経緯や現在の首都移転ついての自分の考えを森嶋に吐露する。日本の将来のためにも「遷都を実現するべき」という村津の考えを聞いた森嶋は、村津に対して持っていた負け犬というイメージが変わっていくのを感じた。
首都移転チームが正式に発足。各省庁から20数人の優秀な若手官僚らが選抜された。初顔合わせの日、チームリーダーの村津は1年でスキームをまとめるとメンバーに発表する。
森嶋が帰宅すると携帯電話が鳴った。東京経済新聞記者の理沙からだった。近くのコーヒーショップに呼び出された森嶋は、理沙から首都移転プロジェクトの事実関係について質問されるが答えない。
理沙と別れたあと、ふたたび森嶋の携帯が鳴った。理沙はアメリカのヘッジファンドが日本で動き出したと告げる。
チーム発足2日目の夜、森嶋は村津に連れられ、渋谷の居酒屋に入った。村津は首都移転を提案した森嶋の真意を問いただす。村津は、これまでの経緯や現在の首都移転ついての自分の考えを森嶋に吐露する。日本の将来のためにも「遷都を実現するべき」という村津の考えを聞いた森嶋は、村津に対して持っていた負け犬というイメージが変わっていくのを感じた。
第1章
12
首都移転チームはスタートしたが、具体的な仕事はほとんどなかった。
部屋に集まると、遠山が資料を運んで来て全員のデスクに配った。
森嶋たちはただその資料を読んでいった。資料の大半は前回の首都機能移転準備室でまとめられたものだった。日本全国の地勢調査、交通網、歴史、住民の意識調査まであった。
村津の姿は最初の数日しか見ていない。
国交省からの帰り、森嶋は議員会館で植田に会った。
植田に一度会って話しませんかと言われたことと、今回の首都移転について政治家の、それも若手政治家の本音が知りたかったのだ。首都移転などという現実味に欠ける構想に本気で関わろうとする政治家はいるのか。
政治家の大部分は、ハドソン国務長官が総理に直接つきつけた要求を知らないはずだ。いや、それとも知っているのか。
「あなたはなぜこのチームのオブザーバーを申し出たのです」
森嶋はこの同世代の政治家に切り出した。
突然の森嶋の言葉に植田は戸惑った表情を見せている。
「政治家は基本的に票にならないことには消極的です。首都移転は票になりますか」
やはり答えない植田に対して森嶋が言った。
「しかし移転候補地の政治家にとっては、目の色が変わるでしょう。あなたは北海道選出だ。移転候補地には無縁だ。だから冷静に考えることができる。それとも、北海道も名乗りを上げるつもりですか」
「キャリア官僚とは思えない厳しい言葉だ。道理で、こんな解答を持ってくるはずだ」
「厳しい言葉とは思っていません。むしろ、当然な考えだと思っています」