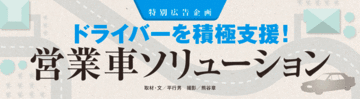広告企画
生産拠点やマーケットを海外に求める企業が増えるのに比例して、ビジネスパーソンの語学習得への熱意も高まっている。しかし、ビジネスの現場で〝使える英語力〟を身に付けられているかというと、そこには大きなハードルがある。キャリアメークにも大きな影響を及ぼす〝使える英語力〟とは?
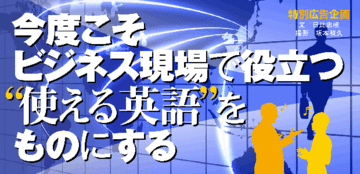
技術大国日本の維持のみならず、社会をリードする役割への期待もあって、理工系人材へのニーズは増している。その一方で、受験科目数が多く、必要な履修範囲も広いため、理工系大学への進学をためらう受験生も少なくないという。理工系大学で学ぶメリットと大学の最新動向等について、「理系ナビ」の渡辺道也編集長に聞いた。
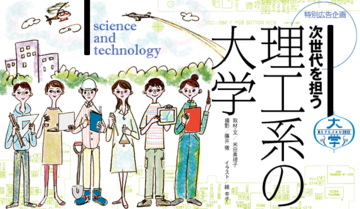
爽やかな風が吹き抜ける仙台市郊外に、画期的なスマートタウンが誕生した。積水ハウスが展開する「スマートコモンシティ明石台」は、同社が掲げるキーワード「SLOW&SMART」を具体化し、環境に配慮した“サステナブルなまちづくり”を実現している。

エネルギーを大切に使いながら快適な暮らしを実現する。そんな社会づくりが求められる昨今、スマートハウスのリーディンカンパニーである積水ハウスは、「SLOW&SMART」というキーワードを掲げ、快適でありながら環境に配慮した先進の住まいづくりを追求している。

グルンドフォスが実施する「ポンプ省エネ診断」を受け導入に至った企業のひとつが、横浜ゴムの新城工場である。では、同社のポンプ導入前後では、電力消費量にはどれだけの違いが生じたのか? 実際に導入した新城工場を訪問し、現場の声を聞いた。
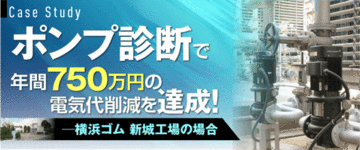
電気料金の値上げや、電力需給の逼迫など、「節電」に対するプライオリティはますます高まっている。しかし節電で効果が高いのに、じつは盲点となっているのが「ポンプ」の存在だ。製造工場の現場はもちろん、事務中心のオフィスビルといった身近な場所でもポンプの恩恵にあずかっている。その効果と対策を見てみよう。

ビジネスで通用する英会話のスキルは、どのレベルまで磨き上げれば盤石なのか? かねてからその有力なモノサシと位置づけられてきたのが、TOEICなどの語学力検定である。だが、英語によるビジネス・コミュニケーション研究の第一人者である明星大学の田中宏昌教授は、冒頭からこんなショッキングな指摘をする。
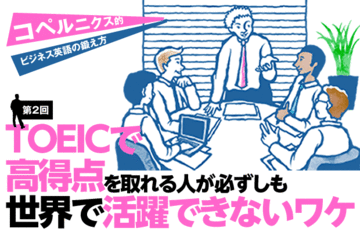
夏休みを間近に控え、旅行シーズンに突入した。震災による落ち込みから回復、円高でお得感のある海外のみならず、避暑地をはじめ国内旅行も人気を呼んでいる。夏から秋の旅の動向を探ってみた。
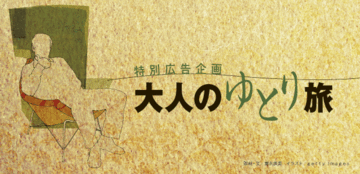
自然現象としての「地震」と、社会現象としての「震災」は別のものであると主張するのは、地震学者である島村英紀教授である。地震を防ぐことはできないが、震災の被害を小さくすることはできる。地震国である日本を生きるための知識と備えの方法を聞いた。
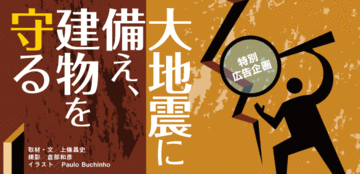
今ではあらゆる業種・職種の人が、英語を使って仕事をすることを求められる。しかも昔と今ではビジネス英語に求められるスキルが異なってきているという。明星大学の田中宏昌教授に話を聞いた。
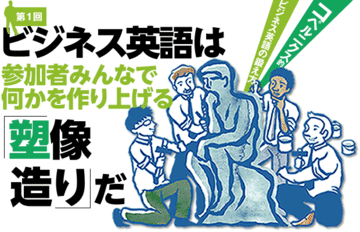
日本のエネルギー政策が新たな一歩を踏み出す中、太陽光発電システムへの関心が高まっている。「災害への備え、エネルギーの自給自足、エコ」といったキーワードに加え、「売電によるビジネス」という着眼点も見逃せなくなった。太陽光発電システムに関する調査、提言などを行ってきた専門家に、今後の展望と課題を聞いた。
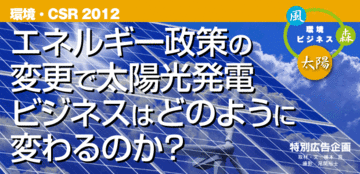
一般的に、中堅・中小企業では、経理や会計事務に精通した人材は限られている。かといって、高いリテラシーを持った人材を新たに雇用する費用対効果にも疑問が残る。そんなジレンマを抱えている企業にとって力になるのはアウトソーシングサービスの導入だ。
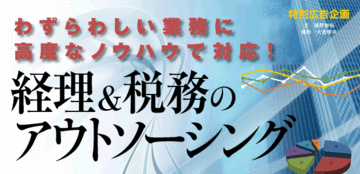
近年竣工のオフィスビルは、さまざま機能を高水準で備え、高機能化している。しかもそれは単なるインフラストラクチャーだけではなく、“快適に働ける環境”というソフト面も充実したものである。

若年人口の減少に伴って大学の競争が激化、生き残りを懸けて新たな特色を打ち出す大学が増えている。建学の理念や研究・教育姿勢の伝統を大切にしながら、時代のニーズに応えていく。そんな取り組みにまい進し、新たなブランド力を獲得している大学に注目したい。
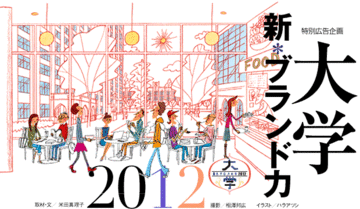
円高からの脱却や新市場開拓のために海外を目指す中堅・中小企業が増えている。現地の法制度や商習慣の違いに戸惑い、思い描いていたビジネスを実現できないケースもある。頼れる専門家や支援サービスを徹底活用することが、海外ビジネスを成功させるための突破口となりそうだ。

住宅ローンの返済や子どもの教育費、場合によっては親の介護費用など、出ていくお金はやたらと増える半面、長く日本人の所得は頭打ち傾向が続いている。この状態はいつまで続くのか。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会副理事長の白根壽晴氏に聞いた。
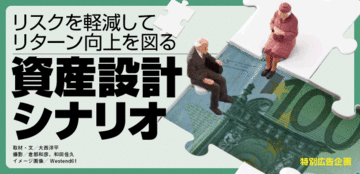
ビジネストラベルの移動時間をいかに活用するか。東大在学中にNPOの立ち上げや起業をし、学生と企業人という二足のわらじを履きながら、最大効率を求め続けたオトバンク代表・上田渉氏に、出張時の効果的な仕事術について聞いた。

福利厚生は比較的低コストで、様々な経営的効果を実現するポテンシャルを有する。採用力を高め、従業員満足度を向上させ、企業の生産性向上等に寄与する「戦略的福利厚生」の構築のポイントを探った。
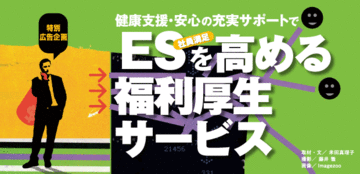
首都圏に住むビジネスパーソンの通勤平均時間は、往復で約2時間。貴重な時間を無為に過ごす手はない! 就職、昇進、転勤など新生活スタートを機に、通勤時間を自分磨きのゴールデンタイムに変え、さらなる飛躍を目指そう。
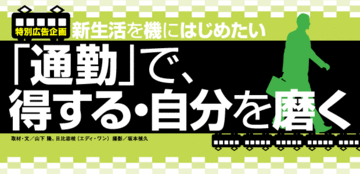
従業員の安全確保やコスト削減だけでなく、企業倫理の側面からも、社有車を安全運転することの重要性はますます高まっている。ドライバーに安全運転を実践させるには、どうすればいいのか。心理的な背景を踏まえた具体的方策について専門家に話を聞いた。