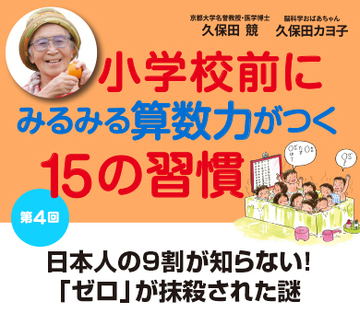記事検索
「数学」の検索結果:2241-2260/2844件
第1回
数字どおりなら「幸せな結婚も可能?」データサイエンティストの悲しき性癖
日々、膨大な量のビッグデータと向き合い続けるデータサイエンティストたち。インターネットの時代に誰も見ていないネットの行動からは、秘めた願望、恋愛、性的志向、偏見がダダ漏れだ。ニュース配信サービス「スマートニュース」のデータサイエンティストたちが語る。
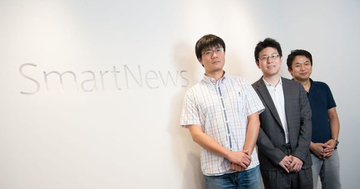
第15回
子どもに聞かれたら、答えられますか? 数は「0」から始まるの? それとも「1」から始まるの?
2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き‼︎最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!小学校前に算数力がアップする秘訣を一挙公開!
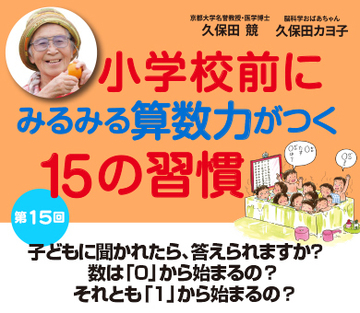
第29回
中小企業や自営業などの経営者らの世界にも、「学歴病」は浸透しているのだろうか。また、大企業に勤務する会社員はなぜ学歴に強い影響を受けているのか。多くの仕事を経験して独立した学歴に詳しいコンサルタントに、学歴と企業規模の関係を聞いてみた。

第14回
お母さん、お父さんが大の数学ギライのとき、子どもに、どう教えたらいい?
2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き‼︎最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!小学校前に算数力がアップする秘訣を一挙公開!
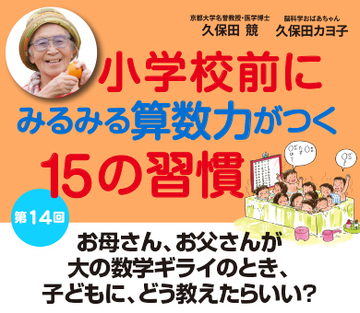
第13回
ノーベル賞受賞者と算数、数学の非常識な関係
2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き‼︎最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!小学校前に算数力がアップする秘訣を一挙公開!
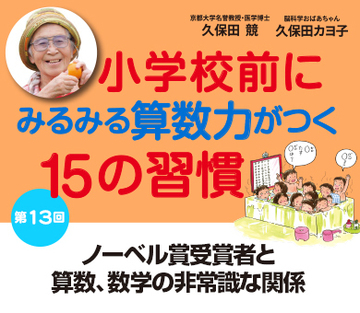
第100回
「超一流」の人を目にすると、私たちは「あの人は生まれつき才能に恵まれていたんだ」と思い込んでしまいがちだ。しかし、超一流の人たちが超一流になりえたのは、本当に生まれつきの才能が要因なのだろうか。
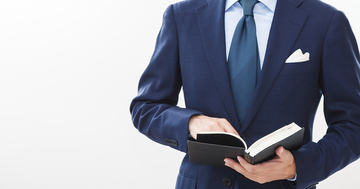
最終回
「辺境の人」「保守本流は好きではない」と言いながらも、ボストンコンサルティンググループを確固たる企業のパートナー役に育て上げた御立尚資氏。今、その視点はどこに向かっているのか。「1000年単位の歴史観を持って事業を行う時代」と語る真意などを聞いた。

第7回
アジアで最下位!なぜ日本は「英語が話せない」国なのか?
これからの進学先は、本当に「東大や京大」「早慶」を目指すだけでいいのか?そもそも親の常識や思考を変えていかなければいけないのではないか、というテーマで、教育界の異端児2人が顔合わせ!最終回はTOEFL試験で明らかになった日本人の「英語が話せない」事実。アジア最下位になってしまった現在、これからの子どもたちの英語教育をどうすればいいのか、を話ていただきました。

第6回
中学受験300万円、留学半年で200万円…。これだけかけて最終学歴がGMARCHでいいのか?
これからの進学先は、本当に「東大や京大」「早慶」を目指すだけでいいのか?そもそも親の常識や思考を変えていかなければいけないのではないか、というテーマで、教育界の異端児2人が顔合わせ!今回は「アメリカ留学の方がコスパがいい」という新しい視点での対談です。

第11回
脳科学おばあちゃん教えて!0~1歳児に算数をどう教えたらいい?
2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き‼︎最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!小学校前に算数力がアップする秘訣を一挙公開!
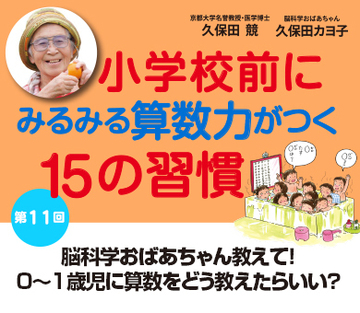
第10回
江戸の知られざる算術のミリオンセラーを「脳科学の権威」が初解剖する!
2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き‼︎最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!小学校前に算数力がアップする秘訣を一挙公開!
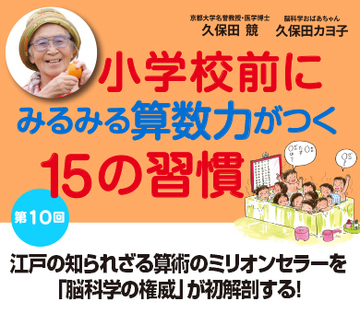
2020年、大学入試が大きく変わる。共通1次試験から大学入試センター試験に代わって以来、30年ぶりの大改革だ。それに合わせて、中学・高校の学びの形も大きく変わろうとしている。

第9回
IQは関係ない!暗算「回数」だけが明暗を分ける
発売たちまちアマゾン1位(「子育て」&「算数」)!2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き‼︎最新脳科学に基づく世界初のメソッド!小学校前に算数力がアップする秘訣を公開!
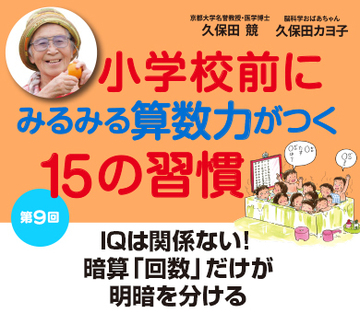
2016年度大学入試で最も話題となったのが、東京大学と京都大学がそれぞれ初めて実施した「推薦入試」「特色入試」だった。その結果を振り返りながら、国立大学入試改革のゆくえを展望する。

第8回
国語、算数、社会、どれを勉強したら、将来、成功する?
2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き‼︎最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!小学校前に算数力がアップする秘訣を一挙公開!
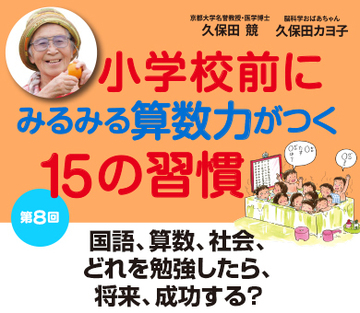
第7回
男の子の算数脳、女の子の算数脳、どうちがう?
2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き‼︎最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!小学校前に算数力がアップする秘訣を一挙公開!

第6回
子どもの「海馬」が急激に「大人の」海馬になる瞬間
2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き‼︎最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!小学校前に算数力がアップする秘訣を一挙公開!
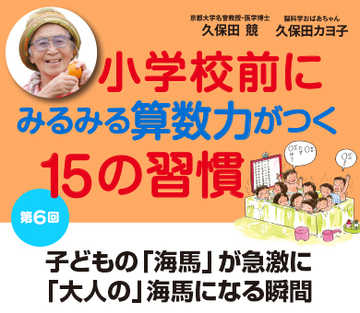
第119回
日本IBMが都内で開催した「IBM ウーマンズ・リーダーシップ・フォーラム」は、日本国内で活躍する女性のビジネスリーダーなど約200人が来場。講演やパネルディスカッションを通じて、日本の女性リーダーのさらなる活躍に向けた提言や意見交換を行った。

第5回
算数に強くないと、子どもがすごく困る脳科学的な理由
2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き‼︎最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!小学校前に算数力がアップする秘訣を一挙公開!
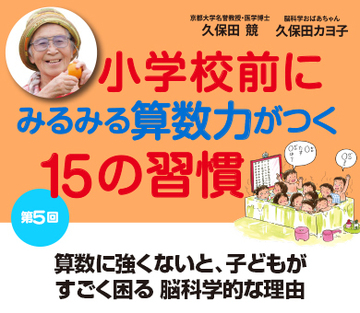
第4回
日本人の9割が知らない!「ゼロ」が抹殺された謎
2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き‼︎最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!小学校前に算数力がアップする秘訣を一挙公開!