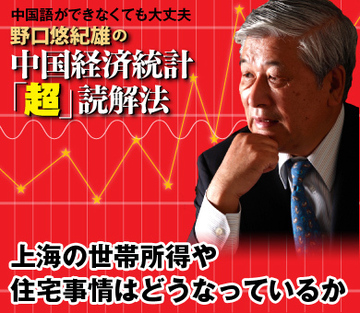野口悠紀雄
第8回
株価や為替レートの乱高下が続いている。日本の金融市場は著しく不安定化した。その理由は、昨年秋以来の為替レートと株価が投機によって動かされたからだ。価格の乱高下は、安倍晋三内閣の経済政策が必然的に引き起こしたものだ。
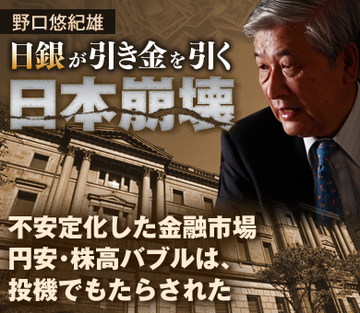
第7回
アベノミクスは、「将来に対する人々の期待が好転すると、実体経済活動もそれに引かれて好転する」という効果を狙っているとされる。それは本当か。財務省の法人企業統計を用いて、期待による経済活性化効果が生じているのかを検証した。
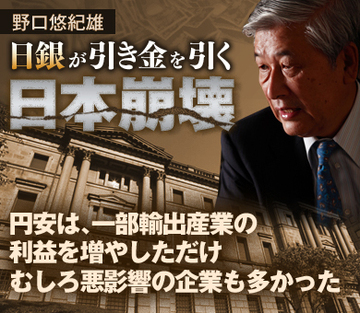
第6回
株価が大きく変動している。今回は、本連載の第4回「円安は企業利益をどう変化させるか――シミュレーションモデルによる分析」に示したモデルを用いて、現実の株価の評価を試みることとしよう。
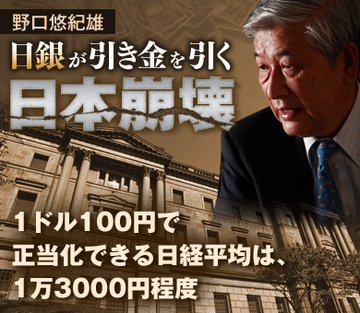
第5回
1-3月期実質GDP(国内総生産)は、対前期比年率で3.5%の増加となった。これをアベノミクスの効果と見る向きが多いだろう。しかし、詳細に見ると、そうとは言えない面が多いのである。
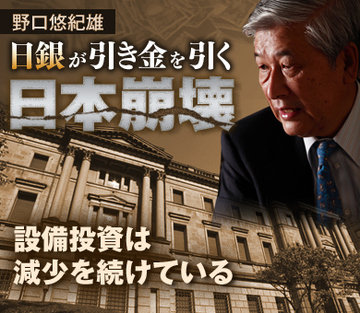
第4回
上場企業の決算発表が続いている。これに対して、「円安によって企業が大幅増益」というトーンの報道が多い。株価上昇を支えているのも、そうした見方であろう。企業の利益増加は、本当に円安だけによって生じているのだろうか?そして、今後はどうなるのだろうか?
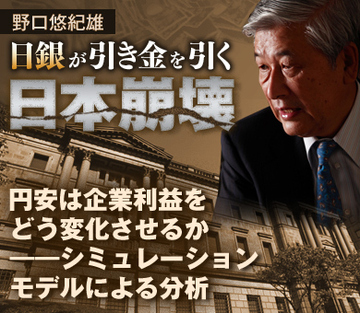
第3回
安倍内閣の経済政策が本当に内容のあるものか、それとも見かけ倒しのこけおどしのものかという判断は、成長戦略によってなされることになる。今回は、「成長戦略で何が必要か?どのように評価するか?」という問題を考えよう。
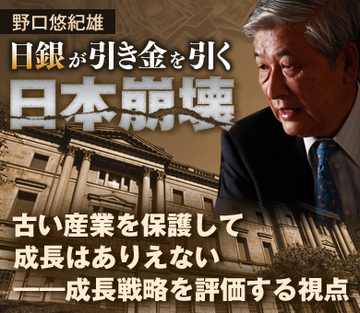
第2回
日本銀行の「次元の異なる量的・質的金融緩和政策」に対して株式市場や為替市場では、緩和策を効能書きどおりに受け取って、株高と円安が進んだ。しかし、プロの市場である国債市場では、国債利回りの乱高下が生じた。
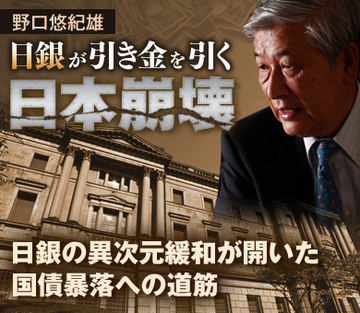
第1回
日本銀行が新しい金融政策を決定した。これを受けて、「日本経済は長く続いた停滞から脱却しようとしている」と考えている人が多い。この期待は、実現されるだろうか?
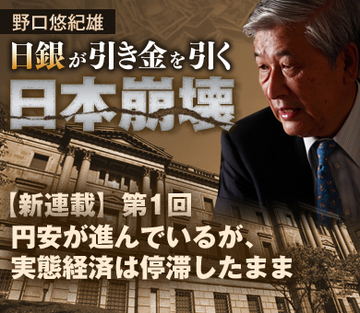
第21回
これまで見てきたように、中国の場合、GDP(国内総生産)など政府によって作成・公表されるマクロ統計は、あまり詳しくない。これに対して、上場企業の場合には、財務データを中心として、世界的な基準にしたがってのデータが公開されている。
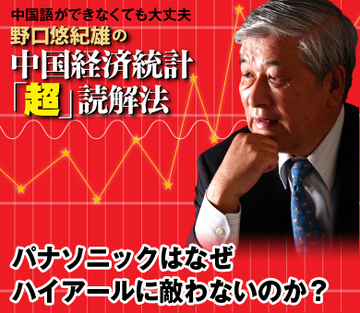
第20回
この連載でわれわれが進めてきた中国語の学習方法は、基本的にインターネットに依存するものであった。10年前であれば、こうした方法での学習は進められなかったろう。以下で見るように、インターネットの世界には、新しい中国が出現している。
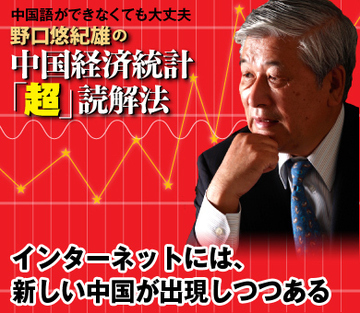
第19回
これまでは、中国語を「読む」ことに集中してきた。日本にいて中国に関する情報を収集するということに限定すれば、これで目的の9割は達成することができる。ただし、それだけではもちろん十分ではない。今回は「中国語を聞くこと」について述べる。
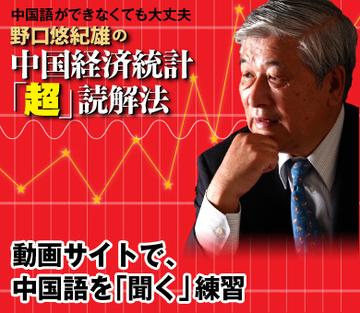
第18回
安倍首相は、TPPの交渉に参加することを正式に表明した。このニュースは、中国にかなりのショックを与えたようである。今回は、日本のTPP交渉参加に対する中国の反応を、中国のメディアを通じて見ることとしよう。
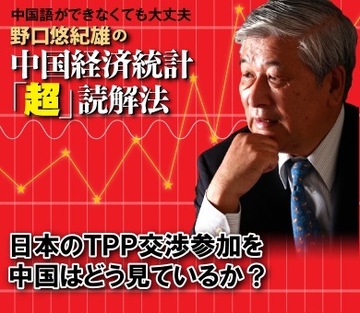
第17回
これまで、簡単な方法で中国語の文献を読むことを探ってきた。これをさらに推し進めることとしたい。中国語の文献を読むいくつかのテクニックを使って、「中国不動産バブル」について、中国語で解説を読んでみよう。
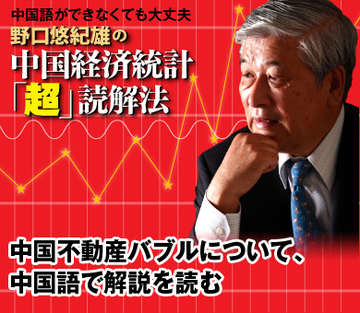
第16回
前回に引き続き、簡単な操作で中国の経済関係の文献を調べる方法を探ることとしよう。我々の目的は、文法的に正確な処理よりも、辞書で調べるべきキーワードをあぶりだすこと。中国の検索エンジンを使って、中国の文献を読んでみよう。
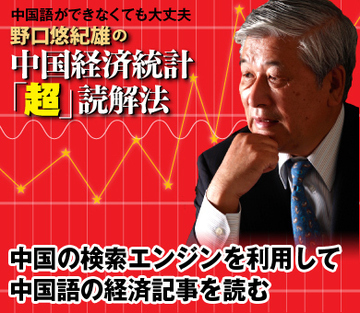
第15回
以下に述べるのは、「10秒間勉強するだけで、中国語が読めるようになる」という方法である。「そんなのはマユツバだ」と感じられる読者が多いと思う。しかし、そうではないのである。これは、日本語と中国語の関係が特殊であることを利用した合理的な方法なのだ。
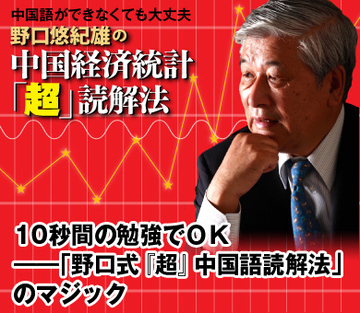
第14回
今回は、中国語の文章を読むことにチャレンジしてみよう。当面の目的は、新聞記事や統計の解説を読むことだ。「何の予備知識もなしに中国の新聞を読む」というと、無謀と思われるかもしれないが、実はそんなことはない。
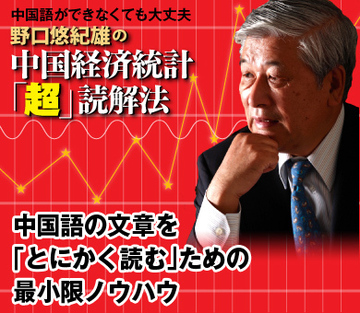
第13回
前回述べたのは会話などのバーバル(口頭の)・コミュニケーションだが、今回は簡字体の読み方について述べる。統計や文書を「読む」という観点からすれば、このほうが重要とも言える。法則を知っていれば、かなりの簡字体を、格別の努力をせずに読むことができる.。
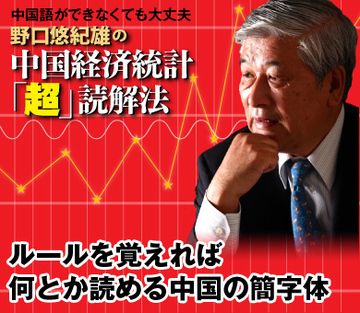
第12回
今回は、本筋の作業からは少し離れて、中国語そのものの学習について述べることとしよう。さまざまの学習用音源や無料の語学講座などが、インターネット上に提供されるようになってきた。中には非常に優れたものもある。これらをどう使いこなすべきか。
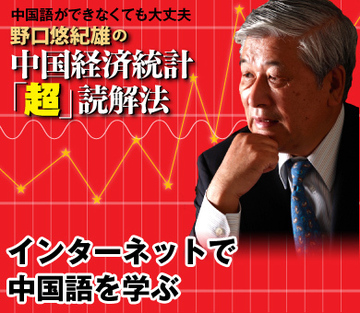
第11回
財政というテーマは、馴染みにくいものだ。しかし、中国を考える場合には、大変重要な意味を持っている。社会主義時代からの流れで公的企業が多く、いまでも共産党一党独裁が続いているので、公的部門の動きが経済全体の動向に重要な影響を与えているからである。
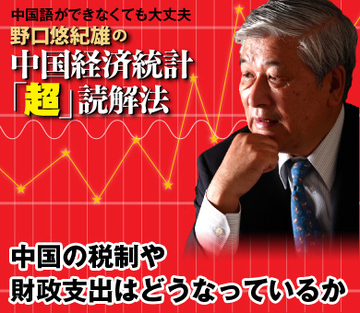
第10回
中国の住宅事情は、つぎの2つの要因によって、きわめて特殊なものになっている。第1は、社会主義経済時代には、住宅の私有が認められていなかったことだ。第2は、急速な経済成長による購買力の上昇と、農村人口の都市への流入によって膨大な需要増が生じたことだ。