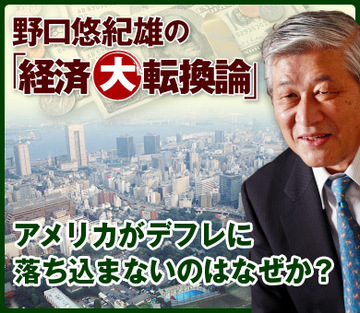野口悠紀雄
第35回
FRBが、金融緩和措置の第3弾であるQE3に踏み切った。注目されるのは、「労働市場の先行きに十分な改善が見られるまで、適切な手段を取る」とされたことだ。しかし、この目標は達成できないだろうと考えられている。

第34回
ヨーロッパ中央銀行が南欧国債の無制限買い入れを決定した。これは、ESMの基金を積み立てて国債を購入する方法から、通貨を増発して購入する方法への転換だ。これにより、ユーロは弱くなる。この観点から今回の決定の意味を考えることとしよう。

第33回
イギリスの対外資産・負債のパタンは、日本やアメリカとかなり異なる。イギリスの国際金融は、国内金融とはほぼ切り離された存在だ。外国から資金を調達し、それを外国で運用しているのだ。対外負債が資産とほぼ同じだけあることが、それを物語っている。

第32回
ギリシャ国債(10年債)の利回りは、2012年の初めに35%という異常な水準に達した。しかし、急騰したのは比較的最近のことである。スペインやイタリアの国債の利回りも同じような動きを見せた。なぜ最近になってこうした変化が生じたのだろうか?

第31回
アメリカを中心とした国際的資本移動を見ることにより、金融政策や金融情勢と資本移動の関係を見ることができる。アメリカと全世界の関係を一括して見るより、相手国との関係を見ることによって、そうした姿が浮かびあがる。

第30回
前回、短期証券投資の形で、イギリスから日本へ巨額の資金流入が2011年にあったことを述べた。これは、世界的な資金の流れが「リスクオフ」の方向を向いていることの反映である。以下においては、「リスクオフ」の流れがいつまで続くのかを考えることとしよう。
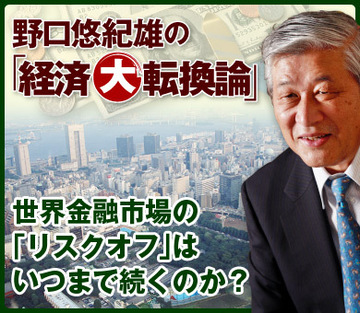
第29回
6月末の欧州連合(EU)首脳会議で、スペインの銀行支援に関する合意がなされたため、金融市場は小康状態を続けてきた。しかし、ここにきて警戒が再び強まっている。

第28回
前回、「時間軸効果」について述べた。「量的緩和政策は経済の実態面には直接の効果を与えなかったが、時間軸効果の点では有効だった」というのが日本銀行の立場である。この問題を、もう少し論じよう。
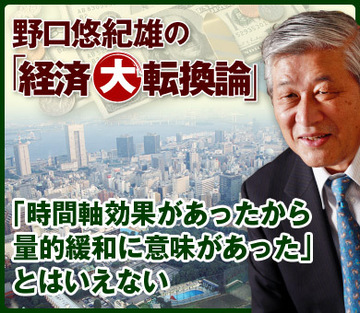
第27回
アメリカの量的緩和政策は直接的効果は認められるが、実物経済への影響はほとんど認められない。ただし、マネタリーストックは増えた。つまり、銀行の貸出が増えて、信用創造のメカニズムはある程度働いた。では、そのマネーは、どこに行ったのだろうか?

第26回
FRB(アメリカ連邦準備制度理事会)が一層の金融量的緩和(QE3)を行なうべきだとの声がある。それが行なわれれば、アメリカ経済や世界経済は好転するのだろうか? それを知るためには、これまで行なわれた量的緩和策(QE1、QE2)の効果を見ておく必要がある。

第25回
日本銀行による金融政策が、これまでどのように行なわれてきたかを振り返ってみよう。かつての日本では、市中金利は「公定歩合」と連動するように規制されていた。日銀はこれを操作することで金融政策を行なってきた。

第24回
金融政策を論じる際に参照する指標には、いくつかのものがある。それらは、量的な指標と、価格に分けられる。量的な指標の基本は、マネタリーベースとマネーストックだ。これらについて説明しよう。

第23回
これまで、量的金融緩和政策が物価動向に影響を与えなかったことを見てきた。他方において、日本の消費者物価が長期的・継続的に下落しているのは事実である。では、なぜ物価が下落するのであろうか?

第22回
日本の長期不況の原因は金融政策にあるとし、緩和政策を取るべきだとの意見は、外国からも日本の政策当局に寄せられた批判だった。しかし、量的緩和政策の結果を見て、「量的緩和政策は効果がなかった」と認めざるをえなくなった。
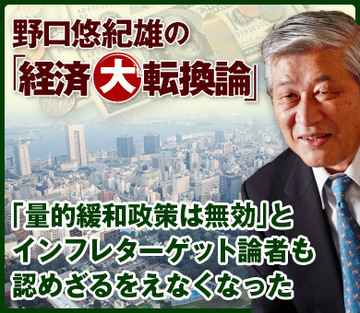
第21回
いま「日本国債バブル」と呼びうる状況だが、日本の財政状況がきわめて悪いにもかかわらず、国債に対する需要が大きいのは、不自然である。これはヨーロッパの金融危機がもたらした異常な事態であるが、日銀による国債購入がバブルをあおっている面も否定できない。

第20回
日銀は、5月23日の政策決定会合で、格別の追加緩和措置をとらないことを決定した。しかし、今後一層の金融緩和を求める圧力が高まる可能性が高い。そう考えられるいくつかの理由がある。

第19回
5月16日の日銀の国債買い入れオペでは、初の「札割れ」となった。つまり、金融機関は、国債を保有し続けることが有利と考えているのだ。そうなると、国債価格が暴落したときに、大きな問題を引き起こす。
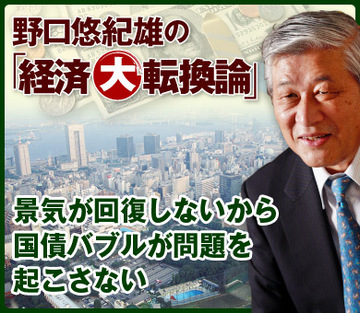
第18回
2001年に量的緩和を始めたとき、購入額が野放図に増えないために導入した日銀券ルール。このルールはすでに破綻しているが、重要なのは、現在行なわれている政策のメリットとデメリットを客観的に評価することである。3つの観点から見てみよう。

第17回
日本銀行は、4月27日の金融政策決定会合で、追加金融緩和策を決めた。他方で、2012年3月の全国消費者物価指数2ヵ月連続で上昇した。しかし、これは、日銀の金融緩和の結果ではない。それとはまったく関係がない原因によって消費者物価が上昇しているのである。
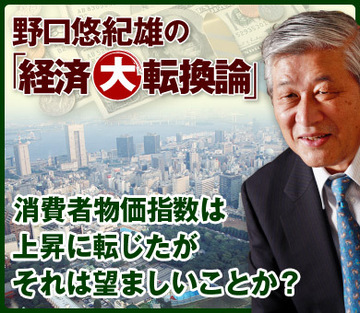
第16回
「新興国工業化の影響は、世界的なもので、日本だけがその影響を受けるはずはない」と反論されることがある。ではアメリカの消費者物価が上昇しているのはなぜか。アメリカも新興国工業化の影響を受けているはずだ。