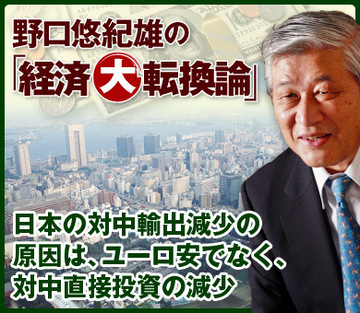野口悠紀雄
第15回
以下に述べるのは、「10秒間勉強するだけで、中国語が読めるようになる」という方法である。「そんなのはマユツバだ」と感じられる読者が多いと思う。しかし、そうではないのである。これは、日本語と中国語の関係が特殊であることを利用した合理的な方法なのだ。
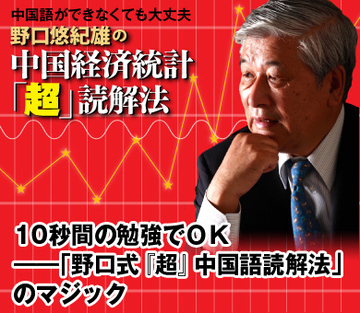
第14回
今回は、中国語の文章を読むことにチャレンジしてみよう。当面の目的は、新聞記事や統計の解説を読むことだ。「何の予備知識もなしに中国の新聞を読む」というと、無謀と思われるかもしれないが、実はそんなことはない。
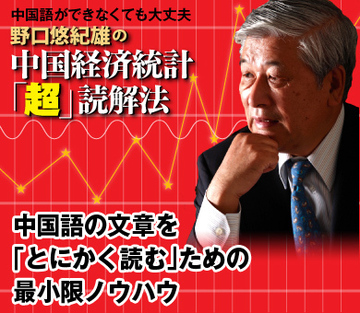
第13回
前回述べたのは会話などのバーバル(口頭の)・コミュニケーションだが、今回は簡字体の読み方について述べる。統計や文書を「読む」という観点からすれば、このほうが重要とも言える。法則を知っていれば、かなりの簡字体を、格別の努力をせずに読むことができる.。
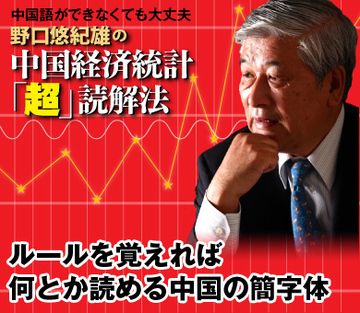
第12回
今回は、本筋の作業からは少し離れて、中国語そのものの学習について述べることとしよう。さまざまの学習用音源や無料の語学講座などが、インターネット上に提供されるようになってきた。中には非常に優れたものもある。これらをどう使いこなすべきか。
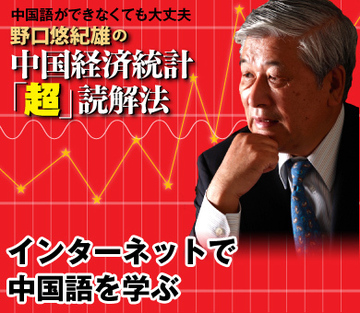
第11回
財政というテーマは、馴染みにくいものだ。しかし、中国を考える場合には、大変重要な意味を持っている。社会主義時代からの流れで公的企業が多く、いまでも共産党一党独裁が続いているので、公的部門の動きが経済全体の動向に重要な影響を与えているからである。
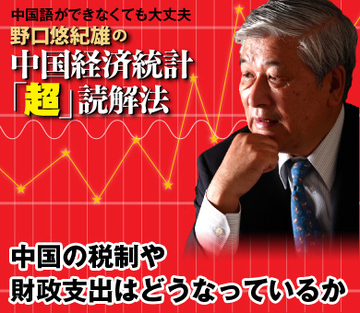
第10回
中国の住宅事情は、つぎの2つの要因によって、きわめて特殊なものになっている。第1は、社会主義経済時代には、住宅の私有が認められていなかったことだ。第2は、急速な経済成長による購買力の上昇と、農村人口の都市への流入によって膨大な需要増が生じたことだ。
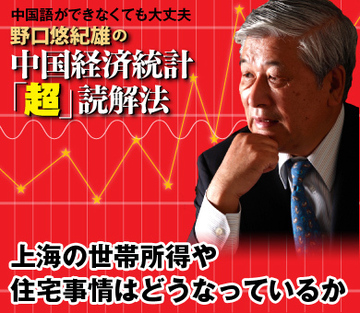
第9回
中国における賃金上昇は著しい。最近では、15%程度となっている。このことは生産拠点を中国に持つ外国企業にとって大きな関心事だ。これまで日本など世界の先進国企業が生産拠点を中国に移したのは、賃金が低かったからだ。
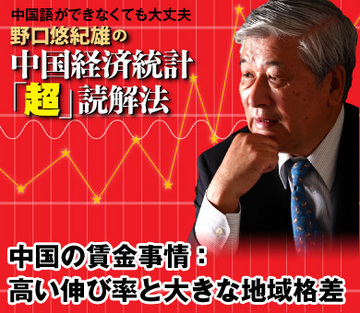
第8回
中国では、物価上昇が大きな問題となる。2011年7月の消費者物価指数は、前年同月比6.5%の上昇となり、大きな問題だとされた。これは、経済危機後に中国がとった景気刺激策の影響だという意見も聞かれた(この見方が正しいかどうかは、後で論じる)。
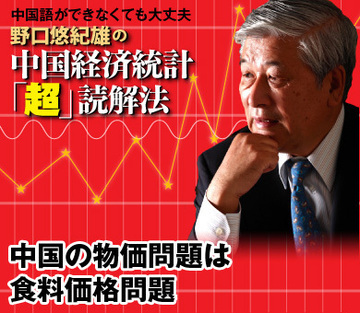
第7回
金融統計はさまざまな統計の中でも信頼性が高いものだ。しかも、迅速にデータが手に入る。したがって、経済情勢を把握するのに最適だ。以下では、中国人民銀行のサイトで公表されている金融関連データによって、中国経済を把握することを試みよう。
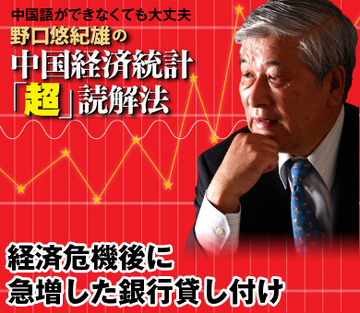
第6回
中国の住宅価格、不動産投資、金融政策は、経済危機後大きく変動した。前回に引き続き、この状況を中国のウエブサイトからのデータによって跡付けてみよう。前回に見た住宅価格動向と不動産業投資との関係はどうなっているだろうか?
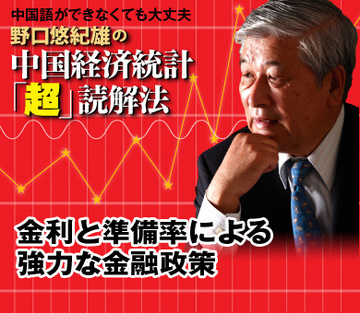
第5回
中国の不動産投資と住宅価格は、経済危機後、大きな変動を経験した。中国経済の動向を理解するためにも、不動産投資と住宅価格のデータを把握しておく必要がある。
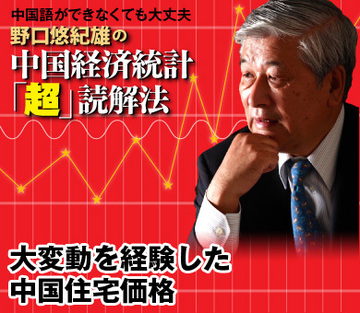
第4回
前回の最後に触れたように、国家統計局のサイトには、英語ページがある。したがって、無理して中国語で読もうとせず、英語のページを開いてしまうほうが簡単な場合が多い。ただし、注意する必要がある点が2つある。
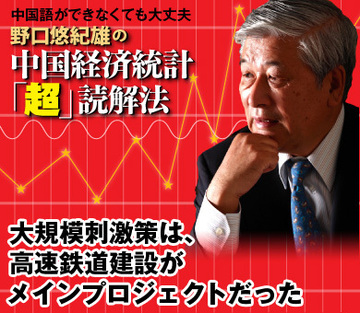
第3回
中国の国内総生産(GDP)が注目を集めている。経済危機後の2009年から10年にかけては、先進諸国の経済成長率が軒並み落ち込むなかで、景気刺激策に支えられて中国は高成長を維持した。その影響で日本から中国への輸出も増加し、それが10年における日本経済回復の大きな原因になった。
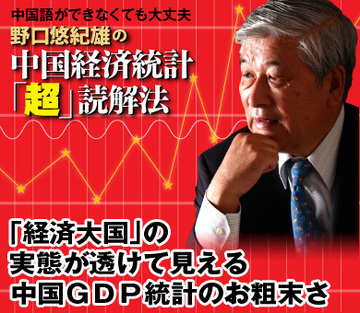
第2回
今回は、中国株式市場に関するウエブサイトを開いて、中国語の予備知識なしにデータを入手することに挑戦しよう。どの国でもそうであるが、株価は経済の動向を知るための最も基本的なデータの一つだ。しかも、さまざまな経済データの中で、通常、最も早く入手できる。
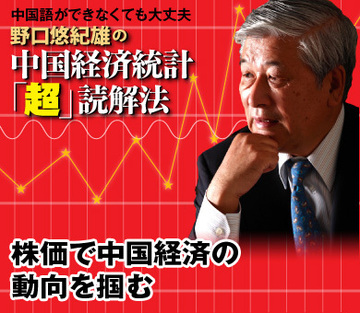
第1回
中国語の知識ゼロで、中国語で中国の情報を収集しよう。これが、この連載でこれから提案することだ。多くの日本企業が、中国関連事業を将来の事業計画の中核に据えている。だから、中国に関する情報の入手は、これからのビジネスマンにとって重要な課題だ。
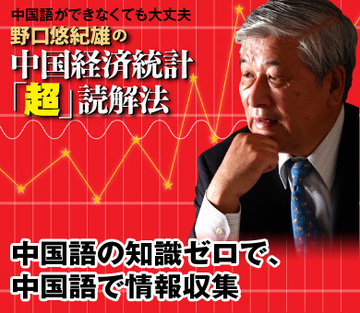
第42回・最終回
ジョン・モールディン、ジョナサン・テッパー著『エンドゲーム――国家債務危機の警告と対策』(山形浩生訳、プレジデント社、2012年8月)も、この連載で取り上げてきたテーマについて論じている。本書が描く世界経済の推移は、つぎのとおりだ。
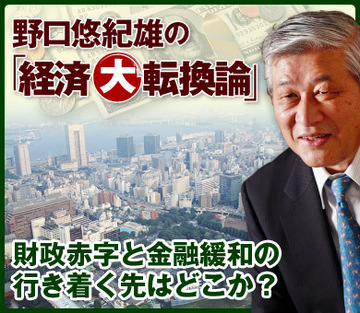
第41回
カーメン・M・ラインハートとケネス・S・ロゴフの『国家は破綻する――金融危機の800年』(村井章子訳、日経BP社、2011年3月)が注目を集めている。ただし、本書の主張に対して、とくに日本に関する部分に疑問点がある。以下に述べることとしよう。

第40回
財貿易統計によると、2012年度上半期(4~9月)の貿易収支は3兆2190億円の赤字となった。これによって、経常収支の黒字も縮小する。これをめぐる議論の中には、誤りに陥っているものもある。その一つとして、国債消化との関連に関するものがある。

第39回
中国に対する日本の輸出が減少していることを述べた。日本の鉱工業生産指数はさらに落ち込む可能性が高い。対中輸出は、現在の日本経済で最大の下振れ要因となっている。したがって、その減少がいかなるメカニズムで生じているのかを知ることが重要だ。

第38回
日本の鉱工業生産指数は、7月、8月とも対前年同月比でマイナスになった。原因は、日本の対中輸出減少だとされる。そして、その原因は、ユーロ安によって中国の対EU輸出が減速していることだとされる。本稿ではこの理解が正しいものかどうかを検討する。