井手ゆきえ
第336回
2型糖尿病患者は、アジア人でもがん死リスクが高い
2型糖尿病(2DM)患者は、がん死リスクが非患者より高いことが知られている。ただ、それを裏付ける研究の大半は欧米人が対象。もともと糖を代謝するホルモン「インスリン」の分泌が少ない東アジア人でも、欧米人と同様に発がんリスクが上昇するかは曖昧だった。先日、中国、日本、台湾などアジア7カ国で行われている19の疫学調査から、2DMと発がんリスクについて統合解析した結果が報告された。

第335回
認知症を予防する飲酒量は?1日あたり0.5合程度が上限
飲酒は認知症の発症リスクになることが知られているが、少量飲酒は予防に働くらしい。中国海洋大学(山東省)の研究チームからの報告によれば、全認知症と大量飲酒との間には、以前から指摘されているように発症リスクが増加する傾向が認められた。

第334回
「男の更年期」改善、男性ホルモン補充療法の効果に疑問符
団塊世代を狙い、日本でも「テストステロン(男性ホルモン)」の低下に伴う心身の不調に対し、ホルモン補充療法(TRT)が注目され始めた。ところが昨年来、TRT先進国の米国から「TRTには期待するほどの効果はない」という複数の試験結果が報告されている。

同じ病気で、同じ病院に入院しても担当医が違うと治療費はかなりばらつく。治療成績が金額に比例して上がるなら納得できるかもしれないが、高い治療費を払っても死亡率、再入院率にはほとんど影響しないというのだ。

第333回
玄米食べてカロリー消費!1日分で約30分の運動に匹敵
玄米など全粒穀物食は、肥満を防止して慢性疾患のリスクを減らすといわれている。米国では、国の「食事ガイドライン」で全粒穀物製品を少なくとも毎日3オンス(85グラム相当)食べるよう推奨しており、全粒穀物=健康の図式は定着したようだ。

第332回
電子たばこは禁煙補助になる?英米で異なる見解
受動喫煙対策をめぐる議論が沸騰しているが、先日「キャンサー・リサーチUK(英国)」から「電子たばこ」の安全性に関する研究結果が報告された。研究では、普通のたばこの喫煙者、喫煙+ニコチン補充療法(NRT)、もしくは電子たばこで禁煙を試みている最中の人、そして禁煙後にNRTか電子たばこに切り替え、半年以上を経過した181人について、唾液と尿中の有害物質濃度を検査。

第331回
不安・うつはがんの初期症状?結腸・直腸、膵臓などで関連
うつ病など気分障害と身体の病気は強く関連し、うつ病があると心筋梗塞の発症リスクは4倍以上に上昇する。近年はがんとの関連が指摘されている。

花粉情報協会によると、今年は関東、東北では「例年並みかそれ以下」の飛散量だが、西日本は例年並み~やや多め。大量の花粉に悩まされそうなのは近畿地方の一部と四国、九州地方だという。花粉症対策について取材した。

第330回
「睡眠時無呼吸症候群」実は2種類、閉塞性・中枢性で違い
眠っている間に10秒以上呼吸が止まる睡眠時無呼吸症候群(SAS)。日中のひどい眠気や集中力の低下が自覚症状だ。肥満が発症リスクだが、顎が引っ込んでいる人や首回りが43cm以上ある人もリスクが高い。ただしこれは“閉塞性”睡眠時無呼吸症候群(OSA)の話。

第329回
周期的に下腹部が痛む「大腸憩室炎」は赤身肉を控えて予防
大腸憩室炎という病名を聞いたことがあるだろうか。耳慣れないが、食生活の変化でじわじわ増加している疾患の一つだ。

第328回
災害時に心臓を守るリスト付き、循環器学会監修の防災セット限定販売
日本循環器学会は、今年3月の学術集会を記念して循環器救急医療・災害対策委員会が監修した「循環器防災セット」(1セット5000円、税別)1000個を事前予約制で限定販売する。

第327回
子供とスポーツ脳振とう、運動再開は7日以内に?
スポーツ少年団などで子供たちの指導をする人は、ケガへの対処法を知っておく必要がある。このうち、脳振とうは頭を強く打ったときに生じると思いがちだが、正確には「頭部、顔面への直接、あるいは首へ伝達する他の身体の部位への衝撃で生じる『頭部外傷』」を指す。直接、頭を打つだけでなく、頭が激しく揺れるような衝撃でも生じるわけだ。

第326回
サウナで認知症リスク低下、本場フィンランドの報告
お父さんたちの疲労回復に、若い女性の美肌・痩身にと根強い人気がある「サウナ」。さらに昨年末、サウナの本場フィンランドから「認知症予防に良い」という報告があった。研究者らは、フィンランド在住の中年男性(42~60歳)2315人を対象に、サウナを利用する頻度とアルツハイマー型認知症(以下AD)および、その他の認知症リスクとの関係を検討。

インフルエンザが流行中である。特に免疫がまだない0~4歳と65歳以上の高齢者はワクチンを接種していても重症化のリスクがあるので、早期の対応が重要だ。基礎的な治療と予防法をまとめた。

第325回
ポケモンGOの運動量増進効果、最初の2週間だけ!?
巷で噂される「ポケモンGO(ポケGO)」の運動量増進効果は、控えめに見積もったほうがいいらしい。昨年末、英国医学雑誌(BMJ)のクリスマス特集号に掲載された報告から。研究者らはインターネット経由で参加者を募集し、2016年8月に「ポケGO」で生じる運動量の調査を実施。米国在住の「iPhone6」ユーザー1182人(年齢18~35歳)が参加した。

第324回
がんに匹敵する悪性疾患「足の狭心症」とは?
血管が硬く、もろくなる「動脈硬化症」。糖尿病や高血圧症、脂質異常症(高脂血症)がリスク因子で、近年は手足に血液を送る末梢動脈の動脈硬化症:PADが注目されている。PADの自覚症状は手足の冷え、しびれ、痛みなど。進行すると「間欠性跛行」──しばらく歩くと足の筋肉が痛み歩けなくなるが、数分休むと歩ける、という特有の症状が出てくる。

「女性医師が担当した入院患者は男性医師が担当するよりも死亡率が低い」――。米学会誌で発表された日本人研究者の論文が現地の有力な新聞がこぞって取り上げるほどの騒ぎとなった。その内容とは。

第323回
インフル予防に漢方「補中益気湯」の可能性
インフルエンザの季節だ。予防には、マスク着用と手洗いの徹底を。おつかれ気味なら、漢方薬の補中益気湯(ほちゅうえっきとう)を試してみよう。

第322回
生活習慣調査から見えた「健康な高齢者」と「不健康な若者」
先日、厚生労働省から「平成27年国民健康・栄養調査」が公表された。これによると、過去10年間で糖尿病と脂質異常症が疑われる人の割合は、ほぼ変化がなかった。加齢が発症リスクであることを考えると「健康を気遣う高齢者」が増えたと推測される。
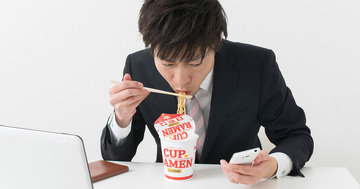
この冬のインフルエンザは立ち上がりが早く、例年より1ヵ月ほど早い11月中旬に「流行期」に入った。地域の保健所、医療機関は病院が休む年末年始に患者が増加するのではと警戒している。
