
山崎 元
第137回
昨年の総選挙では、民主党の目玉政策の一つだった「子ども手当」だが、その後大切に扱われているとは言い難い。まず、はっきり言おう。「子ども手当」は、官僚にとって美味しくないのだ。
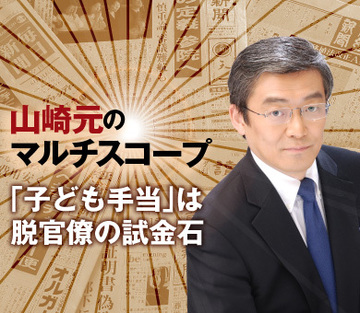
第135回
米国のベンチャーキャピタリストが書いた本を読んでいたら、ベンチャー起業家が投資家向けにプレゼンテーションする場合の市場予測は、4~5年先の数字が多いと書いてあった。

第136回
1億円以上の役員報酬開示義務付けを受けて、定時株主総会で高額報酬者の情報開示が相次いでいる。筆者は全面開示を推進すべきだと思っているが、そのあるべき方向に一歩踏み出すいい制度変更だと評価したい。
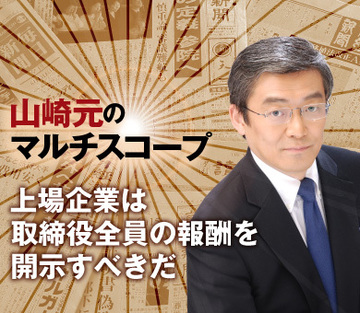
第134回
「夫婦で年収600万円をめざす!」というサブタイトルに興味を持って、花輪陽子『二人で時代を生き抜くお金管理術』という本を読んでみた。著者は「昭和の時代遅れのライフスタイルでは破産する可能性もあります」と警告する。

第135回
今回も大相撲の話題で恐縮だが、どうしても指摘しておきたい問題がある。当事者能力のない日本相撲協会の問題もさることながら、相撲を報じてきたジャーナリズムのあり方だ。彼らは、力士の常習的賭博への関与についても、十分知っていたのではないか。
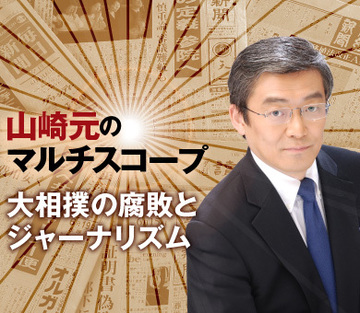
第133回
筆者は電気製品や文房具などへの物欲が旺盛なほうだ。ここのところ、iPhoneとiPadを手に入れて触っている。そこで、iPhone、iPadで、個人投資家の投資管理向けにこんなものがあればいいなあ、というアプリをいくつか考えてみる。

第134回
大相撲の不祥事が止まらない。文科省の川端大臣は、相撲協会に対応を委ねる趣旨の発言をしているが、それは責任放棄だ。相撲協会にまともな統治能力はないのだから、文科省が責任を持って同協会の浄化と統治能力の再構築に乗り出すべきだ。
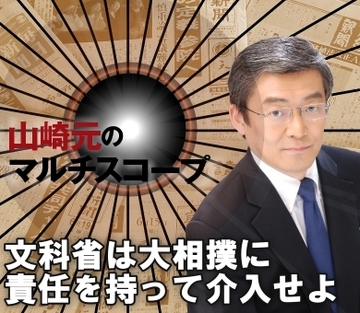
第132回
筆者は今年の4月から獨協大学で「金融資産運用論」という授業を行っている。学部生(2~4年生)を相手に、資産運用のあれこれを説明しているのだが、先日、いわゆるポートフォリオ理論の代表的な理論であるCAPM(資本資産価格モデル)を説明した。

第133回
菅氏は、増税しても、そのお金を正しく使えば、景気は良くなり、失業が減るという趣旨のことを何度か口にしている。だが、その考え方は官製事業の連鎖的拡大による日本経済の急速な社会主義化を招く可能性がある。
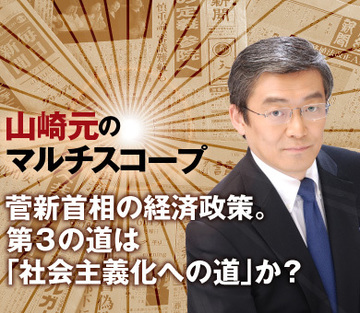
第131回
ギリシャの財政問題に始まった今回の経済的混乱は、資本市場に大きな影響を与えた。一方、こうした「危機」を感じさせるイベントが起こったときに、妙に活性化する一群のビジネスがある。

第132回
離婚の方が結婚よりも何倍も大変だ、と多くの人が言う。連立政権も同じようなものらしい。この離婚(連立解消)の「有責配偶者」は誰が見ても鳩山首相であり、福島氏は、別れる際に、鳩山氏の不実を印象づけて、夫の世間体に決定的なダメージを与えた。
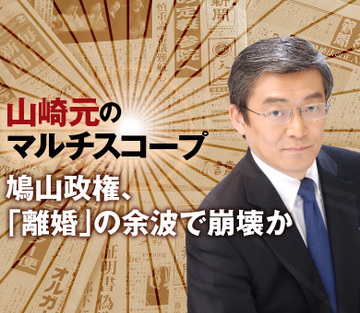
第130回
日本の財政破綻が「絶対ない」とはいえまい(じつは、どこの国でもそうだと思うが)。今回は、財政が将来破綻に近い状況に陥ることが十分あるという前提で、個人の資産運用を考える。

第131回
ギリシャの財政問題を切っ掛けに起こった世界金融市場の混乱は、株価で見ると、2009年前半以降の回復過程にあって、最大の下げ率を記録するに至った。だが、これで日本の株価の大きなトレンドが下向きに変化したということではないように思う。
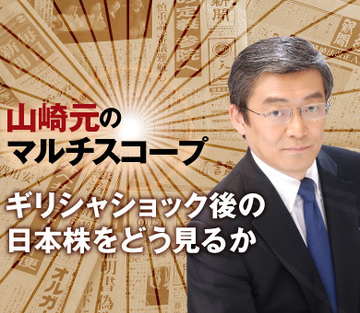
第129回
ギリシャの財政悪化は想定の範囲内で、欧州経済は今後もたつくが、米国の金融緩和が中国などの新興国の経済成長を後押しする構図は崩れないだろう。むしろ欧州の問題でこの状況がより長く温存されるのではないか、というのが筆者の読み筋だったが、想定より大きな問題になった。

第130回
子ども手当で入ってくるからと言って、子供に使わなければならないとか、まして特別に有利な運用方法があるわけではない。しかし、それでも何か特別な運用をしたいという読者のために、筆者もひとつプランを提示しよう。
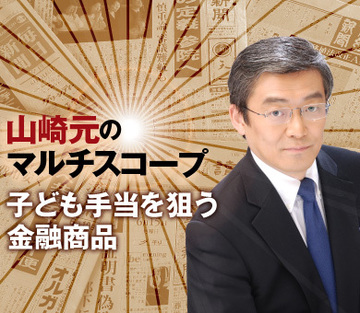
第128回
わが国で現在販売されている金融商品を見ると、リスクを取る商品は、インデックス・ファンドを選ぶしかない。運用会社が直接投資家に販売する独立系の直販投信にも期待したが、今のところ、これは魅力的だと思えるものがない。

第129回
朝日新聞に、菅氏の知恵袋であるらしい人物のインタビューが載っていた。「需要拡大こそ大切 財源ないなら増税」という見出しだ。仮に菅氏の考えが同じだとするならば、それは民主党のマニフェストの正反対であり、菅氏は離党すべきだ。
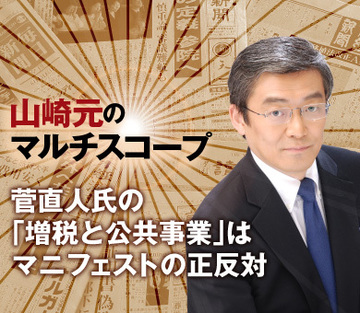
第127回
ゴールドマン・サックスがSECに証券詐欺の嫌疑で訴追された。常識的には、商品の中身が十分開示されていれば、それを誰が売りたがっていようが、買いたがっていようが、組成・販売会社がその情報を開示する必要はないように思えるが、法的な白黒はそうとうに微妙であるように思える。

第128回
世界の株価回復を背景に、企業年金の運用利回りが改善しているという。企業としては、ここで2通りの考え方がある。一つは将来を信じて確定給付(DB)の企業年金を続けること。もう一つはそれを畳む準備に入ること。筆者は後者をお勧めする。
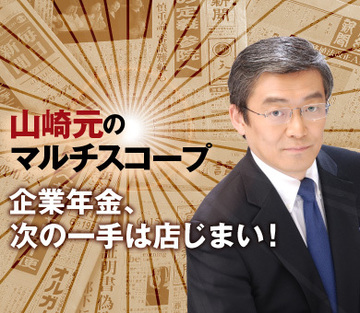
第126回
金融機関による投資教育をひと言でたとえるなら、カモ(=いいお客)の養殖ということになる。顧客側にとっては決定的に重要でも金融機関側にとって不都合な知識を「教えない」ことがしばしばある。
