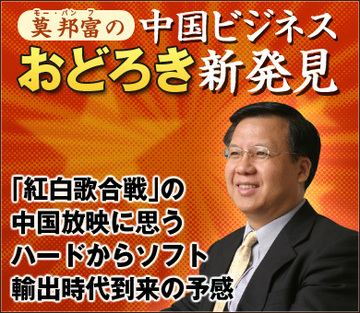莫 邦富
第105回
中国4直轄市の一つである天津は、1980年代、90年代と経済発展から取り残された。だが、2005年の中国の「第11次5ヵ年計画」を契機に急速に発展。今、天津の街を歩くと、この都市が自信を取り戻したことを強く感じる。
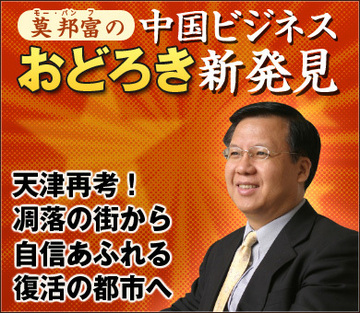
第104回
上海で友人たちに有無を言わさず連れ出された先は、日本の商店街を模した和食レストランのフロアだった。日中関係はこのところ政治的にギクシャクしているが、食の安全と安心に対する関心を背景に、中国では日本食に対する投資熱が高まっている。
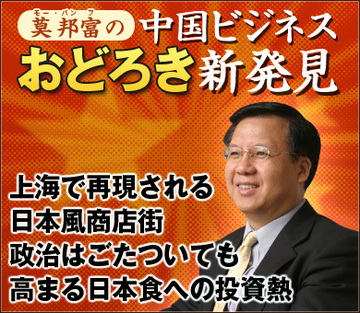
第103回
中国でも、1997年のアジア金融危機対策として、ゴールデンウィークを設定した。その結果、日本と同様に観光客の洪水を経験し、弊害の方が大きくなった。この経験を踏まえて、中国では黄金週間を小型化、分散化させて、観光業の安定的な成長を図っている。
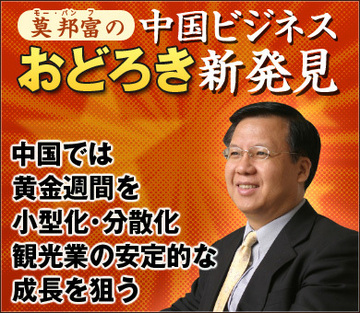
第102回
年間、相当数の講演会をこなす。その旅の途中、多くの方々と挨拶を交わす。その短い接触が後に花を咲かせた出会いも結構ある。そんな出会いの例として、宇部市の久保田后子市長と石川県観光交流局の北村修次長のケースを紹介したい。

第101回
安徽省政府代表団、経済貿易訪日団などが、大挙して来日し、日本側と真剣な議論を交わした。だが、一般的に日本の関心は、まだ大都市に向いている。中国人観光客を呼び込むなら、地方にも目を向け市場を育てながら共に歩むことが大切だ。
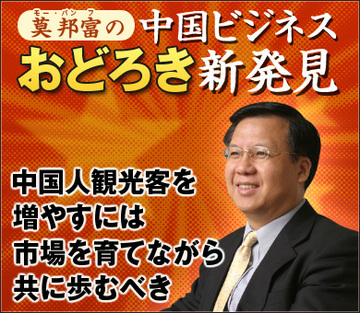
第100回
改革・開放路線以後、上海は急激に発展したが、その過程で外国ブランドに敗れ、上海ブランドは衰退してしまった。今、ミルクキャンディそして乗用車と、上海ブランド復活の動きが本格化している。質やブランドの確立を求める時代が始まった。
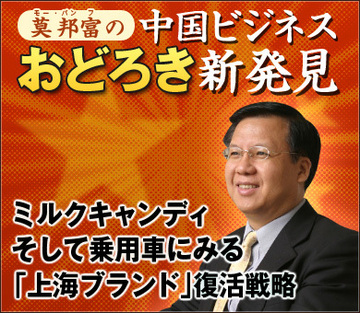
第99回
2月末札幌を訪れた。夜のすすきのを歩くと、楽しげに歩く外国人観光客を目にした。地方都市の場合、外国人観光客たちから、日本の夜が長くて退屈だという不満を聞かされる。昼間だけでなく、楽しい夜をどう演出するかという地道な努力も欠かせない。

第98回
食品業界の専門展示会である「ファベックス」が開かれる。我が事務所もこれに参加しているが、中国でも食の安全・安心への関心が高まると読んだからだ。大震災で中国から出展者を呼ぶことができなった昨年と違い、今年は食の日中交流飛躍の年にしたい。
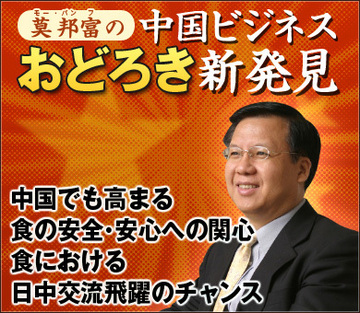
第97回
山東省エン州市を訪れた。石炭の産地という程度の知識しかなかったが、幼稚園から高校卒業まで学費は無料、ハイテク装備のスクールバスの導入も進めていると聞いて驚いた。都市間では経済力競争から、福利厚生を充実させる競争が始まっている。
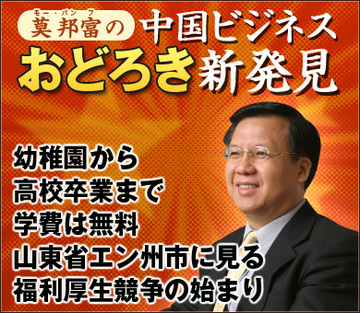
第96回
中国とインド、両国はこれからアジアの2大大国となることが間違いない。この両国に関してとても興味深い本を読んだ。進出先の選択肢の研究と巨大な市場になりつつある今日の中国を見つめるには、読み応えのある2冊である。
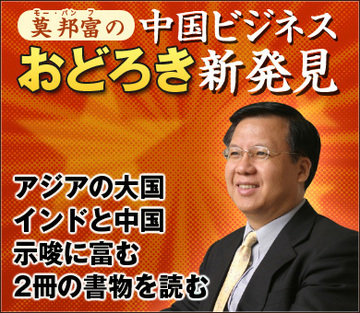
第95回
中国でも農村の疲弊が深刻だ。日本の三ちゃん農業状態に陥っている。一方、私が訪れた高知県・馬路村は見事村おこしに成功している。馬路村の「おらが村方式」というブランディング手法そのものも、中国に輸出できると思う。

第94回
前回、入管のサービス向上を訴えたコラムは、大きな反響を呼んだ。これで少しは入管の対応にも変化があるかもしれないと期待したものの、それは見事に裏切られた。今回はその時の実体験をお伝えする。
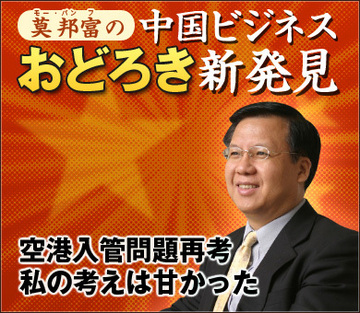
第93回
異国の旅では、それがどんなに小さくても不快な出来事が、心のどこかに傷を残す。その代表が成田空港など代表される入管職員の態度である。先日も「日本人優先」という怒鳴り声に、「ようこそ日本へ」というスローガンが色あせて見えた。
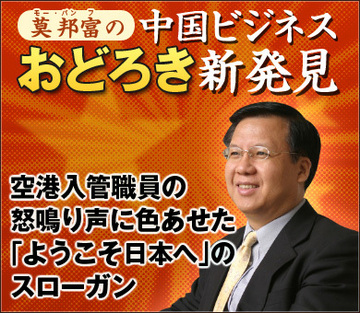
第92回
日本経済の強い足腰を形作る中小企業が減少を続けている。このままではさらなる減少は避けられない。ただ、東京都大田区を筆頭に中小企業の海外進出を支援する動きも加速している。こうした動きが他の自治体に広がることを期待したい。
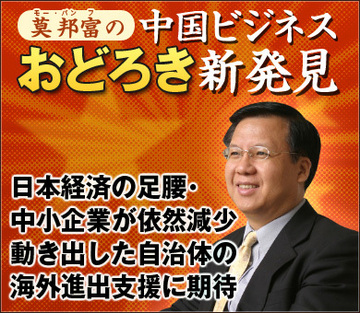
第91回
私腹を肥やす、恣意的な評価をする、平日にゴルフをする。これは中国における中国人社員の話ではない。中国に派遣されている日本人社員の実態だ。こうした状況に愛想を尽かして、有能な中国人社員が日本企業を去っている。

第90回
富山で買ったパン、東京郊外の新築マンションの広告。この二つを中国版SNSである新浪微博で取り上げると、中国のフォロワーから大きな反響があり、SNSはいまやビジネスにとって欠かせない文明のツールであることを再認識した。
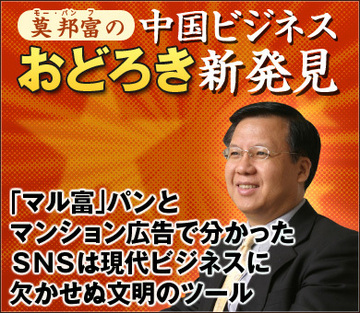
第89回
日本の地方に行くと中国人の間で高まる北海道人気が話題に上る。みな映画の影響と考えているが、それに先行した地道な誘致努力がその背景にあるのだ。一方、山梨県も信玄と風林火山という2枚看板から脱皮した、新しいキャッチフレーズが外国人観光客の心に響いた。

第88回
中国は民族大移動の時期である旧正月(春節)に入った。沿岸部の企業では、格安マンションを提供したり、故郷までの送迎バスを出す一方で、内陸部では帰郷した労働者をスカウト。年を追うごとに、労働者の確保合戦は熱を帯びている。
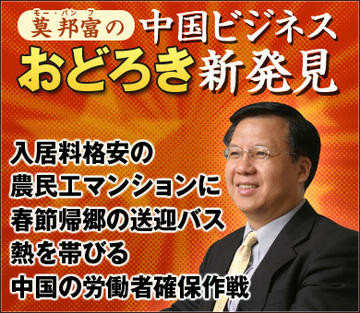
第87回
送り先が不在のお歳暮をヤマト運輸が自宅に送り返してくれた。しかも、その中身だった果物を新鮮なものに入れ替えて。このことを中国のSNSである微博に書いたら、フォロワーからは次々に賞賛の声が寄せられた。
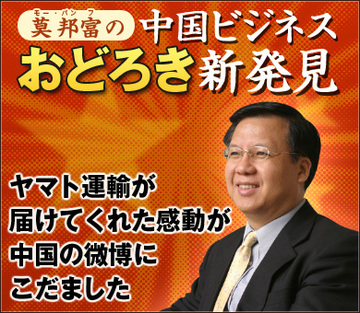
第86回
中国で初めて紅白歌合戦が放映された。いまや中国の消費者は中国製のテレビで日本発の番組を見ている。ハードでは追いつかれてもソフトでは日本はまだまだ進んでいる。ソフトの面で、いかに中国とウィンウィンの関係を作るのか、その課題に正面から取り組む必要がある。