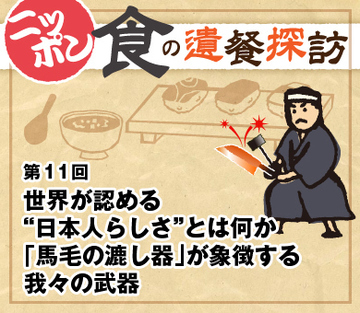樋口直哉
第6回
菜食主義者として有名な人物に、マハトマ・ガンジーがいる。ガンジーは「食事は必要最低限であるべき」と考え、簡素な生活を求めた。若い頃、実験と称して肉を食べたが、母親に隠し事をしている罪悪感に耐え切れず、以後肉食をすることはなかったという。
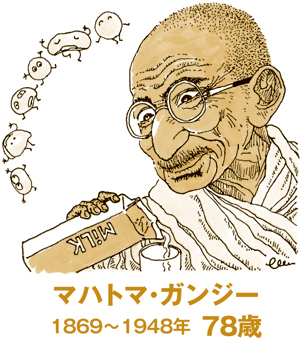
第22回
クジラの解体を見に行くことになった、と言ったら、何人かの知り合いから「クジラってまだ捕ってもいいの?」と驚かれた。僕らは、東京から車で2時間半ほどかけ、沿岸小型捕鯨が行われている千葉県和田を訪れた。驚いたのは人の多さだった。

第5回
根拠があるわけではないが、作家は短命というイメージがある。芥川龍之介が35歳、太宰治は39歳、自ら命を絶っていることも個人的な印象を強めている。しかし、女性作家はなかなかに元気だ。瀬戸内寂聴先生をはじめ、宇野千代と、たくましい女性が多い。

第21回
日本の鶏は安価だ。それは1960年以降、アメリカの大量飼育法が導入されてからだが、半面で本当に美味しい鶏肉に接する機会を失ってしまった。しかし、宮崎県高鍋町で黒岩正志さんが育てている『黒岩土鶏』は本当に美味しい鶏だった。
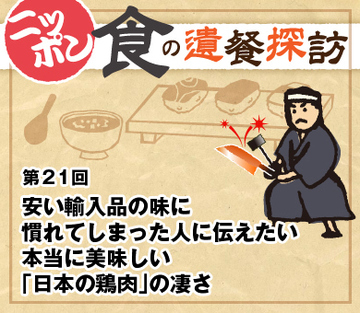
第4回
明確な数字、根拠があるわけではないが、画家は総じて長生きだ。シャガールは97歳、ピカソは91歳、モネは86歳、ダリは84歳といった具合に。そんななかで今回取り上げるのが、特に日本人に愛されていると言われる画家のモネだ。
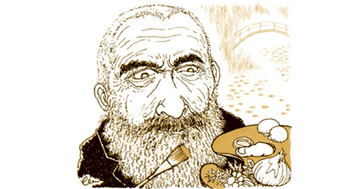
第20回
地方では思いがけず、いい食材に出会うことがある。大山食品の酢もそのひとつだ。海外で困るのが、質の良い米酢の入手。外国人が好きな寿司も質のいい米酢がなければできない。酢は普段決して目立たないが、たしかに日本の味を支えている。
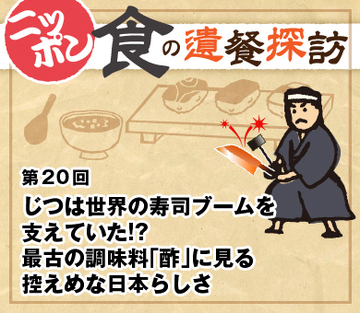
第3回
戦国時代から江戸時代にかけて最も長生きした人物といえば南光坊天海である。天海は謎の多い人物で、生まれもはっきりしていないが、享年108歳と言われている。平均寿命が30代という時代に、煩悩の数と同じ年だけ生きた。
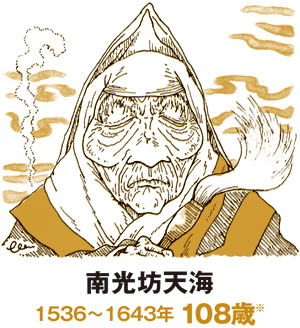
第19回
国際社会での日本の影響力低下が叫ばれる一方、料理界では必ずしも当てはまらない。かつて海外星付きレストランのシェフが来日すると、包丁を何本も買い込んで本国に持ち帰る光景が見られたが、今では誰しもが日本の包丁を使う時代になった。

第2回
平均寿命が37~38歳であった当時、75歳まで生きたという徳川家康。長寿の理由の1つとして、適度な動物性タンパク質の摂取を挙げる研究者は少なくない。実は家康、キジやツルの焼き鳥を好んだと言われている。
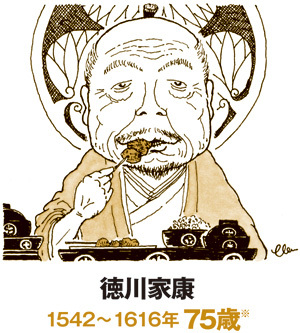
第18回
日本の3大発明をご存知だろうか?『二股ソケット』『ゴム足袋』『亀の子たわし』と言われている。二股ソケットもゴム足袋もグローバル企業を育てたが、現在は商品を見かけることはなくなった。しかし『亀の子たわし』は今も愛され続けている。

第1回
ジャンヌ・カルマンという人物をご存じだろうか? 彼女は人類史上、最も長生きしたとしてギネスブックに認定された女性である。野菜が嫌いで、好きな食べ物は「赤ワイン」と「チョコレート」。この2つを生涯欠かすことがなかったそうだ。
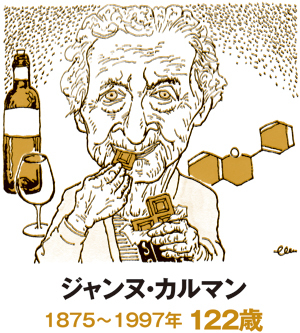
第423回
我が国が南極海で実施している調査捕鯨について日豪が争った国際裁判で、日本完敗といえる判決が出た。今すぐ鯨食が危機に陥るわけではないが、関係者の失望は察するにあまりある。ではなぜ、日本は裁判で「完敗」しなければならなかったか。

第17回
日本の卵が世界に誇れる理由は、国産食材の安全性を象徴しているからだ。外国では卵の生食を勧めていないが、日本は生食が基準であることからも明らかだろう。しかし、そんな鶏卵事情に変化が起きている。鶏卵価格が上昇しているのだ。

第16回
今、世界のシェフたちが「昆布」に関心を寄せている。カロリーゼロ、豊富な旨味、日本にしかない神秘性が彼らを惹き寄せる。そんな昆布が世界から注目されることになった立役者の1人が、福井県敦賀の昆布問屋『奥井海生堂』社長・奥井隆さんだ。

第15回
「お茶は難しいですね」。静岡市にある茶問屋〈やまはち〉の事務室でお話を伺っている途中、茶師の前田さんは何度も「難しい」という言葉を繰り返した。前田さんは日本屈指の茶作りの匠と評される人物。そんな人が「難しい」と言うのだ。
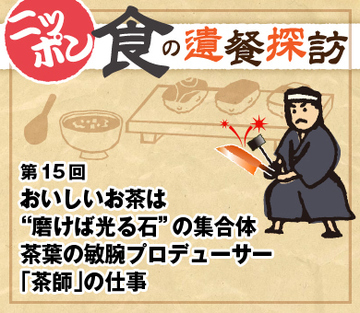
第14回
「三陸のカキ養殖場を廻りませんか?」2013年の11月。ヤフーの復興支援室の方に誘われて、三陸のカキ養殖場をいくつか見学した。まわっていて気がついたのは、その味わいがかの有名な広島産にも劣らないということだった。

第13回
僕が子どもの頃、「日本は資源の乏しい国です」と教わった。でも、日本は本当に資源の乏しい国なのか?なぜそんなことを考えたか。それは取材した『折箱』という器は日本が森林資源を有効に使えなくなったことを象徴していると考えたからだ。
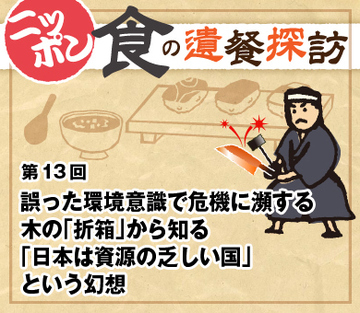
第385回
和食がユネスコの『無形文化遺産』に登録される見込みになり、どの記事からも祝祭ムードがただよう。でも僕には喜んでいていいのかという気持ちと、一連の報道に違和感がある。違和感の正体はどの記事も『「和食」とは何か』はっきりしないことだ。
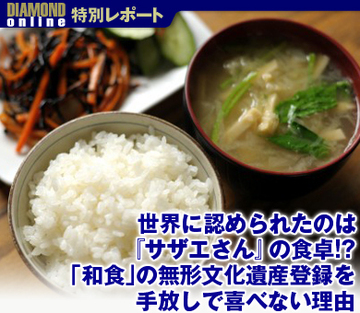
第12回
簡素な箱のなかに砂糖がまぶされた野菜が肩を寄せ合うようにして詰まっている。淡い野菜の色合いがきれいだ。梅鉢屋の『野菜菓子』は江戸時代から続くお菓子。野菜をつかったお菓子は最近定着したが、江戸時代からあったとは知らなかった。
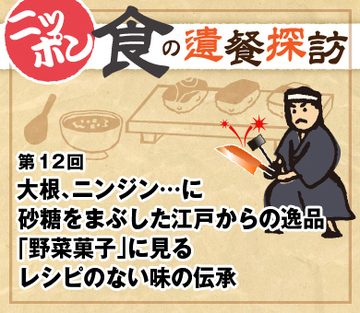
第11回
外国で働く日本人シェフは、「日本人らしさ」を求められるという。その「日本人らしさ」とは何か。それは「日本人の繊細な味覚を通した料理」なのだという。今回、紹介するのはそんな日本の繊細さを象徴している道具『馬毛の漉し器』である。