樋口直哉
第30回
今、スーパーに行けば肉や鮮魚はプラスチックのトレイで売られているけれど、昔、食品を包むのに使われていたのは経木である。この経木には、日本人が失ってはならない何かが含まれている。

第13回
代表作『山椒魚』で知られる井伏鱒二。井伏は、ひょうひょうとして動じず、悩みもユーモアで包み込む性格だった。さらに好きなものを食べ、酒を飲む。特にウイスキーを愛した。そんな彼は95歳まで生きた。
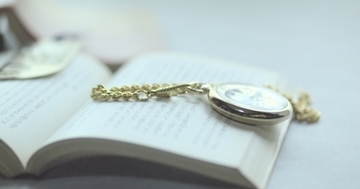
第29回
このところ欧州で「海藻」が人気だ。それにともない海苔の佃煮をつかうシェフも登場している。しかし日本では海苔の佃煮を食べたことのない子どももおり、その存在感が薄れつつある。そんななか、江戸前で絶品の「海苔の佃煮」に出逢った。

第12回
音楽家のロッシーニは美食家で知られ、オペラから早々と引退した後は美食三昧の毎日を過ごした。「20枚のステーキを食べ、太っていた」という記述もあったそうだが、彼は当時としては長生きの76歳まで生きた。
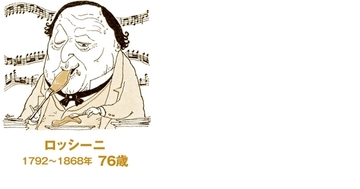
第28回
群馬県にある醤油の老舗・有田屋を訪れた。醤油産業は第二次世界大戦前後になると食糧危機が深刻化し、代用醤油が生まれた。実は丸大豆を使った本醸造が復活したのはここ数十年のことである。醤油の世界では長い間、戦後が続いていたのだ。

去年の暮れから「世界一のレストランNomaが日本に来る」と高級レストラン業界は持ちきりだった。「Nomaって蟻を食べさせるところでしょう」とよく言われるが、決してそれだけではない。デンマークの経済まで変えた存在なのだ。

第11回
レヴィ=ストロースは世界で最も名が知られた文化人類学者だ。彼は驚くべき長寿であり、しかも100歳で亡くなるまでその思考は衰えることがなかった。彼が“食”について関心を持ったことと、フランスの文化は無関係でないように思う。
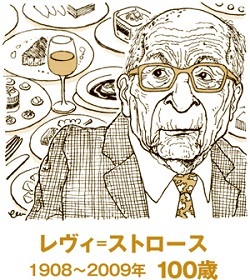
第27回
増え続けている訪日外国人の来日目的の1位は「日本食」らしい。そんな日本食は時折、「味が薄い、淡泊、単調」と指摘されることがある。しかし、そんな日本にも諸外国に誇れる刺激的な香辛料、調味料がある。『かんずり』はその代表だ。

第10回
飯田深雪はアートフラワーというジャンルの創始者。驚くのは彼女が100歳を超えてなお現役だったこと。教室で生徒に指導し、NHKの長寿料理番組『きょうの料理』に、100歳を記念して出演している。
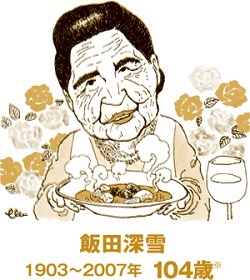
第26回
下仁田ネギで有名な群馬県下仁田町にある『下仁田納豆』は昔ながらの経木納豆を製造している会社だ。社長の南都さんは大手企業に就職し、働きはじめたものの、都会での生活に迷いも生じはじめ、21年前に実家の納豆屋を継いだ。

第9回
今でも広く読まれている『ファーブル昆虫記』の作者であるファーブルはかなりの長生きで、この昆虫記を書き始めたのが55歳の時、63歳で再婚して、91歳まで生きた。ファーブルは普段、どんな食生活を送っていたのか。

第25回
日本人は稲作から多くの文化を生み出してきた。稲からは米だけではなく、米糠、籾殻、藁がとれ、生活のすべてに利用された。藁は縄の材料となり、衣服、日本家屋の壁、布団にもなった。そして今回、紹介する「米俵」の材料でもある。

第8回
『論語』でおなじみの孔子は、長寿でも知られる。没年齢の74歳は春秋戦国時代ということを考えれば、かなりの長命だ。『論語』の「第十郷党篇」からは食にこだわりを持っていた様子がうかがえる。
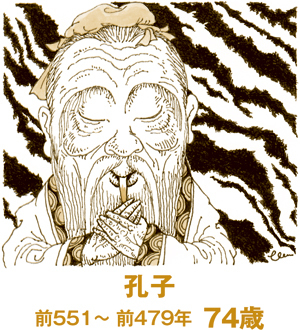
第24回
最近、海外で木の良さが見直されている。北海道旭川にある高橋工芸はもともと家具の脚などを手がけていたが、家具の需要低迷に伴ない、カップなどの制作を開始。大きな転機は、紙のように薄い木のコップ「Kami Glass」を発表したことだった。

第503回
高視聴率で話題のNHK朝ドラ「マッサン」の主人公は、ニッカウヰスキーの創業者、竹鶴政孝とその妻リタがモデルです。話の中心ともなる存在の日本産のウイスキーは今、実は世界で熱狂的な人気を集めていることをご存じでしょうか。
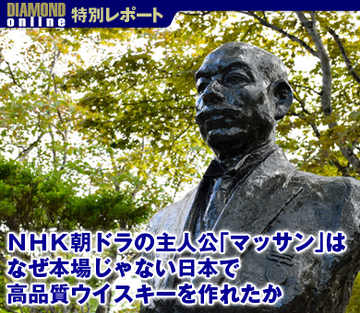
第497回
政府は農林水産物の輸出額を2020年までに1兆円水準にする目標を定めている。日本の農産物をこれまで以上に輸出するためにはなにが重要なのか?そのヒントを求めて、北海道美瑛町を訪れた。この町のゆり根が台湾で人気だと聞いたからだ。

第7回
やっぱり長生きはするものだな、とイマヌエル・カントの人生を知ると思う。彼が『純粋理性批判』を書いたのが、57歳の時だったからだ。生涯を独身で通した哲学者の生活は規則正しいものだった。
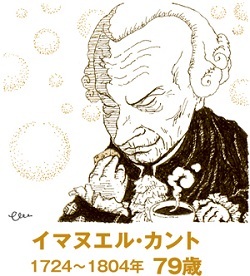
第23回
本連載は基本的には日本の食文化の周縁を取材し、記事にしている。その流れから言えば今回のテーマ「パン」は世間一般の常識からいえば〈日本の文化〉と思われないかもしれない。しかし、もはや日本のパン食は“日本の味”になりつつある。

第492回
国は2020年の東京五輪までに訪日外国人の数を2倍にする目標を掲げている。そのためには東南アジアからの観光客を増やすのは至上命令だが、イスラム教徒の多い彼らは、日本を訪れることを『食』を理由に躊躇しているという。
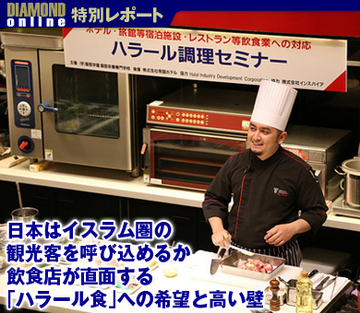
第490回
今年の夏、「ニホンウナギ」絶滅危惧種指定に「もう食べられなくなる」と危機感を抱いた人も多かっただろう。そして今度はマグロだ。日本人が世界総生産量の8~9割を消費していると言われるなか、クロマグロが漁獲規制の対象となったのだ。
