樋口直哉
第10回
「芸術品をつくる人はともかく、道具をつくる人は減っていくと思うよ」。浅草・銅銀銅器店の三代目、星野保さんがいかにも江戸っ子という、べらんめえ口調で言う。鍋の中でも優れた性質を持つ銅鍋だが、なぜか最近使われなくなってしまった。
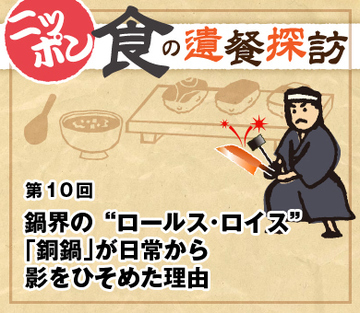
第9回
巻きすは、日本独特の道具である。日本料理では、巻き寿司をつくるときはもちろん、大根おろしや茹でたホウレン草の水気を絞ったりもする。そんな巻きすはどこで作っているのか疑問に思い検索すると、一軒の簾屋「田中製簾所」がヒットした。
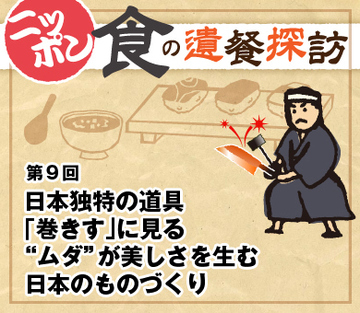
第8回
貴族の飲み物だった麦茶は江戸時代から屋台で飲まれ出した。一般家庭の定番になったのは、昭和30年代、冷蔵庫が普及してから。そんな昔ながらの煮出し麦茶をつくる小川産業を訪ねると、古い木造の工場で大きな音を立てながら麦茶が煎られていた。

第7回
千葉県君津市久留里の城下町では、江戸時代から武士の内職として、楊枝作りが行われていた。ここでつくられているのは〈雨城楊枝〉と命名された高級楊枝だ。しかしこの雨城楊枝、今日に至るまでに2度の大きな危機に襲われていた。

第6回
上野駅から合羽橋道具街へとのびる浅草通りを歩き、稲荷町の駅を抜けたあたりにある『宮川刷毛ブラシ製作所』には様々な種類の刷毛とブラシが並ぶ。普段はあまり存在感のない刷毛だが、じつは伝統的な日本の美を支える重要な要素である。

第5回
戦後、ガラス産業は東京の一大産業となり、数多くのガラス製品が輸出され、神武景気を支えた。その後、輸出は減少し、海外から安価な製品が輸入されるようになったが、今再び海外から評価され、製品を輸出するガラスメーカーが東京にある。

第4回
『巨人・大鵬・卵焼き』の時代には〈幸せな暮らし〉という言葉のイメージに、ある程度の普遍性があったように思える。時が過ぎて、巨人人気のピークは過ぎ去り、大鵬さんは先ほど亡くなった。それでも人気を保ち続けているのが「卵焼き」だ。

第3回
寿司が世界に広まって久しいが、そんななかにあっていまいちブームに乗りきれなかった存在が「海苔」である。外国人には黒い紙とも揶揄されることも多いが、宮城県東松島市で、パリパリしているのに口に入れると消えてしまう極上の海苔を見つけた。
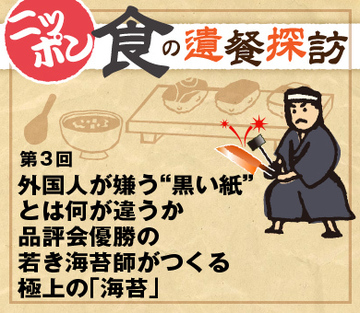
第2回
麩というのは実に地味な存在だ。しかし、そんなイメージを払拭するような「すごい麩」が西会津にある。その麩をつくる職人は、麩とは縁もゆかりもなかった元広告マン。彼がその道に進んだのは、「子どもの大学進学資金を稼ぐため」だった。

第1回
日本料理は特徴的である、とよくいわれる。例えば「おろす」という調理法はフランス料理や中国料理にもない。そもそもおろし金という道具自体、日本にしか存在しないらしい。だからなのか、成田空港でやたらおろし金が売れたことがあったという。
