
小黒一正
ロシアのウクライナ侵攻で国際秩序も大きく変容を迫られている。こうした中、政府は「経済財政運営と改革の基本方針2022」で防衛費の拡充を念頭に、「新たな国家安全保障戦略等の検討を加速し、国家安全保障の最終的な担保となる防衛力を5年以内に抜本的に強化する」旨の記載を行っている。

日本銀行が6月上旬に公表した国内企業物価指数は、前年同月比で約9%の上昇となった。ロシアのウクライナ侵攻に伴う資源価格高騰の影響もあるが、円安の影響も大きい。この状況下、米国と日本の金利差拡大が円ドルレートに影響を及ぼし、円安の圧力を高めているとの指摘が有識者の間で増えてきた。

日銀が公表した3月の国内企業物価指数の上昇率は、前年同月比9.5%であった。資源価格の高騰や円安が続くなか、いつまで日銀は金利を抑制できるのか。円安は米国の連邦準備制度理事会(FRB)が金融政策を引き締めに転換し、利上げを進めている影響も大きい。

ロシアのウクライナ侵攻で原油価格が高騰し、日本を含む世界経済に大きな影響を及ぼし始めている。2016年3月に109円だったガソリン1リットル当たりの小売価格(東京都区部)は、3月中旬時点で170円超で推移。1970年から現在まで、小売価格が最も高い値を付けたのはリーマンショック直前(08年8月)の182円だ。その次は第2次オイルショック時の177円(82年9~12月)。

新型コロナウイルスの3回目のワクチン接種が進んでいるが、終息は見えない。それにもかかわらず、2022年度当初予算(国の一般会計)の税収見積もりが過去最高の65.2兆円となった。21年度も、当初予算の税収見積もり(57.4兆円)と比較して、法人税を中心に増収の見込みで、63.8兆円を超える可能性が出てきた。

財政再建のため、政府は国と地方を合わせた基礎的財政収支(PB)を2025年度までに黒字化する目標を掲げているが、コロナ禍で目標が達成可能か疑問が出てきている。

政府は2022年度予算案を取りまとめた。予算規模は107兆円超で、22年1月の通常国会に提出される予定だが、少し前の臨時国会で成立した21年度補正予算は補正予算の規模としては過去最大の35.9兆円で、財源不足の22兆円は国債発行することも決まっている。

「成長と分配の好循環」を促すため岸田首相は「新しい資本主義実現会議」を立ち上げたが、分配の原資捻出には成長が不可欠で、低成長の解決には資源配分の見直しも必要だ。政策では必ず予算が必要だが、現下の厳しい財政事情の中、この実行には財政中立で予算に関する資源配分の見直しも求められる。

衆議院選挙が終わったが、再分配機能の強化には経済成長の引き上げと再分配の財源確保が必要だ。岸田文雄首相は当初、金融所得課税の見直しで再分配の強化を行うつもりであったことが窺い知れるが、10月上旬に「岸田ショック」と呼ばれる株安が発生して発言を控えるようになった。しかしこの株安は、国内の金融機関による季節的な売却が主因であったことが判明している。では、岸田政権が金融所得課税の見直しを行う理由は何か。

厳しい財政事情の中、社会保障給付費(約120兆円)のうち約40兆円を占める医療費への改革圧力が高まり、経済財政諮問会議や財務省は、CTやMRI等の高額医療機器の配置適正化を求めている。だが、国民医療費に占める医療機器のコストに関する正確なデータは存在しない。そこで、「薬事工業生産動態統計」データ等を用いて筆者が推計したところ、市場規模は2001年の1.96兆円から18年で2.9兆円にまで膨らみ、この間、年率平均2.3%で成長している可能性が分かった。

コロナ禍で財政赤字が拡大し、今後の財政やマクロ経済に及ぼす影響が気になるが、日銀の大規模な金融政策は継続、長期金利がゼロ近傍で推移しているため、財政規律に対する認識は弱まっている。

新型コロナウイルスの感染拡大は世界的流行となったが、日本を含む世界に対し、有事に向けた「平時の備え」の重要性を再認識させた。8月15日は終戦記念日だが、有事に向けた「平時の備え」という意味では、防衛関係の備えも重要ではないか。

先般、国勢調査(2020年)の人口速報値が公表された。日本の総人口は1億2622万人で、15年時点の調査と比較し約86万人の減少となったが、本格的な人口減少はこれからだ。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」(17年)によると、20年で7408万人であった生産年齢人口(15~64歳)は、40年で5978万人に減少するとされている。
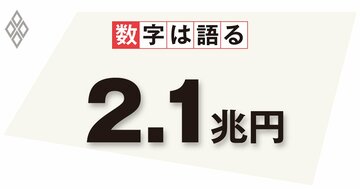
新型コロナの第4波により、緊急事態宣言が6月20日まで延長となった。日本経済に及ぼす影響が当然気になるが、その一つの判断材料となるのが、先般内閣府が公表した「四半期別GDP速報」(2021年1~3月期・1次速報)だろう。

先般、日銀は定例の金融政策決定会合を開催。この決定会合では、2023年度の物価見通しが1%にとどまる可能性を新たに公表した。

新型コロナウイルスの感染拡大は都市構造や経済社会を本当に変えていくのか。この問いに現時点で答えることは難しいが、人口減少や少子高齢化が進む中、都市構造の変化が経済社会に及ぼす影響として最も関心が高いものの一つが合計特殊出生率だろう。

先般、内閣府は四半期別のGDP速報(2020年10~12月期・2次速報)を公表した。この速報から、20年の年率換算の名目GDPは539.1兆円。19年の名目GDPが561.3兆円であったから、20年の名目GDPは前年比で約22兆円の落ち込みと予想される。これは想定以上の回復スピードである。

予測や試算は、一定の前提に基づいて推計を行うものであり、推計と実績が乖離する可能性があるのは当然である。だが、英国やオーストラリア等では、GDP成長率の予測が実績と乖離した場合にはその要因分析を行い、モデルや推計方法に関する有識者の意見も取り込みながら、次回以降では乖離を縮小させるための仕組みが存在する。

緊急事態宣言が再発令されたが、コロナ危機のための経済対策で財政は急激に膨張中だ。

少子化に直面する日本をはじめとする国々では、人口密度の高い地域ほど低い出生率の傾向があるが、それは見せかけの相関かもしれない。
