
小黒一正
インフレ経済に突入した日本で、積極財政の処方箋は通用するか、低所得層中心に支援対象の精緻化を
日本経済はインフレ転換後も名目賃金の伸びが追い付かず、低所得層を中心に家計への負担が深刻化している。内閣府が2025年11月17日発表した7~9月期のGDP速報値では、実質成長率(季節調整値)は前期比マイナス0.4%と、6四半期ぶりのマイナス成長となった。

物価2%超が政策の前提に、日本は財政リスク拡大に備え、支援対象を精緻化した再分配を
2022年4月以降、日本の消費者物価指数(CPI)は、総合、コア(生鮮食品を除く総合)共に前年同月比2%超の上昇を続け、25年8月分の公表値までで41カ月連続という異例の持続局面に入った。
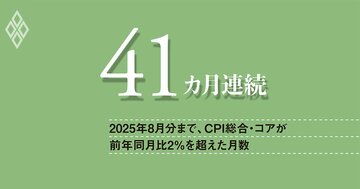
超長期金利「3%時代」に突入、金利急騰と円安圧力の板挟みで、財政再建の実行力が焦点に
今年5月下旬、日本の30年物の国債利回りが3%台に到達し、1999年の入札開始以来、最高水準を記録した。背景には、インフレと生命保険会社など伝統的な買い手の需要後退に加え、日本銀行の国債買い入れ減額ペースも影響している。一方で、副作用も顕在化しつつある。
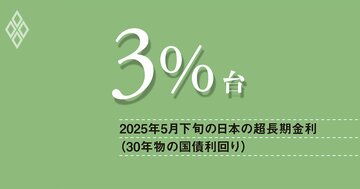
購買力平価と市場為替レート、乖離率は歴史的水準、インフレ念頭に政策立案を
数年前までは1ドル=100円前後だった市場為替レートが、2022年以降は円安が急速に進み、一時1ドル=160円を突破した。このような市場為替レートの変動と並行して注目すべきは購買力平価だ。

インフレ経済への転換が一般会計予算案にも影響、社会保障関係費の伸びを抑制
日本経済がデフレからインフレ経済へと転換する中、日本財政の懸案であった社会保障予算でも興味深い現象が起こり始めている。

地方の若者が東京に流入する主な段階は大学進学ではない、誤解に基づく政策を正せ
石破首相が力を入れる政策の一つが「地方創生2.0」だ。地方創生は2014年にスタートし、出生率の低迷や地方の衰退に歯止めをかけるため、東京一極集中の是正を政策目標の一つに掲げてきた。だが、地方創生の出生率への効果は確認できない。背景には、二つの大きな誤解がある。

巨大地震で想定される国債金利の上昇、有事に備えた財政基盤強化を
2024年8月8日、「南海トラフ地震臨時情報」が発表され、地震の想定震源域で巨大地震への注意喚起が初めて発令された。その後、臨時情報は解除されたが、今後も巨大地震が起こる可能性はある。仮に首都直下地震が発生した場合、国債の発行が必要となるだろう。そのため、長期金利(国債の利回り)が一時的にどの程度上昇するかについての予測も重要だ。

東京の出生率最下位の誤解、再計算で判明した東京3区の高い平均出生率
6月5日、厚生労働省は2023年の人口動態統計を公表した。同年の日本の合計特殊出生率(TFR)が過去最低の1.20に低下する可能性がある。

増加の見通しが続く医療・介護の社会保険料率、抑制に向けた制度の導入を
2024年4月2日に開催された経済財政諮問会議において、内閣府は「財政・社会保障の長期試算」を公表した。この長期推計は、「中長期的に持続可能な経済社会の検討に向けて(2)」で示されたもので、三つのシナリオに基づき、2060年度までのマクロ経済・財政・社会保障の姿を試算している。

診療報酬改定を巡る攻防はインフレ率で財務省に軍配、社会保障の予算策定に変化も
2024年度における国の予算編成では、日本医師会を巻き込みつつ、診療報酬の改定率を巡って財務省と厚生労働省が激しい攻防を繰り広げた。攻防の結果は、23年12月20日の「大臣折衝事項」という文書で明らかになった。

2024年は財政改革「検証の年」、予測と実績の乖離に目を向け、財政健全化プランを作成せよ
政府は、2025年度までに国と地方を合わせたプライマリーバランス(PB)を黒字化する目標を掲げている。岸田文雄首相は23年11月2日の記者会見で、現在もこの目標を変更する考えはないと説明した。そこで、内閣府が毎年2回公表する「中長期の経済財政に関する試算」(1月版・2月版)のデータを、12年度以降の予測と実績値で比較した。

上がり続ける日本の物価、政府は減税策の前に金利上昇のリスクに備えよ
国内物価の上昇や円安が続く中、日本銀行は今年7月、イールドカーブ・コントロール(YCC)を修正した。事実上、長期金利の上限を0.5%から1%に変更する内容だ。約3カ月が経過した今、長期金利は0.8%程度まで上昇し、上限の1%に近づきつつある。背景には、物価やドル円レート、米国の長期金利の影響が主にある。

国立社会保障・人口問題研究所が今年8月に公表した「社会保障費用統計」によると、2022年度の社会保障給付費は138兆7,000億円で、21年度から6兆5,000億円(4.9%)増加した。これは1950年度の集計開始以降、過去最高の値だ。本稿では、今後の社会保障費を巡る(1)政府の予測と実績の乖離問題と、(2)現役世代の負担増に関する問題を概説した上で、その解決策を提示する。

止まらない円安の原因は日米間の金利差だけではない、修正経常収支で分かる別の要因
止まらない円安の原因は何か。メディアでよく挙げられるのは日米間の金利差だが、これだけが原因とは限らない。筆者が注目しているのは、経常収支の構造的変化だ。
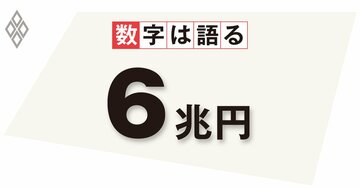
上がり続ける社会保険料は少子化対策に逆行、上限設定も検討すべきだ
岸田政権の目玉の一つは「異次元の少子化対策」だ。一部先送りとなっていた財源問題に対処すべく、政府は新たな支援金制度の創設を模索している。目的は社会保険料率の上乗せによる財源の捻出だが、子育てを担う現役世代の負担がさらに増えることへの懸念が拭えない。

岸田政権が「異次元の少子化対策」に本腰を入れている。合計特殊出生率を上昇させるにはどこにターゲットを絞るべきか、専門家でも断言が難しいのが現状だ。出生率を引き上げるヒントはないのか。

日本財政が大きな転換点を迎えている。従来はGDP比で約1%だったわが国の防衛費が約2%に拡充されるほか、日本銀行の金融政策転換の可能性も高まっているからだ。この状況下、今年1月、内閣府が「中長期の経済財政に関する試算」の最新版を公表した。

2022年12月7日、防衛費の財源に関する自民党と公明党の協議で大枠が決まった。両党は23年度から5年間の防衛費の総額を約43兆円とし、新たな予算増加分を約17兆円とする方針を確認した。

日本のインフレは今のところ米国ほど深刻ではないものの、インフレが重大な政治問題に浮上した場合、何が起こるのか。最も難しい判断を迫られるのは日本銀行であろう。

財務省は2023年度予算の概算要求を8月末に締め切り、2年連続で110兆円規模の水準となった。23年度の予算編成における懸案事項は、(1)脱炭素社会の実現に向けた「グリーントランスフォーメーション(GX)」、(2)子育て支援の司令塔として23年4月に創設する「子ども家庭庁」、(3)ロシアのウクライナ侵攻を契機とする防衛予算といった課題への対応だ。
