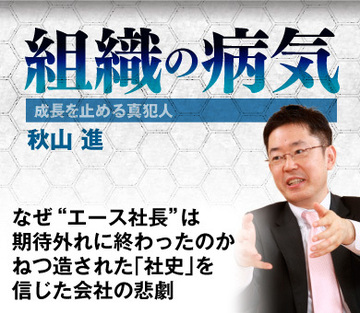秋山進
第25回
組織の重要な意思決定はこのように行われる。実力者が、最適だと思われる機関を利用し、自分の意思を巧妙に組織の意思に作り替えるのだ。だからシナリオ外の決定はほとんどない。これを「意思決定ロンダリング」と呼んでもいいだろう。

第24回
以前この連載で理系と文系がいかに解り合えないかを話したことがあるが、職人と商人にも深い溝がある。私は社長なので形式上は商人だが、そのメンタリティは100%職人。つまりは「こだわりの強い、面倒くさい人」なのである。

第23回
最近当たり前になった「モチベーション」という言葉だが、1980年代まではそれほど一般的ではなかった。それまでは似た言葉として「モラール」が使われていたからである。なぜ「モチベーション」が「モラール」に取って代わったのか。

第22回
トヨタ豊田章男社長は「ヒットは打てなくても、バッターボックスに立ったことを評価したい」と発言したことがある。「失敗しても挑戦をいとわない人」を応援するという意味だが、実際、現場にそんな人材はどれだけいるだろうか。

第21回
人材バンクはメディアやいろいろな場面で、キャリアの一貫性の必要性を力説し、多くのビジネスマンも「一貫性のあるキャリアを積まなければならない」と思うようになった。しかし、一貫性は本当に必要なのだろうか。

第20回
質問タイムはすごく重要である。良質な質疑応答が行われると、個々人が明日から具体的に何をやればよいかのイメージが形成されることもある。実際に良い質問をした人には、社長から声がかかり、出世の道が開けたりすることもある。
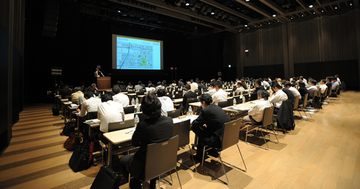
第19回
日本人にはプレゼンテーションが苦手な人が多い。まして英語でとなると、躊躇してしまう人はさらに少なくないだろう。そこでマイクロソフトシンガポールシニアマネジャー・岡田兵吾氏が、純日本人でも自信を持って英語でプレゼンできる方法を紹介する。

第18回
アジアの今や中核を成す都市になったシンガポール。なぜ同国ではみな残業しないのか。マイクロソフトシンガポールシニアマネジャー・岡田兵吾氏にその理由を聞いた。
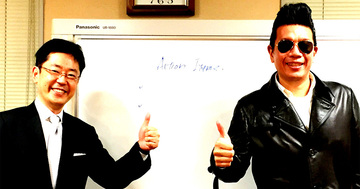
第17回
企業に“大義”は必要なのか。企業の目的を「利益の追求」であるとする人から見れば、「大義で飯は食えないよ」というわけだ。それは正しいと言えなくもない。だが、本当に大義なく儲ける会社に未来はあるのだろうか。

第16回
ある合弁企業で外国企業から出向してきた幹部が社員たちに、「私語が多い」と苦言を呈した。しかし、社員側にも言い分がある。「私語といえば私語ですけど、打ち合わせでもあるんです」。果たしてこの“ワイガヤ”は善か?悪か?

第15回
昨年末の話になるが、みんなが大好きな“ペヤング”にゴキブリが混入するというショッキングな事件があった。このような危機管理に関わる問題が起きると、私はいつも「この企業にも敏腕総務部長がいれば……」と思わずにはいられない。

第14回
トップ肝入りの新規プロジェクトが始動した。異色の人材を採用し、重職に抜擢。最先端の提携先と業界をリードする計画だ。しかしこの計画、大失敗に終わった。そう、これはあの理研の話。あなたは対岸の火事と思っていないだろうか。

第13回
ある和風レストラン。「ご新規3名様ご案内です!」と言われて中に通された。何度か行ってみたが、「ご新規様」と通される。そこで店員に、「もう5回目くらいなんですけど、どうして“新規”なんですか?」と聞いてみた。
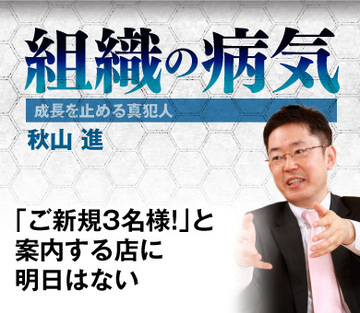
第12回
リクルート社を紹介するときに「褒める」文化がよく挙げられる。誰かが目標(ノルマ)を達成すると、名前入りの垂れ幕が下がり、職場は「おめでとう!」の声と拍手でいっぱいになる。「気持ち悪い」と感じる人もいるだろうが、私は悪いことだとは思わない。

第11回
ある企業でこんな話を聞いた。「彼はとても優秀だけど“中途だから”…(役員にできない)」。中途採用だから、出戻りだから、技術系だから。そんなことを気にしていられるのは、まだ企業に余裕があるからだろう。しかし、本当に余裕などあるのだろうか。

第10回
サラリーマン時代、本部商品企画部で仕事をしていると、現場部署の部長達から「うちの部の○○くんは企画が得意だから、君のところでどう?」とよく打診された。しかし、本部の企画部社員に求められている「企画力」とは、彼らの意図するものではない。
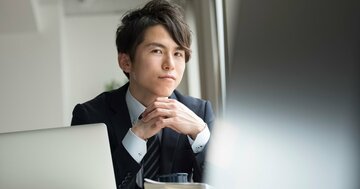
第9回
知人が長年、3人の重臣がオーナーからの寵愛をめぐり争いを続ける企業に転職した。彼に「寵愛レースには参加せず、自分はあくまでもスペシャリストです」という顔をした方がよいと忠告したが、聞く耳を持たなかった彼は非常に残念な結末を迎えた。

第8回
その道で深い知見を持つ人物たちが、自身の主張を雄弁に語るスーパープレゼンテーション=「TED」。最近、この方式を社内会議の場でも持ち込む人が増加している。しかし、そのすべてが「社内的に」評判がいいかといえば、そうではないようだ。

第7回
私のクライアントに「提案をしたい」と、大手コンピュータ会社の営業部長が連絡してきた。お受けしたところ、やってきたのはなんと10人。「この会社もずらずら病か」と私は軽く失望する。ずらずら大人数でやって来るところにロクな会社はないからだ。
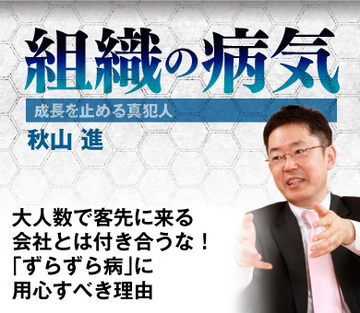
第6回
業績が停滞していたある企業に、新社長が就任した。彼は、過去に会社の主力事業を立ち上げて成功させた若きエース。当然、誰もが彼に期待した。しかし業績は一向に上がず、早々に「期待外れだ」という声が上がった。なぜエース就任は失敗に終わったのか。