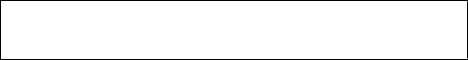キリンホールディングスとサントリーの経営統合が破談になったのは、残念だった。元気な企業同士だし、どちらも魅力的な製品を持っているので、統合会社が将来出す製品を見て(飲んで)みたかった(筆者は酒好きである)。
しかし、実際に両社の統合が行われた場合、どんな経営体制になったのかと考えてみると、本当にこの経営統合がよい経営戦略だったのかどうかについて自信がなくなる。それは、統合交渉を発表する際に「対等の精神」が強調されていたからだ。
対等とは、2つの集団のバランスを取るということであり、対等を強調する限り、2つの集団の区分が残る。組織として一体化しようとしても、「対等」を思い出すたびに、組織は割れてしまう。これが「対等の呪い」だ。
共にプライドの高い2社の統合の場合、「対等」ではなく、一方が他方を「吸収(買収)」するという前提では、吸収される側が納得できないのだろう。もっとも、表面的には「プライドの問題」であるかもしれないが、実質的には人事上の損得問題だ。双方に「人事上の既得権」を持った中間管理職クラスが相当数いて、彼らは、統合がなければ自分が得られたであろう人事上のポジションに固執する。合併ではよくあることだ。
人事上一方の集団だけを有利に扱うことはないという呪文として「対等」を強調すると、この前提を確認するたびに人事は停滞する。
この種の例としてよく引き合いに出されるのは、かつての第一勧業銀行だ。同行は合併後も20年以上にわたって2つの人事部を維持し、多くの場面で「D」と「K」とのバランスを取った「たすきがけ」を経営の基本とした。同行が、規模は大きくても、ついに一流行のイメージを築けなかったことと、対等にこだわった経営とは無縁でなかったように思われる。