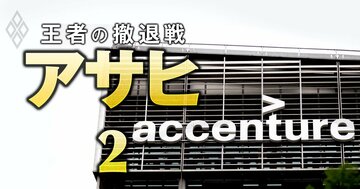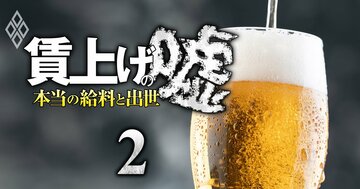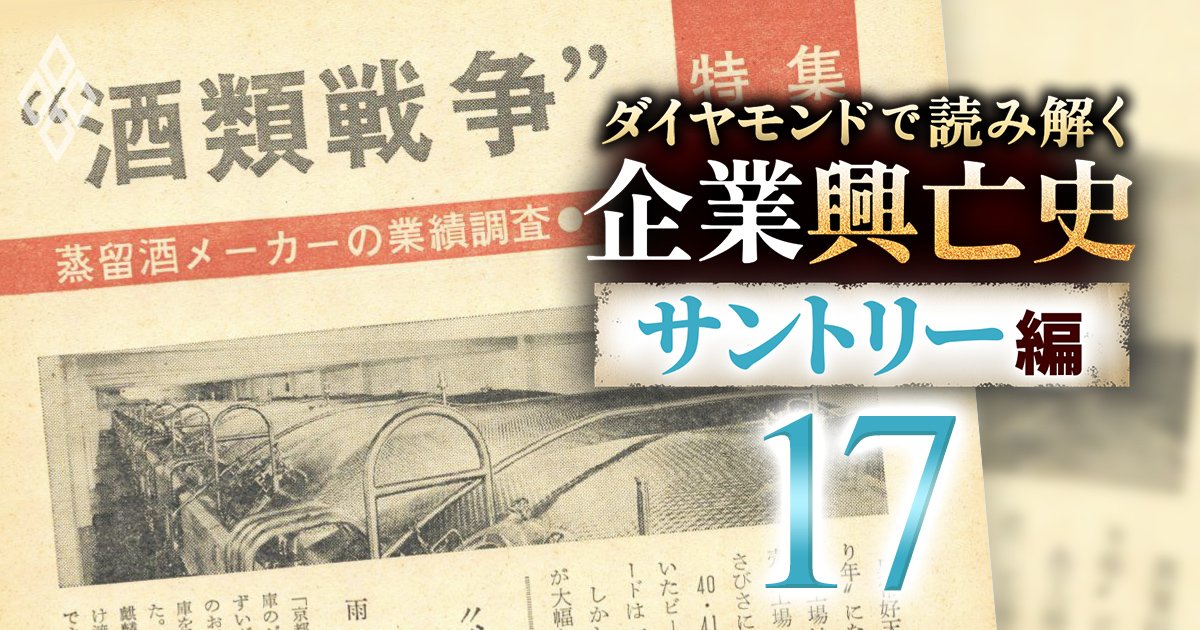
今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』では、「ダイヤモンド」1967年7月17日号の特集『ますます白熱化す“酒類戦争”ビール・ウイスキー・清酒・蒸留酒メーカーの業績調査』からの抜粋記事を2回にわたって紹介する。同年7月、宝酒造がビール事業から完全撤退し、ビール業界はキリンビール、サッポロビール、アサヒビール、サントリーの4社が競う構図に変わった。2年続けて低調だったビール市場も上向き、各社は積極策に打って出ていた。前編の本稿では、“四つどもえ”となったビール業界の当時の勢力図をおさらいし、各社の新製品や、工場の増強計画などの詳細を明らかにしていく。当時、サントリーは京都に新工場を設ける計画が浮上していた。(ダイヤモンド編集部)
宝酒造がビール事業から完全撤退
ビール市場が3年ぶりの拡大へ
「京都工場の明け渡しまでに、在庫のビールを売り切れるかどうかずいぶん心配した。しかし、地元のお得意さんの支援もあって、倉庫をぜんぶ空にすることができた。先ほど、東京から来られた麒麟麦酒の役員の方と、正式に工場明け渡しの調印を済ませたが、これでようやく肩の荷が下りた。10年間がんばった努力は実らなかったが、これから心機一転、やり直します……」
こうしみじみと語るのは、宝酒造の久木田稔取締役総務部長である。1967年7月1日――。この日をもって、宝はビール事業から完全に手を引いた。
宝の京都工場を買収したのは麒麟である。買収価格は34億円。宝からは久木田取締役、麒麟からは鈴木哲夫、山内正治両常務が出席し、京都工場の引き渡し調印が行われた。麒麟は同日、「京都工場建設事業所」を設立した。所長には、名古屋工場の加太孝男副長が就任。総勢20人という陣容である。
麒麟は6月下旬から、同地に担当の社員を派遣していたが、7月末までに基礎的な改修計画をまとめ、8月1日から改築工事に着手する。宝の京都ビール工場の譲渡が決まったのは4月8日であった。
今年のビール夏の陣は“宝落城”というショッキングなニュースでスタートを切った。今年は荒れる――、これが大方の業界人の一致した観測であった。確かに、ここ1~2年、ビール業界には芳しい材料がなかった。
ビールの需要は、65、66年と2年間伸び悩み状態が続いた。その間、出荷が伸びたのは麒麟1社。そのほかの会社は横ばいか、大幅な出荷減に見舞われた。この需要不振が、“宝落城”の一つの大きな原因になったのであるが、同時に昨年のビールのシーズン時には、サッポロ、朝日の合併という“前線”が停滞し、販売戦線が大きく動揺した。
4月ごろまでのビール業界は、低迷ムードに包まれていた。ところが、5月に入ると、出荷が予想を上回る大幅な伸びを見せ始めた。最近の出荷状況については後で触れるが、各社とも手持ちの在庫をほとんど一掃してしまった。ビール工場は目下、フル操業。それでも、生産が間に合わない状況である。
ある販売業者は「宝さんは、惜しいことをした。あと1年ビールを売り続けていれば……。いまとなっては、死んだ子の年を数えるようなものだが……」と語っている。考えてみれば、皮肉なことである。しかし、宝がビール部門の分離を決めた翌月の5月から、ビールの需要は大幅に回復した。本格的なシーズンに入って、ビール各社は、目下、出荷に大わらわである。
67年1~4月のビール各社の出荷量は合計56万1200キロリットル、前年同期に対し6.7%の増加という状況であった。ここまではあまりパッとしない成績であったが、5月に入ると出荷が大幅に伸び始めた。5、6月の出荷を前年同期と比べると、次の通り。
1967年1~4月… 561,161キロリットル 6.7%
5月………………205,149キロリットル 9.2%
6月………………334,660キロリットル 25.1%
5月の出荷は前年同期に対し9.2%増、6月は25.1%の伸びを記録した。その結果、67年1~6月の出荷量は合計110万1500キロリットルとなり、前年同期に対する伸び率は久々に10%の大台に乗せ、12.3%となった。
 「ダイヤモンド」1967年7月17日号
「ダイヤモンド」1967年7月17日号
今年は、春の“ビールスト”が例年になく長びいた。その影響が出てきたこともあるが、シーズン入りと同時に需要が急増したため、各社ともビールの生産が間に合わなくなった。
麒麟は4月から、サッポロ、朝日も6月上旬から、それぞれ割り当て出荷に切り替えた。麒麟は例年、夏になるとビールが足らなくなり、割り当て出荷を行っていた。しかし、3社がそろって出荷規制に踏み切ったのは、61年以来6年ぶりのことである。
ここへきてビールの需要が大幅に伸びてきたのは、5月以降雨が少なく高温が続いたこと、もう一つは、景気が上向いてきたためである。ビールの売れ行きは天候と、景気の動向に大きく左右される。65、66年のビール出荷が完全な伸び悩みに終わったのも、不況と天候不順のダブルパンチを受けたためである。
65年のビール出荷は、その前の今年に比べ0.03%減、66年は6.5%の増加にとどまった。65、66年の両年をならしてみると、出荷はその前に比べ、ほとんど増えなかった。
麒麟の高橋朝次郎専務は「ビールの売れ行きは、何といっても、天候に左右される。特に、シーズン時の天候が決め手となる。その点今年は恵まれている。この調子でいけば、今年はビールの当たり年になるだろう」と語っている。今年は5、6月と月を追って出荷が伸びている。久々の好天で、業者の表情はいかにも明るい。
今年のビール界には、もう一つの特徴が見られる。それは新製品が相次いで登場したこと、工場の増設、新設計画が活発化してきたことである。外国会社と業務提携した会社、技術輸出に成功した会社もある。