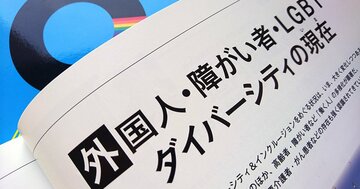障がい者が社会復帰するための“働く場”を作る挑戦
「パラリンピック東京大会」に参加した日本人選手は、欧米と日本の障がい者を取り巻く環境の歴然とした違いを見せつけられることになった。欧米の選手たちは自立して仕事をして家族を養っている者が多く、競技に参加した後には銀座へこぞって買い物に出かける余裕があった。ところが日本では障がい者に就労の機会はなく、家族の世話になるしか生活する術がなかった。
 社会福祉法人 太陽の家(別府市亀川) 大分県別府市大字内竈(うちかまど)1393番2 1965年創設。閑静な住宅地のなか、約2万6千平方メートルの敷地内に、共同出資会社や協力企業の工場・事業所、A型事業所、作業訓練場、宿舎や食堂、スポーツ施設などがある。JR亀川駅より徒歩5分。 写真提供:社会福祉法人 太陽の家
社会福祉法人 太陽の家(別府市亀川) 大分県別府市大字内竈(うちかまど)1393番2 1965年創設。閑静な住宅地のなか、約2万6千平方メートルの敷地内に、共同出資会社や協力企業の工場・事業所、A型事業所、作業訓練場、宿舎や食堂、スポーツ施設などがある。JR亀川駅より徒歩5分。 写真提供:社会福祉法人 太陽の家
スポーツを用いたリハビリテーションを導入することで障がい者の健康を回復させることに注力していた中村医師だったが、障がい者が社会復帰するための環境がないことに気づいたのである。
結果、中村医師は、彼らが社会復帰するための“働く場”を作るという新たな挑戦を始めることになった。
中村医師が勤務していた国立別府病院は、下肢に麻痺がある脊髄損傷患者を多く抱えていた。そこで、彼らの残存機能を活かして就労できる場を作ろうと、昭和40年10月に「太陽の家」を創設――「No Charity, but a Chance!(保護より機会を)」をモットーに掲げ、自ら社会に溶け込む意志力と実力を育てなければならないと、障がい者に対して叱咤激励をしたという。しかし、当初は別府の特産品である竹工芸や木工など、利益の少ない仕事しかなく、わずかな工賃しか払えない状態が続き、障がい者の自立はほど遠いという現実に直面した。