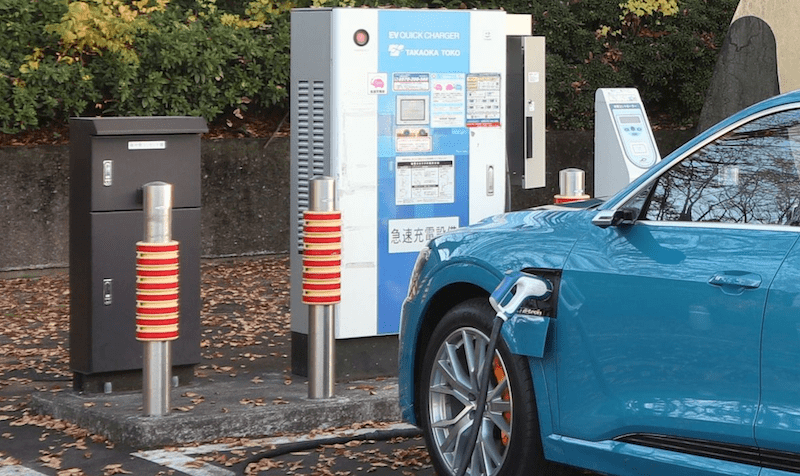 Photo by Shinji Nakao
Photo by Shinji Nakao
2020年は、フォルクスワーゲン、ダイムラー、アウディ、ポルシェ、プジョー、シトロエンなど主だった輸入車ブランドが軒並み電気自動車(EV)を日本市場にも投入してきた。2020年末には、自工会会長豊田章男氏が急激なEV化に対する警鐘ならしたものの、この傾向は21年も続くと見られ、マツダMX-30、日産アリアと軽EV(iMK)、さらにトヨタ・スバル共同開発によるSUVの発売・発表が続く予定だ。購入補助金の見直しも議論されており、国産EV市場の活性化が期待されている。
EV選択肢が増えることで、EVやPHEVを購入候補にする人を見かけるようになった。筆者の周辺でもEV購入を検討している人がいる一方でEVに懐疑的な意見があるのも事実だ。EVはエコではない、電力が足りなくなる、充電が面倒だ、雪や水没に弱い、といったものだ。だが、その疑問の多くは古い情報による誤解や誤認と言える。代表的なものをいくつか検証しつつ、EVの購入ポイントについてまとめてみたい。(ITジャーナリスト・ライター 中尾真二)
EVは高くてもとがとれない?
現状、EVはガソリン車より車両本体価格が高い。EVはガソリン代がかからないとはいえ、ガソリン代と電気代の差額で本体価格の元がいつとれるのか、といった声も聞く。これについては、ガソリン車とEVの本体価格の差を、燃料代削減額で償却していくという話であれば、すでに多く普及しているハイブリッド車(HV)でも、ゼロにするのは難しい。
例えば人気のトヨタRAV4は、ガソリン車とHVの設定がある。燃費はそれぞれ15.8km/Lと21.4km/Lだ。価格差は60万円(車両本体価格)。年間1万キロ走るとして、HVで節約できるガソリンの量は約166Lだ。ガソリン単価を130円とすると年間2万1580円の節約になる。60万円の差額を償却するには約27年かかり、28年目の途中から「利益」がでることになる。年間5000キロくらいの走行距離ならば、55年かかる。
じつは、この手の減価償却もどきの計算は無意味である。RAV4の例でいうと、28年目から出るという「利益」とは何なのか。28年目になったところで支払った金額が戻ってくるわけではない。それより、節約分は毎月のフリーキャッシュになると考えたほうがいい。とくにEVは、充電の電気代が増えてもガソリン代を超えることはほぼない。
平均的なEVの電費は6km/kWhとされる。年間1万キロ走る(毎月800キロ以上となるのでかなりのヘビーユーザーだが)場合の電気代を単純計算してみると、およそ4万5000円(従量電灯B:120kWh~300kWhの単価27円/kWh・基礎契約料除く)となる。HVを25km/Lの燃費としても5万円を超える。
旅客運送業以外、EVが従来車に比べて何らかの金銭的な利益をもたらすことはまずない。購入代金を回収したいという考えがあるならば、自動車、とりわけEVなどは買わないほうがよい。タクシーや鉄道のほうが確実に安上がりだ。







