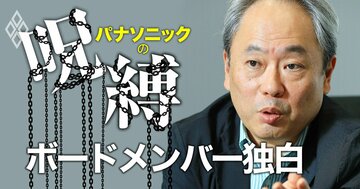知識以上に大事なことは
「知識を活用する力」
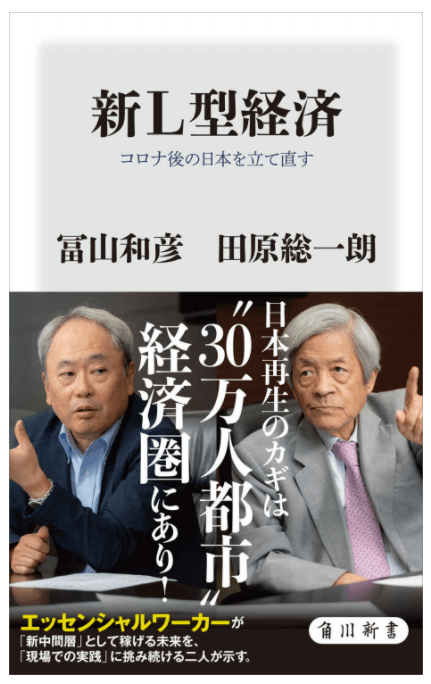 冨山和彦、田原総一朗『新L型経済 コロナ後の日本を立て直す』 (KADOKAWA)
冨山和彦、田原総一朗『新L型経済 コロナ後の日本を立て直す』 (KADOKAWA)
田原 大学の話が出たところでね、少し教育の話をしたい。今の時代は正解のない問題に自分なりの答えを出さないといけない。そこで昔、宮沢喜一が首相の時に聞いた話を思い出した。先進国首脳会議、あるいは国連や国際会議に出ると、日本の政治家は発言しないというより、できないというんだ。宮沢に聞いた。「これは英語ができないからか」「違う、教育が悪いんだ」――。
宮沢は英語も堪能で、戦後のタフな交渉を乗り切った。宮沢は場慣れもしていたから問題ないけど、他の政治家は違ったんだね。小学校から高校まで、正解のある問題、正解を答えないと怒られる。ところが、G7のような会議で話される議題には正解がない、正解が分からないから議論している。今回のコロナ禍もそう。答えが出ないという場面が日本の政治家は苦手だ。
冨山 実際に社会に出ると、議論しているのは正解のないことしかないので、できれば中学、少なくとも高校くらいからは、正解の出ない問題に重心を置くべきなんですね。
知識は大事なんですが、それ以上に大事なことは知識を活用する力です。世の中で大事なことは何か、今何が起きているのか、それが、これからのあなたの人生にどんな影響を与えるのか、そこで自分はどう生きていくのか……こうしたことを考える力を身に付けてもらう教育を行うべきです。
ビジネスでも、正解のない世界に出て行かないといけないのに、正解ありきの世界の勝ち組である試験優等生タイプは間違えることを恐れ、重要な決断ほど先送り、すなわち決断しない、試験を受けないことを選択します。ですが、間違えるか間違えないかなんて、やってみないと分からないんですよ。だって、今は正解でも明日にはイノベーションで新しいゲームに変わってしまう時代なわけですから。
田原 本当ならば、世の中が求めているのはイノベーションで、イノベーションを支えるのは創造力だね。
冨山 たとえば東大の数学の試験問題であっても、出題者が想定していない解き方をする人が、数年に一人くらいの割合で、出てくるといいます。そういう学生には5倍くらい価値があるんですが、試験ではどんなダサい解き方でも正解は正解で満点は変わりません。ここを変えたら良いのにと思います。