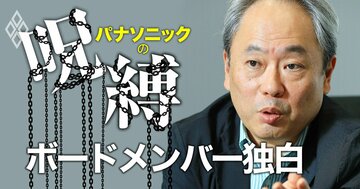おっさんサラリーマンによる
「ニッポンのカイシャ」モデルと決別する端的な方法
冨山 今や出産、子育てなどのライフイベントも実は経営者としては重要な経験の多様性になります。むしろそれを加点要素にすべきです。年功の裏返しで昇進の年齢上限みたいな頭があるからこれまた障害になるんです。
「日本人のおっさんサラリーマンの、おっさんサラリーマンによる、おっさんサラリーマンのためのニッポンのカイシャ」というモデルと決別する最も端的な方法は、思い切り女性活躍を進めること。女性が活躍できていないような会社であれば、なおさら彼女たちが働きやすいようにルールをガンガン整備すべきです。
田原 そうか、中途半端な点数評価なんか意味ない。
冨山 そうです。経営者層の外国からの招聘ももっと当たり前にやるべきで、部長レベルでもいいし執行役員でもいいのですが、そこで外の血を入れること。女性比率も意識的に上げる。そうするとトップの候補がすごく多様になりますから。そのプールの中から、またこれが社内の視点だけだと必ず偏るので、経営経験をした社外取締役も入れて、事業を任せながら選ぶという方向に変えたほうがいいですね。
G型産業もこれからデジタル革命の主戦場はリアルでシリアスな領域ですから、日本企業が長年、培ってきた現場力、改善改良力、集団的オペレーション力はものを言うようになります。しかしそれだけの「片利き経営」では勝負にならないこともはっきりしているんですから、ここは古い日本的経営モデルに別れを告げ、「両利き経営」の会社、真に多様な人材がそれぞれに違った働き方、生き方で活躍している会社へと思い切り会社改造、CX、憲法大改正をしていってもらいたいと思います。
彼らが世界で成功し、かつての貿易収支ではなく、配当や利子、ライセンス料といった所得収支で外貨を稼いでくれることは、インバウンドなどのサービス収支と並んで、小資源国日本の持続性のために重要ですから。
ローカル型企業のデジタル化は
まずは「見える化」から手をつける
田原 G型企業の経営改革方針はわかった。ではL型企業はどうしたらいいのか。
冨山 これも明確で、封建的な会社をいかに現代化するかがまずは大切です。繰り返しになりますが、そのために新しい血も入れて経営人材を強化することが何よりも大事ということになります。
私は危機の時には、中小企業のオーナー創業者モデル、オーナー経営モデルは強いと思っているんです。トップダウンもできるし、決断の影響力が大企業よりもすぐに出ると。
たとえば老舗の旅館やホテル、食関連のビジネスでは、下手に大企業型にするよりも事業の持続性が高い場合があります。それは経営理念も継続するし、長期的な経営や修繕計画もできるし、企業文化も変わらずに継承される場合が多いからです。
ですが、その半面、非常に封建的で外部が経営にかかわる機会を奪い、社内が停滞する可能性と隣り合わせです。これでは、やっぱりうまくいきません。実際に私たちが企業再建にかかわったとき、地方の再生案件はほとんどが創業から三代目以降の会社でした。当たり前ですが、創業一族から何代も優秀な経営者が出続けるなんてほとんどありません。
田原 そんな企業体質でデジタル化はできるんだろうか。
冨山 デジタル化というと難しく聞こえるかもしれませんが、まず多くの場合は現場の「見える化」にあります。管理会計を厳密にやって、どこにコストがかかっているか、どこに無駄があるかを数字で把握していく。そのために最初はエクセルのような表計算で実態把握と分析を行う。PDCA手法が練れてきたら会計ソフトを導入して、自動的に全体でわかるようにする。これも立派なデジタル化です。
バスでいえばたとえば路線別収支を出そうと思ったら、一番簡単なのは大都市と同じようにICカードを導入すればいいんです。
最初は田舎のお年寄りだからできない、そんなところにお金を使っても収入が増えるわけではない、といった反対意見も出てくるんですが、そんなことはありません。都バスでお年寄りだからICカードが使えないなんて話は聞いたことがないですよね。結局、顧客利便性は増すし、お客さんがどの時間のどの停留所からどこまで利用しているかが分かるので、ダイヤ改正や路線改正の大事な情報になるのです。ICカード導入も立派なデジタル化の投資です。
事故が多い運転手とそうではない運転手の違いを突き止めるために、車内が映るドライブレコーダーをつける。これも立派なデジタル投資で、運転がうまい運転手のスキル、発進時や停止時にお客さんの転倒事故を防ぐためにどんな工夫をしているかをみんなが共有することで、事故率は劇的に低下します。
デジタル化なんて難しいという話がすぐ出るのですが、要は現場で役に立つことを技術でやるということでしかないんです。