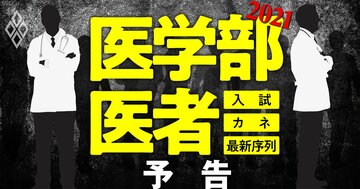『週刊ダイヤモンド』10月9日号の第一特集は「医学部&医者2021」です。医者の「安定、高収入、高ステータス」というイメージにより、1990年頃以降過熱の一方だった医学部入試。しかし、ここ数年は高偏差値校の男子生徒による医学部離れの兆しが徐々に見え始めていました。それは、東大理三への合格者数トップを走ってきた西の名門、灘高校も例外ではありません。本特集では、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的流行)のインパクト、そして今後の医学部入試の動向&受験対策を徹底解説します。
「灘→東大理三」の黄金ルートが崩壊か?
三男一女を理三に入れた佐藤ママも憂う異変
 灘中学・高校の校舎。出身者には医者だけでなく、各界の著名人も多い Photo by Atsuko Shomura
灘中学・高校の校舎。出身者には医者だけでなく、各界の著名人も多い Photo by Atsuko Shomura
長年、医学部の最難関、東京大学理科三類(以下、理三)への合格者数が最多の高校といえば灘(兵庫県)だった。2013年には27人(以下、合格者数は総数)が合格。当時の定員は100人だったため、なんと合格者の4人に1人が灘出身者だった。医療界でも、「灘→理三」は一種のブランドになっている。
しかし、19年には21人が合格したものの20年は14人、21年は12人だった。他校に比べて灘高生の学力が落ちたわけではなく、同校によれば理三の志望者自体が減ったという。
「三男が理三を受験した13年は、27人が合格しました。そのうち21人が現役で、保護者の間では『花の65回生』と呼んでいます。三男の合格発表では、親しいお母さんの息子さんたちがみんな合格していたので、『良かったね』と喜び合い、ちょっと騒ぎ過ぎたくらいです。昨年は全国トップとはいえ14人、今年は12人(2位)なので、寂しいですね」
そう話すのは、3人の息子全員が灘から理三に進学した佐藤亮子さんだ。