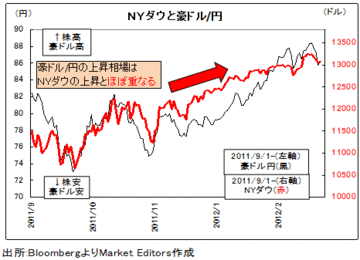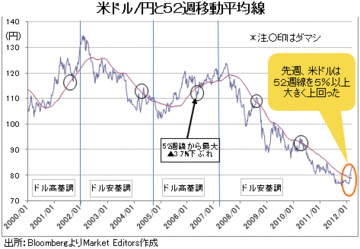5日発表された米11月雇用統計では、何と50万人超もの雇用激減となりました。実に34年ぶりの大幅な雇用減だということです。ところがこの日、米株と米金利は上昇し、そしてドルも対円で反発に転じました。なぜでしょうか?
前回のレポートでも書いたように、相場が短期的に下がり過ぎで、言い換えれば悪材料が相場的には織り込まれ過ぎている可能性があったからではないでしょうか。
米長期金利は「異常に下がり過ぎ」だった
下図は、米長期金利(10年債利回り)の長期移動平均線=5年線からのかい離率を見たものです。これを見ると、過去30年間で、米長期金利がもっとも5年線を下回ったケースでも、かい離率は1986年の40%弱であり、40%を大きく下回ったことはないことがわかります(数値は月末終値)。
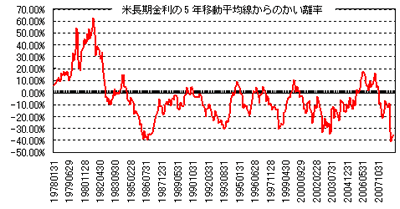
そんな米長期金利は、12月に入ってから3%を大きく下回り、4日には2.55%まで低下しました。5年線は、11月末現在で4.3%程度ですから、それを40%以上も下回り始めたことになるわけです。これは、少なくともこの「30年の常識」からすると、米金利が異常に下がり過ぎているということになるでしょう。
こういった中で、5日、34年ぶりの「悪い雇用統計」となったわけです。そして、そんな結果にもかかわらず、米長期金利は2.7%へ急反発となりました。その中で、米長期金利の5年線からのかい離率は、マイナス40%から35%程度に縮小に向かいました。
これまで見てきたことからすると、さすがに「30年の常識」から見て、異常な金利下がり過ぎとなっていたことの修正が入ったと考えるのが、もっとも辻褄の合うところではないでしょうか。
米長期金利で決まってきたドル/円相場
ところで、下図は、前回のレポートでも紹介したドル(対円相場)と米長期金利のグラフを重ねたものですが、両者は過去2年以上、ほぼ重なり合って推移してきたことがわかると思います。
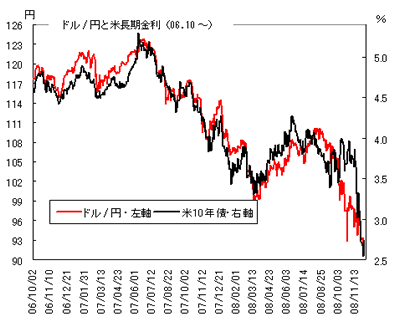
この関係がこの先も続くなら、ドルの行方は、米金利次第であり、その米金利がこれまで見てきたように「30年の常識」から見て下がり過ぎなら、ドルも下がり過ぎの可能性があることになります。
そして、5日の雇用統計発表後、米金利が下がり過ぎの修正により反発に転じたことで、それと相関性の高いドルが対円で反発に転じたということになるでしょう。
私はここで、相関関係の高いドルと米金利が「下がり過ぎ」と書きましたが、米金利は5年という長期移動平均線から見て下がり過ぎ圏に入っているのに対し、ドルの場合は、前回のレポートでも書いたように、あくまで短期的な「下がり過ぎ」の可能性だと考えています。
ここから言えることは、この2年以上続いてきたドルと米金利の相関関係も、この先ずっと続くのではなく、微妙にずれていく可能性があるということです。
なぜ「利下げでもユーロ高」なのか?
いずれにしても、この「短期」か「中長期」かの区別を認識することは非常に大事なことだと思います。
たとえば、先週はECBなど多くの中央銀行で大幅な利下げが行われました。しかし、特にユーロは、利下げと前後して、むしろこれまでのところ反発の動きになっています。こういったことを考える上でも、「短期」と「中長期」を区別する必要があると思います。