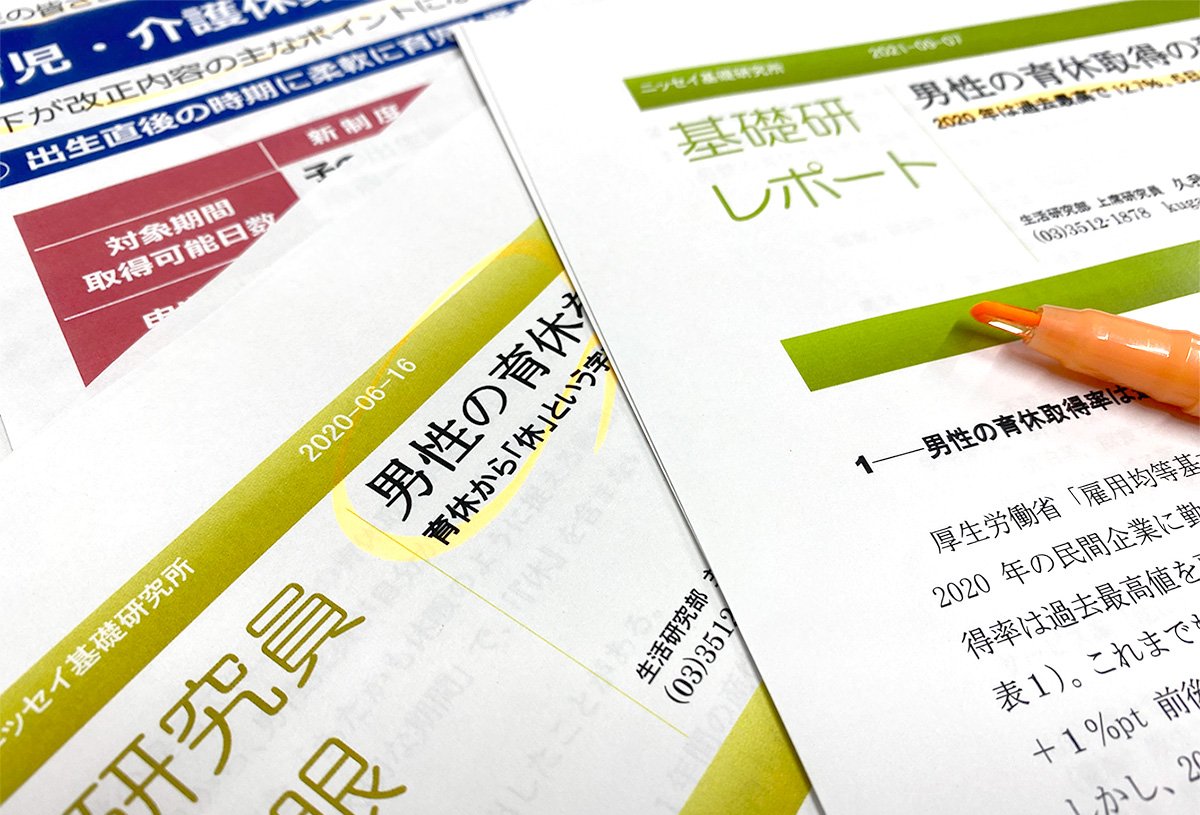
「“1割(10%)の壁”は高い」と言われ続けた男性の育児休業取得率が、昨年2020年の調査*1 でその壁を越え、過去最高数値を記録した。政府の進める働き方改革が企業に浸透しつつあること、また、コロナ禍によって多くのビジネスパーソンが仕事と家庭のバランスを顧みるようになったことなどがその要因だろう。また、今年2021年6月には「育児・介護休業法」が改正され、「男性育休」を取り巻く状況は大きく変化しているようにも思えるが、育休取得を歓迎しない職場の雰囲気や取得する本人のうしろめたさ、平均取得日数の短さなど、課題は多いようだ。「男性育休」についての論考がある、ニッセイ基礎研究所の久我尚子さんにお話をうかがった。(フリーライター 棚澤明子、ダイヤモンド社 人材開発編集部)
*1 厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査」(令和3年7月公表)データより
企業・本人の「男性育休」取得におけるメリットは?
男性の育児休業(以下、育休)取得率が、これまでハードルとなっていた「1割(10%)の壁」を越えたことは大きな前進だが、「2025年までに30%の達成」という政府が掲げる数値目標*2 には遠く及ばず、(男性の)育休取得日数の3割強が「5日以内」という行政のデータもある。男性が育休を取得しづらいという職場の実態、「取れるのに取らない」理由はどこにあるのだろうか?
*2 内閣府「少子化社会対策大綱」(令和2年5月29日閣議決定)より
久我 そもそも、日本には、子育ては女性の役割だという価値観が根強く、男性が育休を取るという習慣がまだ根付いていません。「男性である自分が育休を希望し、取得すると、周囲から否定的な目で見られたり、仕事の評価が下がったりするのではないか」という男性本人の懸念、また、そう思わせてしまう職場の雰囲気こそが取得率の伸びない原因でしょう。人手不足や仕事の属人化が常態化した職場では、「仕事に穴をあけて、周囲に迷惑をかけるのは申し訳ない」と自分であきらめる人も少なくありません。“取得日数5日以内が3割強”という数字は、「夏期休暇と同じ5日程度なら周囲に迷惑もかけず、評価にも影響はないだろう」と考える方が多いことの表れだと思います。国の制度の整備と並行して、企業各社のそうした社内の雰囲気を変えていくことも重要です。
「男性育休」に対するネガティブな空気を変えていくためには、そのメリットを明確にする必要があるだろう。たとえば、夫が積極的に育児参加することによって、第2子以降の出生率が上昇するという調査データがある*3 。男性の育休取得は少子化対策としても期待できるのだ。また、夫の家事・育児時間が長いほど、産前産後の妻の就業継続率が上昇するという数字もある*4 。妻の仕事復帰は世帯収入の向上、消費の活性化に繋がることから、日本経済の底上げにもなり得る。このように、男性の育休取得は社会全体においてメリットがあるが、人手不足に悩む中小企業ではおよそ7割が義務化に反対する*5 など、「男性育休」に対して否定的な側面もある。
*3 内閣府「令和元年版少子化社会対策白書」より
*4 厚生労働省「第13回21世紀成年者縦断調査」より
*5 日本商工会議所・東京商工会議所「多様な人材の活躍に関する調査」の集計結果より(調査期間:2020年7月16日~8月7日)
久我 いま、多くの企業が強く意識しているのは、新卒をはじめとした若くて優秀な人材の確保です。そして、その対象である、昨今の若い方が求めているのは、「ワークライフバランス」と言われるような、私生活とのバランスを大切にした働き方です。男女問わず、就職活動をしている学生の多くは、女性活躍の指標となる「えるぼし認定」の有無をチェックしていますし、実際、若い男性就労者の間では育休取得の意向が年々高まっています。企業が若手の人材を確保しようと思えば、ライスステージに応じた働きやすさに配慮することはもはや常識です。目先の労働力確保のために男性の育休取得に否定的になるよりも、「男性育休」の取得率を上げていく方が若い世代からの好感度は増すでしょう。

久我尚子 (くが なおこ)
ニッセイ基礎研究所 上席研究員
2001年、早稲田大学大学院理工学研究科修了(工学修士)、同年4月、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社。映像配信サービスのマーケティングなどに従事。2007年、独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)。2007年、東京工業大学大学院社会理工学研究科修了(学術修士)。2009年、同イノベーションマネジメント研究科修了(技術経営修士)。2010年、ニッセイ基礎研究所入社。2016年、主任研究員、2021年7月より現職。専門は消費者行動、心理統計。統計から、女性や若者などを中心に消費行動や価値観の変化のほか、背景にある働き方や結婚、出産など暮らしにまつわる変化を読み解いている。内閣府「統計委員会」専門委員および臨時委員、総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員、東京都「東京都政策連携団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員などを歴任。著書に「若者は本当にお金がないのか?~統計データが語る意外な真実」(光文社新書)など。









