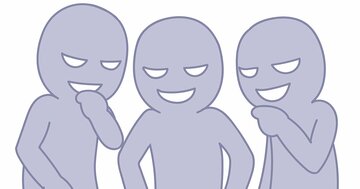「真剣さ」が短所になってしまう生きづらさ
何言ってるの、この人。
私は、自分を認めてくれる人を求めていた。私がこれまでに考えてきたもやもやに、興味を持ってくれる人を求めていた。そして彼はそういう人になってくれると信じていた。なぜなら、彼は私のことを本気で好きていてくれていると思っていたからだ。それが私の求めていた「好き」の形だった。本当に相手を好きなら、相手を理解しようとする。たとえすぐには理解できなくとも、共感もできなくとも、相手がそういう考え方をするのだと、理解しようと試みる。相手を知ろうとする。たとえ自分と相手の価値観が大きく異なっていても、その違いこそ、楽しもうとする。自分と相手の差を、男と女の差を、楽しむ。そうやって知ろうとする気持ちこそが愛だと思っていた。
だから私は彼を知ろうとしたし、彼にも自分を知って欲しかった。いや、知ろうとして欲しかった。興味を持って欲しかった。彼とはそういう関係になれると信じて、ずっと付き合っていた。でも、蓋をあければ、彼にとっては私のそういう恋愛にたいする「真剣さ」すらも、「変」だったのだ。自分が求めている恋愛はこういうこと。こういう風になりたい。こういう考え方が好き。価値観の交換が好き。自分の気持ちを深く深くほりさげていくことは、私にとっては当たり前だった。でも彼にとっては当たり前じゃなかった。私が一番重きを置いていて、一番の長所だと思っていた部分を、彼はあっさり「変なやつ」だと否定した。彼には、私が何事にも真剣な姿勢そのものが、「面倒」で、うざかったのだ。彼はもっと気楽に、何も考えずに付き合える関係を望んでいたのだ。
もう女のプライドも人としての矜持も、見栄も、自尊心も、何もかもが一気に崩壊した。これは現実? こんなに辛いことって起こるの? しかもそういうときに限ってどうして視界に入ってきてしまうんだろうか、枕元にある、ホテルに備え付けのコンドームの入った箱が、より一層私を虚しくさせた。
「俺、本当なら、人の話はあんまりききたくないんだ。俺がずっと話してて、彼女にはきいてもらうだけでよかった。彼女にそういう……なんていうの、哲学的な話とか求めてなかったし、ぶっちゃけ、紗生が言ってることの意味も、よくわからなかった。そういうことって考えても、無駄だと思ったし。なんでそんなことに時間使ってるんだろうと思ってた、ずっと。だって何の役にもたたないじゃん」
私の目を見ずに、空中の一点をただぼんやり見ながら言う彼を、私は信じられないような気持ちで見ていた。頭が真っ白だった。いろいろな不満が浮かび、頭で考える間も無く、冷静になることもなく、そのまま彼に向かって、私は暴言をぼんぼん吐き出した。どうして今さらそんなこと言うの! どうして今さらそんなに正直になるの! ずっと自分のことよく見せようと見栄張ってたくせに、ねえ! どうしてそう思ってたならさっさと言ってくれなかったの!? どうして! どうしてどうしてどうして! おかしいでしょ! 男として、人としておかしいよ。だめだよ! ねえ。ひどいと思わない!? 思うよね? 私が言ってること、間違ってる!? ねえ!
さっき受けたグレネードランチャーの反撃とばかりに、どかーん、ぐわっしゃーん、と暴言の手榴弾を休む暇なく彼に投げつける。彼はものすごい勢いで私に身体中を爆破され、焼き尽くされていった。答えろ、おらー! どうなんだよ、え!? と、メイクも涙でどろどろに落ち、眉間にしわを寄せ、それこそ烈火のごとく怒り狂う私の形相は、それはそれはひどいものだっただろう。彼も相当に傷ついてることは想像にかたくなかったが、私は止める方法を全く知らなかった。というか、私をこれだけ傷つけたのだからお前も同じ分だけ傷つくべきである、と本気で思っていた。
明らかに言い過ぎな部分もあった。だが彼は「ごめん」としか言わなかった。言い訳をしようとすらしなかった。自分が悪者になろうとし続けた。でもそれが私にとってはかえってしゃくだった。常にプライドを守り続け、他人の評価をいつも気にする彼が最後だけ正直に、悪者になろうとしているのが許せなかった。悪者になろうとするその潔さみたいなものが、私と別れたいのだという意思をよりはっきりと強調している気がして、ますます辛くなった。ひとりで彼をせめまくり、自分は悪くない、お前が悪いと主張し続ける私のほうが、よっぽど「悪者」みたいだった。でも私は止めることができなかった。最後まで綺麗な思い出のまま別れるなんて器用なことは、不可能だった。
でも私の本当にみっともないのは、それだけ暴言をあびせておきながら、結局やっぱり彼が好きで、喧嘩して別れ話が落ち着いたあと、仕方なく二人で広いベッドの端と端に寝ているうちに、情が蘇ってしまって、「ねえ、やっぱりやり直せない?」としおらしく言ってしまったことである。ああなんと情けない。ダサい。ダサすぎる。典型的なダメ女である。感情にまかせてギャーッと騒いでおきながら、冷静になるとやっぱり彼が惜しいのである。でも結局は後の祭り。「いや、もう完全に好きじゃなくなった」と冷めた声で彼に言われ、私は何度も彼の背中を振り返り、何度も泣き、当然のように手に入っていた彼の背中のぬくもりにもう二度とふれられない辛さをかみしめながら、一睡もできないまま朝を迎えたのである。彼は大あくびをかいて寝ていた。死ぬほど腹が立った。彼とはもちろん、それ以来、まともに顔を合わせることはなかった。