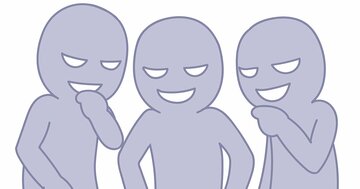深夜2時、ラブホテルのベッドの上で振られた日
たとえば、どうして人は見栄を張ってしまうのかとか。どうして嘘をついてしまうのかとか。みんなが何を考えていて、私とはどう違うのかとか。友達に悪口を言われていると知ったとき、自分は何にたいして怒りを感じているのかとか。自分のどこがどうだめなのか。私は何にたいして罪悪感を覚え、何を大事に生きていきたいと思っているのか。何が正義で何が悪なのか。人間性とは一体何なのか。人間は死んだらどこへ行くのか。生きている意味はあるのか。この世界で、必要とされる人というのは、どういう人なのか。
そして、もやもやしている自分の胸の奥のよくわからない何かは、どんな感情や欲求から成り立っているのだろう。
そういうことをただとりとめもなく、よく考えていた。別に理由なんかない。何かに役立てるつもりもなかった。ただ私にとっては、そういうことを考えるのが日常だった。
でもみんながみんな、そういうことを考えるわけではないのだということに勘付き始めたのは、中学の頃だった。
私が自分の考えていることを友達に話すと、「紗生の言ってることってよくわかんない」とつまらなそうに言われた。それはすなわち「つまんない」というのと同義だった。中学生の彼女たちにとっては、恋愛の話や、部活の先輩との上下関係の話や、嫌われている教師の悪口の方が、ずっと面白いのだ。ああ本当に興味がないんだなと思った。でも私は不思議だった。どうしてそういうことを考えずにいられるんだろうと思った。だったらいったい何を考えているんだ。何も考えていないのか、それとも。
その違和感は高校に入学してからも続き、不満はどんどんふりつもっていった。自分が考えているもやもやを共有して、一緒にもやもやしてくれるような友達がほしかった。誰かはいるはずだ、と思った。きっと自分の感情を理解してくれる人がいるはずだと。世界のどこかに。だって、この世は広いんだから。
人の多い大学なら、そういう人もいるだろうと思って、死に物ぐるいで勉強して、早稲田に入学した。自分のいるべき場所はここじゃない。バカなくらい純粋にそう信じて。
自分と同じ、もっと「わかる人」がたくさんいる大学にはたしかに、頭のいい人や、並々ならぬ知識量を持っている人がたくさんいた。バケモノかと思うくらい頭が切れる人もいたし、リーダーシップを発揮して次々に人を引き寄せる人もいた。自分とは違う人間と会うのは、面白かった。世界が広がったと思った。私が求めていたのはこいういうことだったのだと思った。何も考えていないような、ただ日常をぼーっとしながら生きる人なんかと話すんじゃなくて、ディープなことを語り合える、相手。もっと学術的な何かを求めていたのだ。人生にたいする真剣さを求めていた。
いろいろな人がいる大学では、私も自分が考えていることを以前よりもたくさん話すことができた。うんうん、と話をきいてくれる人がいた。やっぱり早稲田にきて正解だったと私は確信した。自分の居場所は中学や高校よりもここだったんだと。みんなが私を認めてくれる。すごいと言ってくれる。何言ってるのかわかんないじゃなくて、面白い話だと言ってくれる。興味を持ってくれる。私は私のままでいてもいいんだ、と思った。ここなら。
けれど大学二年のときに半年くらい付き合った彼氏に別れ際、こう言われた。
「なんでそういう小難しいことについて真剣に考えてるのかわからなかったし、そういうことを話したいと思ったこともなかった。そんなこと考えてどうするの? 意味あるの? すごいやつなのか、ただの変なやつなのかってことがずっとわからなかった」
全・否・定。ずがーん、どがーん。グレネードランチャーでぶっとばされたかのような(ぶっとばされたことないけど)衝撃。自分の保ってきたもの全てが、がらがらと崩れ去っていくのを感じた。
しかも最凶最悪に運の悪いことに、私がそれを言われたのは新宿のラブホテルのだだっ広いベッドの上で、しかももう終電もなくて、意味深にうすぼんやりとピンクに光る間接照明が照らす彼の申し訳なさそうな顔から発せられたその言葉を、にわかには、理解することができなかった。