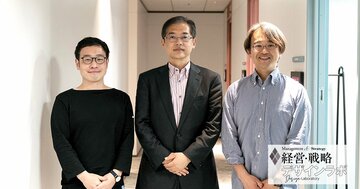プロセスに関わること自体が
すでに価値である
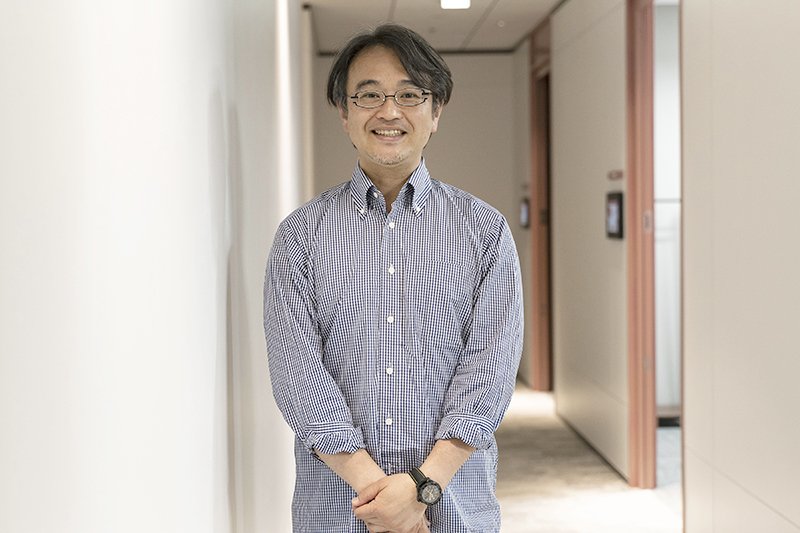 井上英之(いのうえ・ひでゆき)
井上英之(いのうえ・ひでゆき)慶應義塾大学卒業後、ジョージワシントン大学大学院に進学。外資系コンサルティング会社を経て、NPO法人ETIC.に参画。若い社会起業家の育成・輩出に取り組む。2003年、社会起業向け投資団体「ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京」を設立。2005年より、慶應義塾大学SFCにて、社会起業に関わる実務と理論を合わせた授業群を開発。2009年、世界経済フォーラム「Young Global Leader」に選出。近年は、マインドフルネスとソーシャルイノベーションを組み合わせたリーダーシップ開発に取り組む。「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」共同発起人。Photo by Teppei Hori
感じていること、思っていることを共有できる場があれば、新しいことは生まれる。うまくいったことばかりでなく、失敗や、もやっとした感覚も共有できる、それも含めて応援されていると感じる場。
「こんなこと、やりたいと妄想しているんだ」と誰もが話すことができる、そんな場をつくれることが、大切ですよね。
「やりたいなら自分の責任で勝手にやれ」ではなくて、その応援は、自分にもつながっている。何をするにしても、それぞれの「私」があって、「私たち」があるんです。
そのため、応援フルな「ソーシャルフィールド」「リレーショナル・フィールド」を作る。そのフィールドで、目に見えない関係性をよりよくデザインし、「皆にとって大切なこと」をやりとりする。そこから、新しいアイデアや挑戦が生まれ、大きなシステムが変わり始めると思うんです。
小田理一郎(以下、小田) 本当にその通りで、私たちは「生命システム」として、自然や社会の一部です。「システム」の中で、いろいろな要素が集まって、相互作用して、一定の特性が出てくる。気づいたら人口が80億近くになっているとか、気づいたら世界中に情報が駆け巡っていて情報社会になっているとか、これはシステム的な特性ですね。
その特性の中でも、私たちはスケールやスピードを求めてしまう。でもこれは多分に西洋的な価値観で、非常に画一的なものです。もちろん、結果を出すのは大事ですが、プロセス自体がすごく大事で、こうした一方的な価値観が優勢になると、「制約」のほうが勝り、システムやテクノロジーは機能しなくなります。
でも、学習する過程で、社会関係資本や自然資本を修復し、再生していくことができる。実はそこにプロセスとして関わっていること自体が、すでに価値を作っていることになる。自分のキャパシティを広げ、人間性を培い、精神的にも身体的にも健康を取り戻すことができる。
 小田理一郎(おだ・りいちろう)
小田理一郎(おだ・りいちろう)チェンジ・エージェント代表。オレゴン大学経営学修士(MBA)修了。米国企業で10 年間、製品責任者・経営企画室長として、組織横断での業務改革・組織変革に取り組む。2005年チェンジ・エージェント社を設立。日本において、「システム思考」や「学習する組織」など、変化のための方法論の普及・実践の推進に務める。サステナビリティ、社会課題解決分野における、能力開発とプロセスデザインに関連するサービスを提供する。共訳にピーター・センゲ著『学習する組織』、著書に『「学習する組織」入門』(共に英治出版)など多数。Photo by Teppei Hori
生命システムとして、自然や社会に関わることに価値を見いだせば、システム的な効果はさらに高くなるはずですよね。
例えば、「プラスチックで作ると、こんなに安価で、何百億個と大量生産できます」と、それだけがあたかも素晴らしいことだと思わされていたけれど、ふと立ち止まって、「それが何のためにあるのか」を考える。それを使ったら、いずれ廃棄されて、海のどこかで分解されず回遊してしまう。それは本当に価値があることなのか、どうすれば価値があることができるだろうか、と。
そのテクノロジーは何のために適用するのか、誰のためにやるのか、それを誰が決めるのか? 高リターン、高効率、スピード、スケールといった指標は、近代西洋の考え方であり、それを受け売りするのではなく、日本人・東洋人は、それとは違った「価値」を持っていたはずではないのか――。
このことを、ピーターはすごく強調していましたね。その「価値」を言語化しようとすることが大事なのではないかと。
しかし、それは、スケールやスピードのように、なかなか定量化することができない。定量化できなくなった瞬間に、「これは価値ではないのではないか」と思うかもしれない。
でも、井上さんが言われたように、「何が価値なのか」、あるいは「それがどれだけ価値があることなのか」を、私たちは、リレーショナル・フィードを作り、そこで会話することで、感じることができるし、間違いなくこれは価値があることだと、確信を持てるようになる。
「そのようなことをしてもリターンがないじゃないか」と、誰かに言われるかもしれない。でも、「見えませんか、ここに価値があるじゃないですか。見てください、皆の生き生きした顔、子どもたちが未来を信じている顔を」と言ってやればいいんです。
そういうところに価値を求めていくことが、私たちがやれることではないかと思います。
――ありがとうございます。これまでのお話を踏まえて、一人一人の身の丈を超えたテクノロジーが広がったり、パンデミックなど予測不能なことが起こったりする現代において、企業や組織が「進化する条件」は、あらためて何だと思いますか?