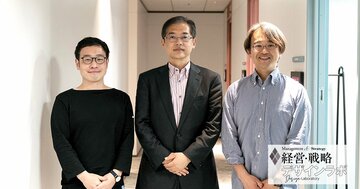進化し続ける組織の条件(1)
共有し振り返ることができる環境を組織内外で育む
 福谷彰鴻(ふくたに・あきひろ)
福谷彰鴻(ふくたに・あきひろ)システム思考教育家。米国でMBA取得後、欧州系ヘルスケア企業等を経て、ボストンのSoL(組織学習協会)にて、ピーター・センゲ氏の各種ワークショップの運営をサポート。10年以上にわたってセンゲに直接、師事し、継続的なメンタリングを受けている。帰国後は⽇本の教育分野における「学習する組織」及び「システム思考」のツールや考え方の導⼊に従事。国公立大学、中学高校での講義やワークショップ、教職員向け講座を多数開催し、さまざまな学習するコミュニティづくりを推進している。Photo by Teppei Hori
福谷彰鴻 「学習する組織」の背景に、次のような考え方があります。
人間は「学ぶ存在」であり、学びには「ビジョン」と「プラクティス」が必要である。しかし、学ぶことを赤ん坊に教える必要はない。生まれながらにして何かを願う存在であり、何かをやってみることで、学ぶようにできている。私たちは誰もが「学ぶ力」をあらかじめ持っている。生物として、そのようなシステムを持っているのだと。
そのような素晴らしいシステムが自分の中にすでにあるのに、多くの場合、人々は目の前の課題に反応することで精いっぱいであり、しかも、そのモチベーションは「恐怖」によって作られています。
こうした状況はまったく望ましくないことで、私たちは今一度、目の前の課題だけでなく、長期的な視点を持てるような場を作っていくことができるか、そのことを突き付けられている気がします。
井上さんから、組織の中で本当に思っていることを話せる場が大切というお話もありましたが、今、皆が願っていることは、「子どもたちを幸せにしたい」「どのような社会であるべきか」など、言葉にできることです。それを願いながら、何かやってみて、たとえうまくいかなかったとしても、振り返る。これが、「学習する組織」のコアにある考え方です。
何かを願いながら、やってみることができる。やってみたことを共有し、振り返ることができる。それが可能となる環境を組織の内外で育んでいく。そのことが、私たちが向かいたいところへ向かっていくための進化につながるのではないでしょうか。
進化し続ける組織の条件(2)
速度と強弱のバランスをデザインし直す
 Photo by Teppei Hori
Photo by Teppei Hori
井上 本当にそうですね。「私」が欲する未来に向けて、まずはやってみる。これがものすごく大きい。
そして、やってみた「結果」がとても大切な材料なんですよね。この結果を、僕たちはよく、良し悪しだけでジャッジしてしまう。でも、やってみた結果自体が、価値ある一次情報なんです。「こうやってみたけどうまくいかなかったよ」という大切な情報を共有しないのは実にもったいないことです。
つまり、この世界という複雑な迷路の中で、「こっちは行き止まりだったよ」という貴重な情報を得て戻ってきて、共有してくれる。そのおかげで皆はそこへ行かずに済むんです。
個々がやってみること、そして、やってみた結果を情報として共有し、共に学び新しい選択肢を生み出すこと。そのような関係性を醸成していくこと。それが、進化の生まれる場づくりなんだと思います。
個別の客観的な分析には、もちろん意味はあります。でも、より大きく、正直な目線や「主観」も必要です。このままでは、現状の地球や社会は続かないと皆、わかっている。今、「私」は本当は何を感じていて、どんな未来が欲しいのか。何より、その「私」のように感じている人は、自分だけはなく、一定以上の「代表性」があるはずです。この個々が感じていることが、これからの世界をつくるのではないでしょうか。
目の前にある既存のビジネスで事業をまわして収入を得つつも、常に変化し続けるために、新しい事業を生み出す必要があります。その長期の目線の材料は、今、多くの人が、もやっとしていたり、体感として感じていることに、ヒントがある。意識化しきれていないが、感じていること。そこに潜在的なニーズがある。そこにいかに耳を傾けるか。
以前から、エサレン研究所(※)で始まった、身体と気持ちをつなぐ「エサレンマッサージ」の施術をしてもらっています。皮膚感覚の伝達には、早く強く押すことで刺激できる、情報を早く伝達する神経線維と、ゆっくりと触れることで初めて動き出し、ややゆっくり伝達する神経線維があるんだそうです。そして、後者が、自律神経系や生命維持にとって、きわめて重要な役割を果たしている。
システム思考も同じで、時間をかけた取り組みをすることで、初めてスイッチが入るものがある。それこそ、体のもともと持っている免疫の力や、自己回復につながっている副交感神経系を動かしていくようなものです。
「早く強く」だけでは届かないところ、「ゆっくり丁寧に」傾聴したり耳を澄ませてみたりすることで気づく、より大きなシステムがある。私たちが必要なのは、この両方の使い方をデザインし直すことなのではないでしょうか。今、もし、すべてを「早く強く」で乗り越えようとしているのだとしたら、別のやり方に対して意識的になるときなのだと、思いました。
「体に悪いのについ間食をしてしまう」というような、「その結果を望んでいないのにもかかわらず、目先のアクションとして繰り返してしまっていること」は、さまざまなレベルで、同じパターンが起こっています。
生活習慣から、家族や職場での関係、さらには、国同士、人間と自然との関係……。世界のあちこちで、同じような構図でこのパターンが起きているとしたら、「私」の日常で起きていることは、さまざまなことの縮図で、僕たちが進化していくためのエッセンスが詰まっているかもしれません。