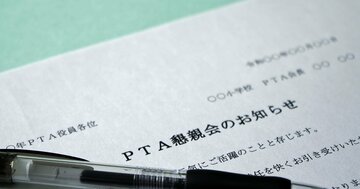日本の社会では手段が目的化しやすいのにお気づきだろうか。
今さら言うまでもないことだが、レストランでワインを嗜むのは会話を楽しむためなのに、ワインのうんちくでお客の会話を台無しにしてしまうソムリエがいる。バレンタインデーは本来女性が意中の男性に思いを伝える手段としてチョコを渡す極めて日本的な儀式に過ぎないのに、あの子にもこの子にもと大量に買い求めたり、自作のチョコをキッチンで量産したりする作業が女性たちの苦行になってしまった。
コロナ騒ぎでも、マスクの使用が必須の手段のように崇められ、一時は医療用マスクまでが不足する事態に。いずれも、手段が目的化してしまった事例だ。
次に、オンライン教育の運用を論じるにあたり、前提となる以下の2点を無視して話を進めても意味がないので、ここで触れておく。
1つは、成績上位者(喩えて言えば偏差値65程度以上)とそれ以外の子とでは、自律的な学習をやらせた場合、その効果に大きく差が出る現実がある。
学齢期から言っても、高校生には無理はないけれど、小学校低学年に自律的なオンライン学習は厳しいだろう。
2つ目は、学校にWi-Fi設備が敷かれ、家庭でも学校から配信されるオンライン学習が日常化したとしても、その中身が旧来の一斉授業スタイルだったら、最初は珍しくてもやがてはリアルな授業と同じように子どもが飽きてしまう。
だとすれば学習効果も薄い。要するにオンライン、オンラインと学校の教員に言うだけでは足りない。予算が整えばオンライン授業に切り替わるだろうが、そこでAI×ロボット時代にふさわしい進化した教育が行なわれるとは限らないのだ。むしろ、旧態依然とした教育がそのまま動画になって配信されるだけ、という姿になりがちだ。先にも指摘した通り、「一斉授業」が「デジタル一斉授業」に見た目が変わるだけだという意味だ。
つまらない授業は、オンラインに載せるともっとつまらなくなる。
オンラインコンテンツを活かせば
若い先生でも「授業力」を高められる
学校のDX化によって、スマホやタブレットという機器を思い切り教育ツールとして活用させていくのなら、若い先生の力がいかんなく発揮される。むしろ若手の能力こそが、必要とされる。教員になった時点での学力が諸先輩に比べて相対的に低かったとしても、オンライン上にあるコンテンツを活かして、自分の授業力を高めていくことは若い先生ほどできるはずだ。
自分が生身かつ独りで何もかも教えるのではなく、自分自身を「○○先生」というキャラとして捉え、ネットワークで教える方法を確立すればいい。自分の背後に、何人ものオンライン先生を味方につけ、デジタルの教材にも精通した「ネットワーク先生」を演じること。
これが、新時代の学校に求められる教員の姿ではないだろうか。
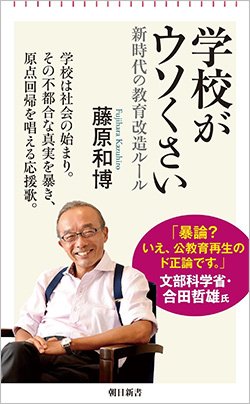 『学校がウソくさい――新時代の教育改造ルール』(朝日新書)
『学校がウソくさい――新時代の教育改造ルール』(朝日新書)藤原和博 著
授業の一部は、その教科のその単元を教える「最高のオンライン先生」の動画でいいと割り切る。YouTubeから探してラインナップを揃えるのは、教職大学の在学中に済ませればいいだろう。教職課程を持つ大学のカリキュラムも、もはや、授業の姿をYouTubeやChatGPT登場以降の姿に変えなければ、ウソくさい!
何度でも言うが、動画なら一時停止もできるし、繰り返し再生できる。スピードも変えられる。生の授業は1回限りなので、ちょっと油断したら聞き逃すし、理解できていなくても終わってしまう。
すでに訪れている超高度に発達したネットワーク社会では、学校という舞台で、授業という演目で、このように「先生」を演じることができる教員が求められていくのだと思う。