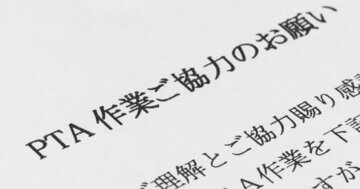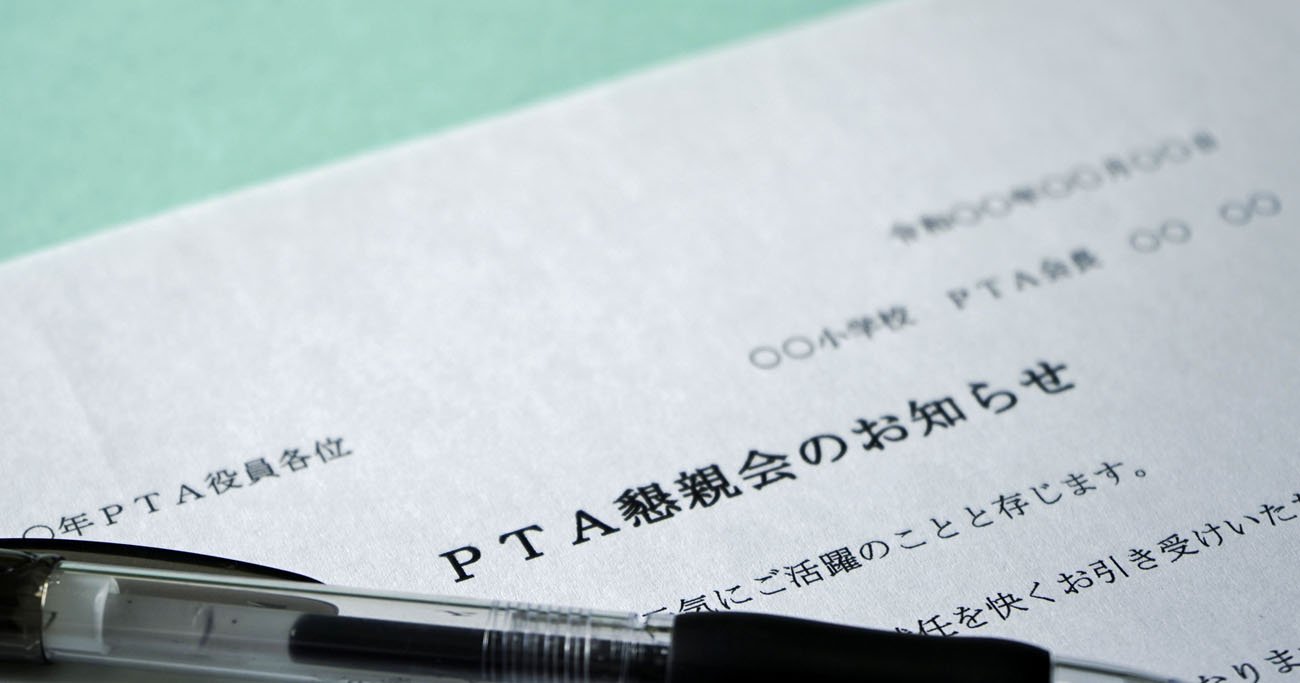 画像はイメージです。Photo:PIXTA
画像はイメージです。Photo:PIXTA
昨今はPTAを解散(廃止)したり、その活動を「代行サービス業者」に委託したりといった学校が増え始めた。解散や外部委託には至らないまでも、ひとまず休止している学校もよく聞くようになった。だが、そうした学校の“後日談”についてはあまり知られていない。短期集中連載「大塚さん、PTAが嫌すぎるんですが…」の#4では、PTA・学校・保護者に豊富な取材経験を持つ筆者が、既存のPTA運営からの脱却を試みた各学校のリアルな現状をリポートする。(ライター 大塚玲子)
PTAの「解散(廃止)」が多発
その背景に何がある?
ここ1~2年、メディアでよく取り上げられるPTAの話題で「解散(廃止)」と「代行サービス(外注)」というものがあります。「これから、我々保護者をラクにしてくれるものかな?」と気になっている方もいるのでは。
PTAの「解散」や「代行サービス」は、それぞれどんな背景や経緯で出てきたもので、これにより学校や保護者の状況はどう変わるのか、ということを今回は見ていきたいと思います。
「PTAの解散」は、筆者がPTAの取材を始めた10年ほど前から、たまに聞くものではありました。ただし、その中身は「強制をやめると同時に名前を変えた」といったものが多く、「解散」というより「改革&改称」というほうが近い印象でした。
つい2~3年ほど前にも「解散したPTAがある」と聞いて問い合わせたら、「PTA改革をしてP連(※)を退会したら、近隣校で『解散した』といううわさが流れた」と、役員さんが困惑していたこともありました。
※「PTA連合会」などの略称で、各地域のPTAのネットワークを指す。
しかし、ここ1~2年で様子が変わってきたと感じます。「PTAを解散して、代わりに行事等のお手伝いをする組織を学校が主導してつくる」という話や、「特に代わりの組織はつくらない」といった話が、以前より増えてきたのです。こうなると、名実ともに「解散」という印象です。
代わりの組織ができるとしても、運営の主な担い手が保護者から学校側に移る点で、PTAとは大きく異なります。本部役員、つまり保護者による執行部が存在せず、会費もなくなるのです。学校側は代わりに新設する組織を、文部科学省が推進する「地域学校協働活動」の一種と考えていることもあるようです。
ではなぜ今、解散に至るPTAが出てきたのでしょうか。
・解散に至るPTAが増えている理由
・「休止」したPTAに潜む意外な注意点
・保護者取材で分かった、PTAを「休止・廃止・外注」した学校の現状