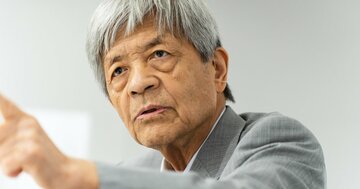お金をぐるぐるまわすだけの活動が
本当に社会に必要だろうか
マルクスは晩年、まとまった著作を残していない。図書館で書いたメモのみが残されている。これを斎藤氏は徹底的に読み込み、そこに「脱成長」を論じるヒントがあった。
中国やソ連などの国家体制を見ると、「社会主義」は失敗しているかのように見える。「資本主義」国家では「社会主義」は排斥されがちだ。
しかし、マルクスが志向したのは、中国やソ連のような共産党による独裁体制ではない。アメリカのミレニアム世代は、現代の地球環境や格差社会への関心が高く、「金持ちになりたい」「環境が犠牲になるのはやむを得ない」といまだに考えるのは「ダサい」という認識が広がっている。平等を打ち出し、持続可能性を考える社会主義(※)が、むしろクールだと受け止められているという。

日本でも、Z世代ではそうした考えを持つ人が増えており、日本においてもこうした価値観の転換を大々的に起こすべきだと斎藤氏。
「一定の最低年収と、一定の最大年収があって、その中では多少の格差や競争はあっても良い」と述べつつ、「今の社会のように、すでに使いきれない富を持っている人たちばかりがますます富み、一方で、年収200万円以下の人たちが増えている、こうした社会は良くないのではないか」と語った。
斎藤氏によれば、介護、保育、医療、農業、清掃業など、なくなると人々の暮らしが成り立たない「エッセンシャルな活動」と、なくなったほうがいい経済活動や生産活動がある。株の高速取引や投資コンサルタントのような、お金をぐるぐるまわすだけの活動が本当に必要なのか? 結局それは、投資する先がないほど資本主義が成熟しているということであり、つまりは、実は必要のない活動ではないのか?
アメリカの人類学者、デヴィッド・グレーバー氏(1961〜2020年)の著書『ブルシット・ジョブ ―クソどうでもいい仕事の理論』(岩波書店)でも、さまざまな「無駄な仕事」が指摘されている。「グラデーションがあり、白黒わけるのが難しい部分はあるが、明らかに必要な仕事とそうでない仕事はある。ただし、それを個人が決めるのは独裁であって、それは避けるべき」と斎藤氏。
「個人の競争を認めれば、経済的な成長を認めることにならないか?」と田原氏が疑問を呈すると、斎藤氏は、「今は『競争』=『お金もうけ』の一辺倒になっている。学問にも競争あるが、『いいものを発見しよう』という競争。スポーツなどの競争も同じ。『お金もうけ』ではない競争を、経済や企業活動の制度設計に組み込む必要があるのではないだろうか」と応じた。
「良い論文を書いて、本が売れれば、学者の地位も安定する。そうすれば収入も増える。やはり競争を認めるということは、経済的にも成長するということであり、最終的にはお金もうけにつながるのでは」と追及する田原氏に、「でもそのもうけは、たかが知れていますから」と答えると、会場の空気が和んだ。