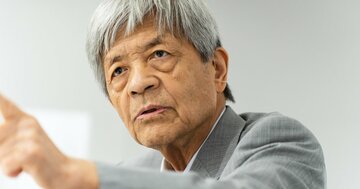「小さなコモン」づくりに
まずは集中せよ
「今の社会は変えられない」「世の中はこういうものだ」とあきらめていることが、最も問題だと思うと斎藤氏。
「田原さんが若い頃の時代は、学生運動で社会が変えられると、若者はみんな、思っていた。そうした強い思いは、資本主義に奪われていった。資本主義というのは、既得権益を持っている人には都合がいいが、アメリカのBLM(Black Lives Matter)や『#MeToo』運動を見ればわかるように、弱者や若い人にも、社会を変える力がある」

「人口の3.5%くらいが変われば、変革は起こせる」(※)と斎藤氏。げんに気候変動に関する考え方は、グレタ氏(グレタ・トゥーンベリ/スウェーデンの環境活動家)ひとりでも変わった。ひとりで世界へ多大なインパクトを与えた。
日本でも、SEALDs(※)は、バックに組織のない若者たちによる活動だったが、「今の日本でもこういうことができる」というインパクトがあった。現在はそうした活動が若い人には継承されておらず、もどかしいが、そこはあきらめないでいたいと言う。
ある大学院生は、同級生の就職活動を見ていると、昔の資本主義とは違った「搾取」を感じるという。就活生が「圧倒的成長」と言いながら就職し、長時間労働をし、資本主義の奴隷になろうとしていて悲しいと発言すると、斎藤氏は「最初から大企業に行きたいと思うような人たちは放っておいていい」と一蹴。それよりも、足場としての「小さなコモン」をいかにつくるかに集中すべきだと説いた。
現在主流の価値観から少し距離をとり、ふと訪れた人が、別の生き方を模索するような、場づくりやきっかけづくりを、今の社会に疑問を持っている者同士でやっていかないことにはどうしようもない。いきなり「主流の価値観にとらわれている人」たちを動かそうとしても行き詰まるだけだ、まずは「小さなコモン」づくりから始めよと、「革命の方法論」を述べた。
田原氏は、そうした「場」が新興宗教になっていると指摘し、だからこそ、われわれが別の場をつくる必要がある、と斎藤氏は強調した。
安全保障と脱成長の
バランスをどうするか
その後、4〜5人のグループに分かれて、ディスカッションが行われた。あるグループからは、「コミュニズムに賛成だが、リアリズムという点で見れば、ロシアのウクライナ侵攻が起きているなかで、(他国からの侵攻に対抗するための)兵器を造らないのは、死活問題ではないか。国際社会との比較のなかで、安全保障と脱成長のバランスをどうとるか?」との疑問を投げかけた。
斎藤氏は、「その論理だと、リアリズムでは、軍拡するしかなくなる。それでは戦争は止められない。(侵攻されないためには)軍拡しかないと選択肢を狭めるなら、それこそが破滅への道。これまで通りの成長戦略では、未来がないことが明らか。だからこそ脱成長をしなければ、さらに戦争のリスクも上がっていく。『平和ボケ』という人もいるが、逆だ。対話を通じた安全保障を実行することが、脱成長型の安全保障ではないだろうか。ウクライナとロシアの戦争の悲惨さを前にして、それが今重要だということが、ますます浮かび上がっていると思う」と答えた。
教育の話をしたという、教員を含んだグループは、「3.5%の仲間を見つけて世の中を変えるためには、私たち教師は何をすべきか、教育はどうしていくべきか?」と問うた。
田原氏は「正解を教える教育をやめるべき」と以前からの持論で応じた。斎藤氏は「正解のない中で、教育現場でのいろいろなチャレンジが、いつしか3.5%になる。チャレンジしていることをシェアしてほしい」と答えた。
宗教の力で社会改革を行えるか、といったことについても話題となった。たとえば、なぜドイツで気候変動の取り組みが盛り上がっているのかを、マルクス・ガブリエル氏(※)に斎藤氏が聞いたところ、キリスト教の存在が大きいからだと言われたという。
一方で、マルクスは「宗教は民衆のアヘン」と、宗教の力を危険なものと見なしている。宗教に頼ると本質を見失うことがあり、たとえば近年話題の「SDGs」も、本質が置き去りのまま企業に活用されてしまっており、斎藤氏は著書で、「SDGsは企業のアヘン」と説いている。