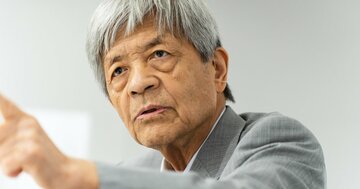人口が減り始めている中
なぜGDPを増やす必要があるのか
会場から「『日本経済が成熟している』とされることの根拠は何か?」という質問が出た。
斎藤氏は「田原さんの若い頃は、カラーテレビ、冷蔵庫など、必要なものをどんどん国民が買っていて、経済成長できた。たくさん働いて、企業が成長して、給料が上がって、資本主義がまわっていた。今はそうした機器が一通り普及し、国民の皆が買うものを企業がつくるのが難しい。買い替え需要しかない。イノベーションとして多くの人が頭に浮かぶものはこの20年ほどでiPhoneくらいしかなく、イノベーションのスピードは落ちている。AIが話題だが、AIは商品をつくらない」と答えた。

「しかし、世界は成長している」という田原氏の指摘に対し、斎藤氏は「アメリカは自国通貨が、基軸通貨であるため、ドルを使って世界の富を収奪できるから成長しているだけ。EUも、ドイツのように、域内の貿易でもうかる国があるだけで、EU全体では落ちている。韓国は出生率が0.8と低く、もうすぐ成長が止まることになる。かつての成長モデルに戻るのは難しい」と答える。
そして、「気候変動もあり、先進国の人口が減り始めている中、なぜGDPを増やす必要があるのか。日本のような成長が止まった国が、中国のようにまだ成長したがっている国に、新たなモデルを示すべきであり、日本自身も自国の魅力を売り出すことで模範的な存在となる。そうした『ソフトパワー』を使うべきだ」と続けた。
会場から、金利トレーダーとして大手投資銀行に勤めていたことのある参加者が意見を述べる。
「『成長』とは何なのかを考えると、この30年間にたしかにいろいろと便利になった。今までは調べ物は図書館に通う必要があったが、今はスマートフォンひとつで調べることができる。過去の映画やドラマを見るためには、レンタルビデオ店でビデオやDVDを借りる必要があったのに、今はYouTubeやNetflixなどの動画配信がある。女性も昔に比べると今のほうが明らかに活躍できている。たばこを吸う人が少数派になり、環境も良くなった。こうしてみると、日本はとても『成長』していると思うのだけれど、賃金だけを見て『成長していない』という人がたくさんいる」
「成長とは何だろうか?」会場の参加者たちに一度、立ち止まって考えてみることを促すとともに、「『賃金が上がること』が『成長』という考えの人にとってみれば、お金を増やすしかなく、ものを売らない限りそういった『成長』はしない。これはもう、『積んじゃってる』のではないか」と問いかけた。
斎藤氏はこれに同意。マルクスが言う、「価値と使用価値」の話で言えば、お金が「価値」で、私たちが実際に自分たちの欲求を満たせるものが「使用価値」。「この30年、経済は成長していない」というけれど、使用価値も、ジェンダー平等も、昔と比べて改善されてきている。しかしそれは、GDPに価値として表れない。だから「日本がだめ」と思う人が多いと、解説。
「GDPのみを見て判断する人は、非正規の社員が増えても、ジェンダー格差が広がっても、企業業績さえ伸びればいいと言いかねなくて、危険。もちろん、今の社会がGDPを指標に動いている以上、GDPや企業業績は無視できない。でも、あまりにもそこだけに集中する社会のあり方が、われわれを貧しくしてきた。それが幸福度を下げたり、地球環境を破壊したりしている」と続けた。
会場から、「脱成長のコミュニズムを前提としたとき、やるべきことは、たとえば、賃金収入の上限や下限を設定することだとしても、それを実行しようとすると、すでに権力や影響力を持っている人が反対するだろう。弱者や若い人たちから変革していくのは難しいと思う。掲げた理念を実現するにはどうすればいいのか?」との声が上がった。