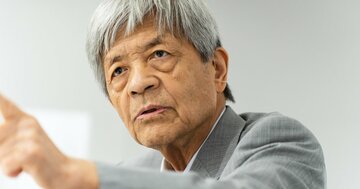「現状のまま何とかなる」
こうした考えこそがユートピア的だ
「社会運動は近年、暴力性がなくなる傾向にあるが、これについてどう思うか?」という会場からの発言があった。
斎藤氏は、ソ連や中国の共産党のような抑圧的なやり方から脱するためには、明確なリーダーがいない社会運動へと転換していることは、良い流れだと思う。過去の社会運動のように公園や建物を占拠する、それだけでは社会は変えられないと気づき、積極的に政治に参加し、そこから変えようとう動きが活発化している。2022年の杉並区の区長選では、市民グループから出馬した候補が現職の区長を破って当選、杉並区初の女性区長が誕生した。政治のフェミナイゼーション(権力維持ではなく、ケアやニーズに寄り添うこと)が自治体レベルで日本にも起こっており、こうした潮流が国政レベルにまで広がれば、日本の未来に希望が持てると述べた。
ある学生は、「『社会主義』とは果たして何か? 現状を一つ一つ変えていく運動そのものが『社会主義』ではないか?」と、「社会主義」の定義を問う。
斎藤氏は、社会主義というのは、目指すゴールがあるのではない。やりながら変わる。マルクスが、達成すべき社会主義の定義をはっきり書かなかったのは、現状の社会に埋め込まれた偏見や価値観も込みで、その定義に投影されるリスクを自戒していたからだと答える。
「私が構想するコミュニズムは、一種のユートピアである。リアリズムの人からは、ばかげていると批判されるが、彼らのリアリズムは現状を肯定し続けること。それで何とかなると考えていることのほうが、よほどユートピア的で、現実を無視している」
斎藤氏は続ける。「理想のコミュニズムが、すぐに実現するとは思っていない。でも、ユートピアを思い描くことで、今の社会を無批判に受け入れず、距離をつくるきっかけをつくり、新しい発想が出てくる。それをどう肉付けするかは、ひとりひとりが考えることだ」。
学生はさらに問う。「改革自体はみんな、毎日少しずつ行っていること。それは当然のことではないだろうか? となると、それはすでに社会主義ではないのか?」。
日々の改革と違う点は、「根本から変える」ことを前提としている点だ。「ただ日常に変化を加える」のではなく、「根本から変えることを前提に絶えず変化を加える」と斎藤氏。「まず、自己変革。そのためには学ぶ場に身を置かなければならない。本や論文を読んでいるだけではだめで、現場に行かなければわからないことはたくさんある。田原さんも日頃から、一次情報が大事と言っている」。
田原氏も「一次情報というのは本当に大事。経済成長も、原発も、賛成派、反対派、それぞれの言い分がある。それは現場に行って直接、話を聞いてみないと、本音や背景はわからない」と発言。
「若い人たちがたくさん来てくれて、普段会えない層の方々と、じっくりと話ができて良かった」と斎藤氏は締めくくって、熱気に満ちた田原カフェは散会となった。