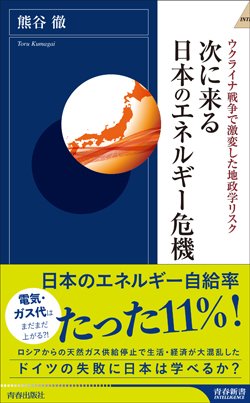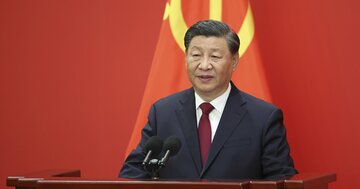2つの文書は「気候変動の抑制などについては、中国と協力する必要があるため、関係を断つデカップリングは行わない」としながらも、「ドイツはエネルギーやモビリティの転換に必要な原材料など一部の領域での中国への依存度が極めて高くなっている。ドイツの過去の対ロシア政策の失敗の教訓を生かして、中国への過度な依存を減らすデリスキングを行う」と明言した。この背景には、長年にわたりロシアのエネルギーに大きく依存して、去年夏に天然ガス供給停止によって梯子を外された、ドイツ政府の苦い経験がある。彼らはこの失敗に懲りて、対中政策を修正しようとしているのだ。地政学的リスクが増した今日の世界では、高い依存度の引き下げが各国政府にとって重要な政策目標になりつつある。
欧州委員会も今年3月16日に「重要原材料法案」を公表した。欧州委員会は、EU経済のレジリエンス(耐久性)を高め、サプライチェーンを守るために、脱炭素化に貢献するネット・ゼロ産業、デジタル産業、航空産業、防衛産業に不可欠な戦略的鉱産資源の自給率を高める。
具体的には、2030年までにEU加盟国が消費する戦略的に重要な鉱産資源の少なくとも15%をリサイクルし、10%を域内で採取する。さらに欧州委員会は、戦略的に重要な鉱産資源については、EU域外の一つの国に依存する比率が65%を超えることを禁止する。EUは名指ししていないが、「一つの国」が中国であることは明白だ。
逆戻りする世界経済のグローバル化
このようにウクライナ戦争によるエネルギー情勢の激変は、戦略的に重要な鉱産資源に対する欧州のスタンスにも変化を及ぼしている。我々が今目撃しているのは、生産費用を抑えるために極端なまでに進んだ「国際分業と経済のグローバル化」という映画の逆回し、つまり経済の非グローバル化、ローカル化の動きである。
発電の主役が化石燃料から再エネに代わっても、限りある資源の奪い合いの構図は変わらない。日本の多くのメディアは大きく報道していないが、重要資源をめぐる争奪戦は、我々日本人にとっても、決して「海の向こうの話」ではすまない。