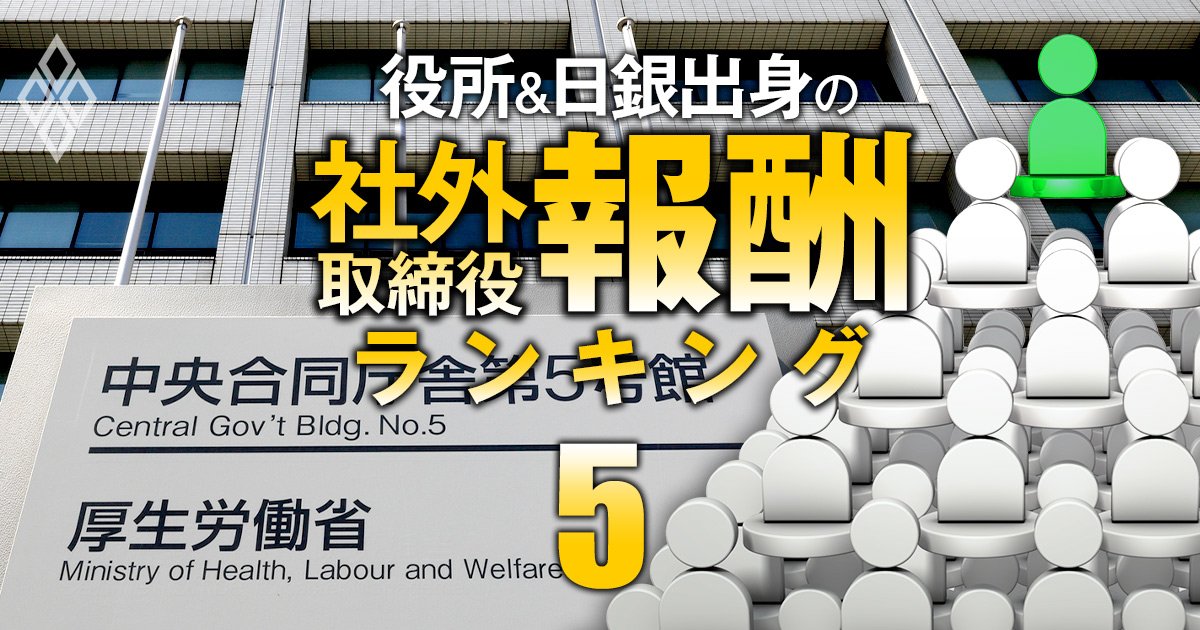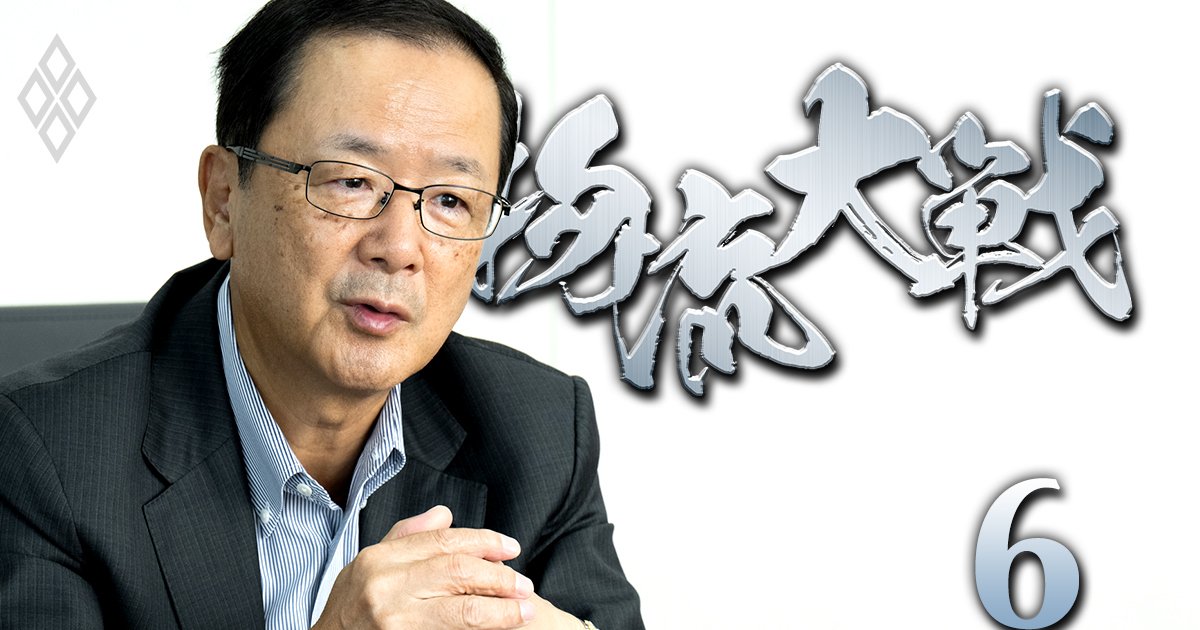「日本人は感情のボキャブラリーが少なかったり、言い出しにくいと感じる傾向があります。でも『今日はタスクがたくさんあって実は会議どころじゃない』など、何かしら感情を抱えているはずなんです。そういったことを少しでも話しやすくするため、8つの感情から選べる形式にしました」(中村氏)
「dive」では、指定したテーマに関連する出来事や思考を振り返り、または1on1で活用するためのもの。自動botが会話を促すためファシリテーションする負荷がなく、お互いに考えをシェアすることに集中できるようにしたという。

「emochanでは『対話のきっかけを作る』『対話をファシリテートする』の2つに力点を置いています。社員同士の個性をかけ合わせてパフォーマンスを発揮していくには、対話は欠かせません」
「しかし、リモートワーク下では仕事に関連すること以外の会話が減ってしまった。コロナで失いつつある雑談を円滑にするのがemochanの狙いです」(中村氏)
本当のターゲットは会社ではなく、社員
中村氏いわく、これまでのコミュニケーションツールは初めこそ自由な使い方がされるものの、次第に「プロジェクト管理」「人材管理」などに重きが置かれ、社員同士が自由に話せる場ではなくなっていくケースも少なくないのだという。
「emochanは法人向けサービスですが、本当のターゲットは社員のみなさんです。そのため、デザインもC(コンシューマー)向けっぽくしています。checkやdiveのサマリーページも基本的には個人ごとの管理としていて、マネージャーや経営層には見えない仕様にしました」(中村氏)
「ターゲットは社員」ならば、法人向けにこだわる必要はなかったのではないか? そんな疑問をぶつけたところ、中村氏の回答はこうだった。
「もちろんC向けにすることも検討しましたが、まずは会社でのコミュニケーションを変えたいと思ったんです。それをきっかけに働く社員が変わり、家族や友人などプライベートへと伝播していく。大きな波を作るには、会社の中を変えることから始めたほうがインパクトがあると考え、法人向けにしました」(中村氏)
また、中村氏の中でemochanとツクルバでの経験はつながっていると話す。
「ツクルバの代表を離れたもう1つの理由は、事業や組織作りで培った知見やエッセンスを広げたいと思ったから。emochanを発展させていきながら、今までの経験を活かしたいと思っています」(中村氏)