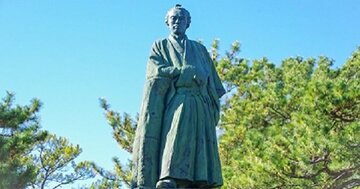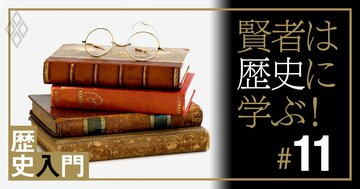森主税と村上真輔の暗殺で
もっとも利益を得たのは誰か
升吉ら13名が森主税と村上真輔を襲撃した事件には黒幕はいたのであろうか。『速記録』の四郎証言によると、襲撃者13名の他にも彼らに同志は多数いたであろうが、そのなかでも特に関係が濃厚であったのが「野上鹿之助・疋田元治・山下恵助」(赤穂藩の下級藩士)とある。そしてこの党派と「もう一つの党派」が結び付いて「暴挙」に及んだと断言する。四郎が述べる「もう一つの党派」とは、失脚していた森続之丞(赤穂藩江戸家老。藩政改革による財政再建を目指したが、手法をめぐって森主税と対立)の党派のことである。
升吉らの党派と森続之丞の党派は、本当に結び付いていたのであろうか。土佐藩京都勤番の目付役下横目源蔵は、文久事件後の12月22日に、赤穂に入り、状況を調査しているのだが、その際の復命書を、土佐藩士・手島八助が日記に書き留めている。そこには、赤穂藩家老・森主税と用人・村上真輔を斬った13人は森続之丞・吉村牧太郎・三木惟春その他十四名と「兼て同志」と記されているのである。
この記述によって、升吉らと森続之丞一派が結び付いていたことが分かろう。四郎によれば、「これ程のことをやったならば、上に引張りがあるから、士分に取り立ててもらえる」と升吉らは考えていたという。森続之丞らから、主税や真輔を殺害したならば「槍一筋の士(それ相応の身分の武士)にしてやろう」との甘言があったのではと、四郎は推測しているのだ。
文久事件後、藩中での噂においても「今度、彼等は、槍を建てて帰るそうな」というものがあったという。森続之丞一派は、復職のため、升吉らを利益をもって唆し、凶行に及ばせたというのだ。
1年前に結成された土佐勤王党による
暗殺事件と状況が奇妙に付合する
このようにして文久2年(1862年)12月9日、赤穂の下級武士らは、同藩の要職にある者を討ち取ったが、この暗殺計画(事件)に「手本があったのでは」と指摘する見解もある(福永弘之「もう一つの『忠臣蔵』1」)。
その手本とは、同じ年の4月8日に起きた土佐藩における吉田東洋暗殺事件だ。東洋(1816~1862年)は、上士の出。土佐藩の参政であり、改革に邁進していたが、藩内の尊攘派志士から反発を受け、土佐勤王党の那須信吾・大石団蔵・安岡嘉助らにより、暗殺される。土佐勤王党は、土佐出身の武市半平太(瑞山)らにより、文久元年(1861年)に結成された。