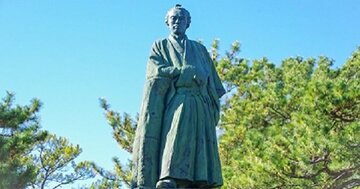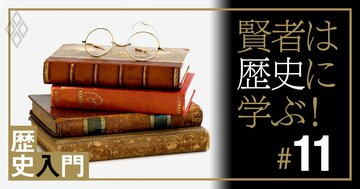郷士だけではなく、上士も含む約200名の武士が同党に加わったが、そのなかには、あの坂本龍馬や、西川升吉と交流があった平井収二郎の名も見える。
東洋は、土佐藩主の山内豊範への講義を終え、自宅への帰路、降りしきる雨のなかで、暗殺された。暗殺が夜間、そして下城途中というところが、文久事件と似ている。
 『仇討ちはいかに禁止されたか? 「日本最後の仇討ち」の実像』(星海社新書)
『仇討ちはいかに禁止されたか? 「日本最後の仇討ち」の実像』(星海社新書)濱田浩一郎 著
升吉が平井収二郎から東洋暗殺のことを聞き、参考にしたとしても、おかしくはないだろう。升吉は収二郎と面会した時に「真輔と申す者を除かねば、国(赤穂藩)は振るわない」と語っていたようだ(土佐藩士・小原与一郎の日記による)。一方で森主税のことについては、何も語らなかったという。
暗殺事件の直前、大坂にいた升吉は、交流ある但馬豊岡藩の志士・田路平八郎に依頼し、自らの書状を平井収二郎に届けさせている。田路は、収二郎に、赤穂藩の要職にある村上真輔を斬るという升吉の決心や、暗殺実行後、実行犯が「七・八人脱走、上京」するので宜しくということを伝えたようだ(瑞山会編纂『維新土佐勤王史』)。これを聞いた収二郎は、赤穂脱走は下手人のみとし、他の同志は赤穂に留まり、「藩論を勤王に決せしめよ」と、田路に述べたと言われる。
土佐の平井収二郎は、赤穂で暗殺事件が起こり得ることを事前に知っていたのだ。文久事件には、土佐の尊攘派が絡んでいたことが、ここから理解できよう。升吉らは、内では森続之丞一派と結び、外では土佐の尊攘派と連携し、事を起こしたのだ。穏便な方法では藩政改革は成らずとして、過激な行動に打って出たのである。