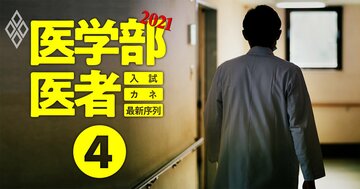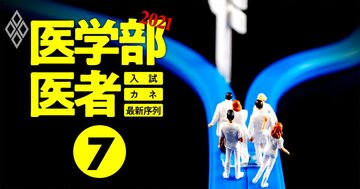医薬分業が進んだこのご時世
薬を多く出しても医者は儲からない
これまで医療は出来高払いと述べてきたが、厳密に言うとちょっと違う。今はもうあまり言わないと思うが、昭和の医療は薬漬けという言葉があり、開業医を非難してそう表現することがあった。当時の診療所は院内に薬局を併設しているところが多く、薬価差益といって、仕入れた薬価代金と処方したときの公定価格の差の分を儲けとしていたことが多かった。つまり処方すればするほど儲かるわけである。
ところが現在は医薬分業が進み、この問題は解消されつつある。院内処方よりも院外処方の方が医療報酬が高いので、新規に開業するクリニックで院内薬局を併設する所はかなり減っている。院内薬局を併設しようと思ったら、診療所の中に薬局を作らなければいけないのだから、そのコストは人件費を含めて莫大になる。
国はさらに、医者が薬をたくさん出すのを抑えようとしている。院外処方で、内服薬が6種類以下のとき、処方箋料は68点(=680円)だが、7種類以上になると40点(=400円)に減額される。薬をたくさん出すと「損」になるのである。こういう誘導もあって、無闇に(不要な)薬を出す医者はかなり減ったのではないか。ただし、医者が儲けようとして必要な薬を削って6種類以内に収めようとするのは論外であるが。
6歳未満の小児医療の特別ルール
「マルメ」は何もしないほうが儲かる
小児医療に関しては特別なルールがある。小児科外来診療料というものだ。対象患者は6歳未満。これは出来高ではなく、どんな医療をやろうとも、報酬金額が一定というものだ。こういう医療形態を包括医療といい、業界内ではマルメ(金額を丸め込む)と呼ばれている。検査をやろうが、処置をしようが、報酬は同じである。つまり露骨に言えば、何もしない方が儲かるということになる。
初診料は599点(=5990円)、再診料は406点(=4060円)である。ところがさらに、処方箋を出さないと、初診料は716点(=7160円)、再診料は524点(=5240円)に跳ね上がる。薬も出さず、ただ話をしていれば一番儲けが出るというシステムだ。いや、ただ話をするだけというのは言い過ぎだ。しっかり説明するということだ。