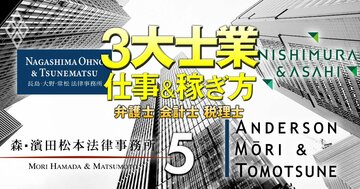『腐敗する「法の番人」:警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う』(平凡社新書、平凡社)
『腐敗する「法の番人」:警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う』(平凡社新書、平凡社)鮎川 潤 著
とりわけ新型コロナウイルスの感染が問題になっていたような時期には部屋の確保も難しく、調停の日程でさえも数カ月先になってしまうことが起きていた。
申立人や相手方である利用者がせっかく仕事の休みを取って、家庭裁判所まで遠路出てきたにもかかわらず、ほとんど無駄足になってしまった。
家庭裁判所の現状を示すものとして、新年度に異動してきたり、職場に復帰したりした家庭裁判所調査官や書記官の挨拶の文章で、子育てについて触れているもののなかから2例のみ要約して紹介しよう。
●育休明けの家庭裁判所調査官の挨拶の例
<子ども二人について育休を4年間取得して、4月に職場に戻ってきました。経験が乏しいとともに、自分の育休中に法改正があったので、以前とは状況が異なる分野を、7年ぶりに担当することになりましたので、よろしくお願いします。>
●育休明けの書記官の挨拶の例
<12年前に書記官に任官しましたが、二度の育休を取ったので、実際の仕事の経験年数は6年ほどになります。初めての分野の仕事のためご迷惑をかけるかもしれませんが、よろしくお願いします。>
裁判所はすばらしい労働環境を提供している。それは日本の他の職場が理想として実現する目標にふさわしいと言ってもよいものだ。ただし、現状を見ると、裁判所が利用者のことを第一に考えるのではなく、裁判所に勤務する人のための機関となってしまっている面もなくはない。
利用者を尊重した、利用者にしわ寄せがいかない、利用者優先のシステムへと改善したり、工夫したりする必要があるだろう。